相続登記を申請する際の注意点は多岐にわたります。
どういった点に注意すべきかは事案ごとにさまざまなのですが、この記事では、その中でも広く当てはまることが多い注意点について8つ解説します。
※本記事は、公開時点での法令等に基づいて作成されております。最新情報については、専門家にご相談いただくか、ご自身でご確認ください。
相続登記に関する注意点8選
不動産の調査もれ
被相続人名義の不動産を調査するには、
- 権利証
- 固定資産税納税通知書
- 名寄帳
これらの書類を確認する方法があります。
固定資産税納税通知書には非課税不動産が記載されないため、名寄帳も取得するのが無難です。
ただし、市区町村により共有名義の不動産が記載されない場合があるため注意が必要です。
被相続人よりも前に開始した相続で登記手続が行われていない場合などに、共有名義の不動産があることを見落として手続を進めてしまうおそれがあります。
そのため、名寄帳を請求する際には、共有名義のものも含めてすべての不動産が記載されているものを請求するように気をつけなければなりません。
さらに、念を入れるのであれば公図や住宅地図を駆使して調査をする方法もあります。
どこまで調査をするべきかは一概には言えませんが、登記もれのリスクは後になって大きな問題につながりますので、事案ごとに十分な調査をしておくべきでしょう。
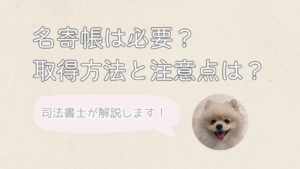
相続関係の見落とし
相続人を特定するためには、必要な範囲の戸籍を収集し、そこから相続関係を読み取る作業が必要です。
被相続人が婚姻と離婚を繰り返している場合や相続人がすでに亡くなっている場合、養子縁組が関わる場合など、相続関係が複雑になります。
戸籍上の記載から正確な相続関係を読み解くのは、慣れていないと難しいかもしれません。
相続人を間違えてしまうとその後の手続すべてが成立しなくなってしまいますので、相続関係を見落とさないようにご注意ください。
遺産分割協議書の記載方法
遺産分割協議で不動産の取得者を決めると、合意内容を遺産分割協議書というかたちで書面にします。
この際に、不動産の記載方法を間違えると、相続登記の申請に使用できない場合があるためご注意ください。
司法書士に相続登記の依頼をすれば、遺産分割協議書も作成してくれるため安心です。
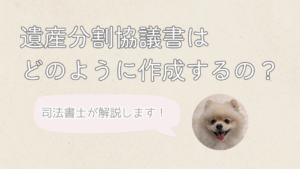
判断能力の衰えがある場合
遺産分割協議をするには、一定の判断能力があることが必要です。
認知症などで相続人のうち一人でも判断能力に問題があると、遺産分割協議を有効に成立させることができません。
衰えの程度によりますが、成年後見人の選任申立という家庭裁判所の手続が必要となる場合もあります。
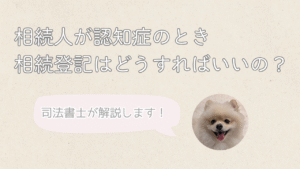
子どもが未成年の場合
未成年者が完全に有効な法律行為を行うには、親権者の同意や代理が必要です。
遺産分割協議についても同様なのですが、配偶者自身も相続人であるため、子の法定代理人として遺産分割協議を行うことができません。
そのため、家庭裁判所に特別代理人を選任してもらう手続が必要となります。
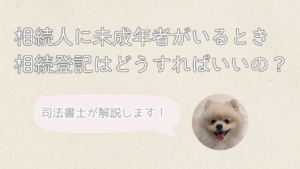
登録免許税の免税措置
相続登記を申請する際、登録免許税の免税措置を受けられる場合があります。
免税には、所定の文言を申請書に記載する必要があり、記載しなければ当該措置の適用を受けることができません。
適用可否について検討したうえで、可能な場合は忘れずに記載をするようにご注意ください。
登記識別情報通知の不通知
登記識別情報通知は任意で「不通知」とすることができます。
ただし、特段の事情がない限りは、不通知としないことをおすすめします。
将来的に売却等をする場合に、資格者による本人確認情報の作成が必要となり、その費用がかかるからです。
同様の理由で、いわゆる「保存行為」による相続登記の申請もおすすめできません。
申請人となる相続人には登記識別情報通知が発行されますが、申請人ではない相続人には発行されないからです。
他の共有者の分は本人確認情報の作成が必要となり、やはり費用の負担が発生してしまいます。
補正の対応
登記申請書や添付書類に不備があると、「補正」という訂正対応を求められることがあります。
補正の方法は、書面申請の場合、申請書の不備については登記所の窓口に出頭して行います。
添付書類の不備の場合は、窓口で訂正するか、新たな書面と差し替えることにより行います。
添付書類を差し替える場合は郵送でも可能ですが、基本的には登記所の窓口に行かなければならない点にご注意ください。
なお、オンライン申請の場合は、申請書の補正をオンライン上で行うことが可能です。
また、不備の内容が補正することができないものである場合は、相続登記の申請が却下されます。
ただし、いきなり却下ということはなく、取下げを促されるのが一般的です。
効果的な対策方法は?
正直なところ、相続登記に関する注意点をすべて対策し尽くすことは現実的ではありません。
そのためには民法や不動産登記法、関連する法令等の理解が必要で、それらを一朝一夕に身につけることなど到底できっこないからです。
よって、効果的な対策方法は、専門家へ依頼すること、これに尽きます。
法務局の登記手続案内などを利用して、登記申請書を作成することはできるかもしれません。
ですが、問題なく登記が完了したとしても、不動産の調査もれや遺産分割協議に関するトラブルなどが後になって大きな問題となる可能性もあります。
司法書士に相続登記を依頼すれば、すべて不備なく手続を終えられますので安心です。
まとめ
この記事で解説した相続登記に関する8つの注意点は、私がこれまで相談してきたなかで、実際に見聞きした話をもとにしています。
他にも相続登記の注意点は挙げればキリがないくらいですが、上記のものは多くの方に当てはまる内容だと思います。
相続登記を促進するための法改正が進み、一般の方でも書類を集めたりしやすくなりましたが、登記の申請となると、まだまだ敷居が高いと言わざるを得ません。
司法書士に相続登記を依頼をすれば、すべて不備なく手続を終えられますので、まずはお気軽にご相談ください。
この記事が参考になれば幸いです。
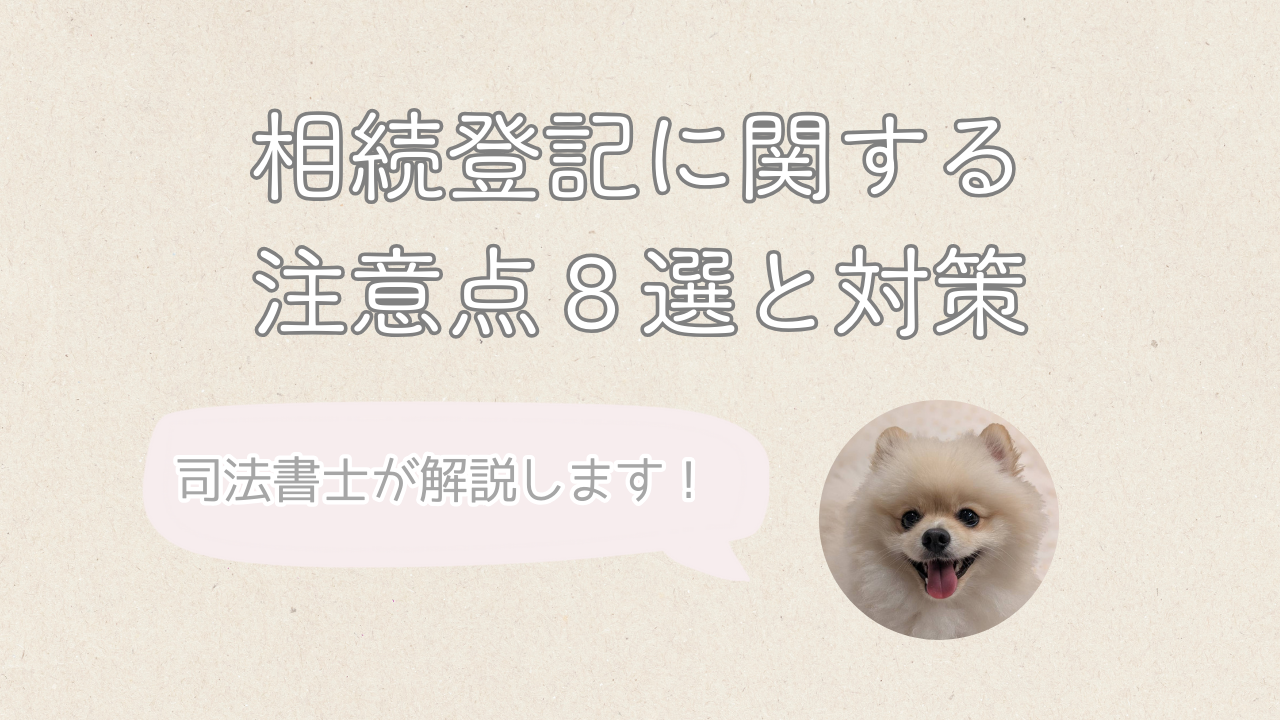
コメント