名寄帳とは、市区町村が課税のために作成している固定資産の登録簿の一部で、その市区町村内で、ある人が所有している不動産の一覧を確認できる書類です。
読んで字のごとく「名」で不動産を「寄」せるわけですね。「固定資産課税台帳」と呼ばれることもありますが、名寄帳で通じるのでこれで覚えて大丈夫です。
絶対に必要というわけではありませんが、相続登記もれを防ぐためには取得すると安心です。
この記事では、相続登記で使うことも多い名寄帳の取得方法や注意点について解説します。
※本記事は、公開時点での法令等に基づいて作成されております。最新情報については、専門家にご相談いただくか、ご自身でご確認ください。
名寄帳の取得方法
相続登記では、名寄帳を 「亡くなった方がどの不動産を持っていたのかを調べる」際に利用します。
権利証を紛失している場合、被相続人の方が生前にどの不動産を所有していたのかを把握することが困難になります。
毎年、納税義務者のところに届く固定資産税課税明細書(課税明細書)にも不動産の所在地について記載がありますが、こちらは課税不動産が対象となり、非課税不動産については記載されません。
そのため、被相続人が所有していたことに気づかず、相続登記もれが発生してしまうことがあるのです。
名寄帳には原則として、これらの不動産も記載されるため、相続登記の対象となる不動産を調査する際に役立ちます。
請求先
名寄帳が取得できるのは、不動産がある市区町村役場です。
固定資産評価証明書と同じで、市区町村単位で管理されています。
そのため、複数の不動産を所有している場合、他市区町村に対して請求をする必要があります。
申請方法
名寄帳を取得するには、以下の方法があります。
- 窓口での直接申請
- 郵送申請
- オンライン申請(対応している自治体のみ)
窓口で取得するのが一番確実かつ手っ取り早い方法ですが、遠方の場合は郵送の方法によらざるを得ません。
オンライン申請は、有効な電子署名期間のあるマイナンバーカードが必要で、対応している自治体には限りがあります(2025年5月現在。順次拡大中)。
必要書類
市区町村により異なりますが、一般的には以下の書類が求められます。
- 申請書(市区町村の様式。窓口またはインターネットでダウンロード)
- 被相続人の死亡の記載がある戸籍
- 相続関係が分かる資料(戸籍など)
- 申請者の本人確認書類
市区町村によって異なるため、各役場のホームページなどで事前に確認してください。
手数料
こちらも市区町村によって異なりますが、大体200~400円です。
なお、縦覧期間中(毎年4月から6月の間。自治体による)は、無料で名寄帳の取得ができる自治体もあります。
これは、固定資産税の課税の基礎となる価格等を納税義務者が比較したりできるように各市区町村が定めているもので、この期間中であれば、無料で名寄帳の内容を見ることができます。
ただし、原則として写しをとったりすることは認められておらず、メモ等に書き取る必要があります。
ところが、一部の自治体では縦覧期間中の名寄帳の交付手数料を無料としているため、手数料を支払うことなく取得することができるのです。
自治体によって縦覧期間や縦覧場所が異なります。各役場のホームページ等でご確認ください。
注意点
名寄帳はその市区町村内にある不動産の一覧です。
つまり、被相続人が複数の自治体に不動産を所有していた場合は、各市区町村で名寄帳を取得する必要があります。
また、その年度の1月1日時点での所有状況について記録されているため、1月2日以降に売買・贈与・相続などによって取得した不動産については記載されておらず、反対に1月2日以降に売却した不動産等が記載されている点にも注意が必要です。
よって、相続財産の調査には最新の登記簿謄本を取得する等、現在の権利状況を確認することが必要となります。
登記簿謄本の取得方法についてはこちらの記事もご覧ください。
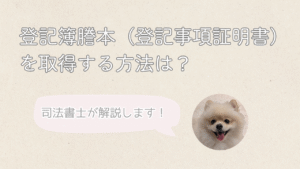
まとめ
この記事では取得の方法や注意点について簡単に説明しました。
相続登記をする上で、名寄帳が絶対に必要かといわれると、そうとも言い切れません。
実際に、被相続人の所有していた不動産が明確で、地番なども明らかになっている場合は、名寄帳を取得せずに相続登記を申請する場合もあります。
ですが、不動産のもれなく相続登記を進めるため、名寄帳を取得すると安心です。
縦覧期間中の取得であれば手数料もかかりませんし(※自治体によります)、より安心して手続を進めるためにも取得することをおすすめします。
この記事が参考になれば幸いです。
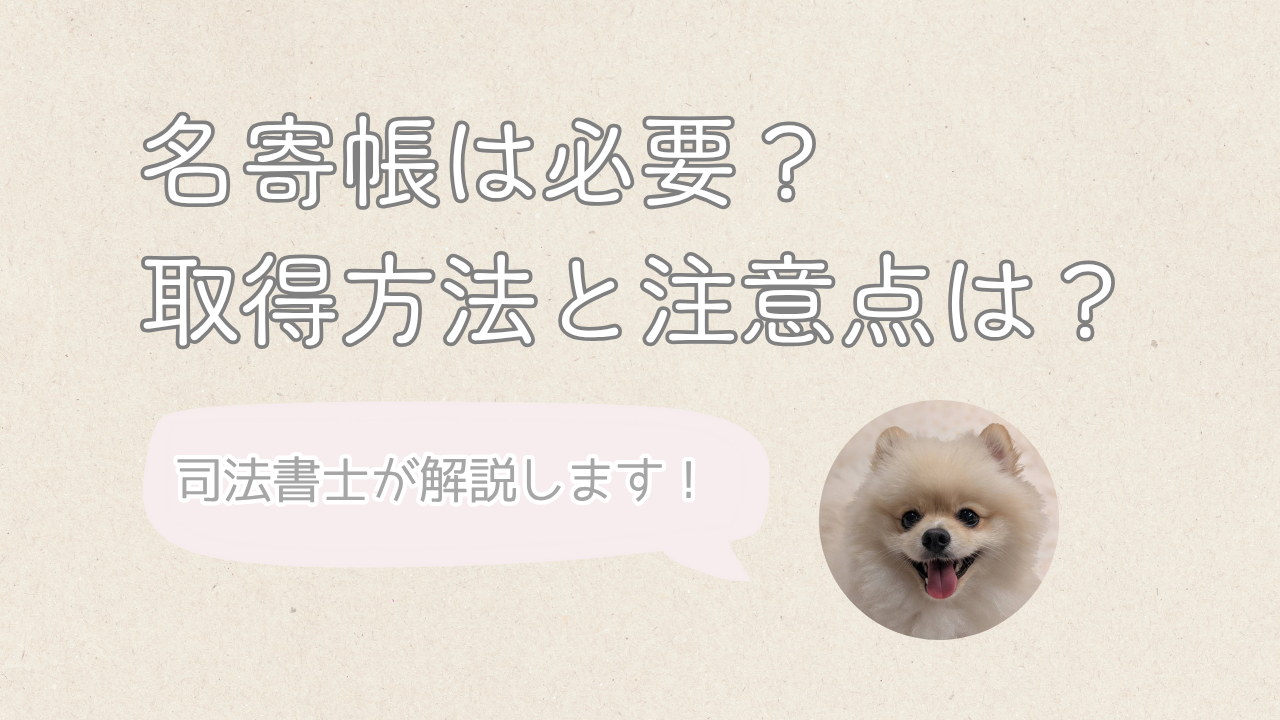
コメント