複数の相続人がいる場合、不動産の名義を誰にするかを決めるためには、相続人間で話し合いを行い、その結果に基づいて遺産分割協議書を作成します。
相続登記には、遺産分割協議書と印鑑証明書を提出する必要がありますが、そもそも印鑑登録をしていなければ、印鑑証明書を取得することができません。
この記事では、印鑑登録の基本と注意点、家庭裁判所の手続が必要になる場合について解説します。
※本記事は、公開時点での法令等に基づいて作成されております。最新情報については、専門家にご相談いただくか、ご自身でご確認ください。
印鑑登録の方法と注意点
印鑑登録をしていない場合は、印鑑証明書を取得できないため、相続登記に必要な書類が整いません。
そのため、まずは役場で印鑑登録をする必要があります。
印鑑登録のやり方は?
印鑑登録は住所地の市区町村役場にて行います。
基本的に本人が窓口で写真付きの身分証明書(運転免許証やマイナンバーカードなど)を提示すれば、即日で登録し、印鑑カード(印鑑登録証)の交付を受けることができます。
しかし、持参した身分証明書が健康保険証など写真付きでないものである場合は、照会書の郵送による方法によらざるを得ないため、登録までに時間がかかってしまいます。
自治体によって異なりますので、どれくらい時間がかかるのかなど、詳細については役場に確認してください。
印鑑登録は代理人でもできる?
代理人による印鑑登録も可能です。一例として、以下のような書類が必要となります。
- 委任状(本人が自署したもの)
- 本人の身分証明書(運転免許証など)
- 代理人の身分証明書(運転免許証など)
身分証明書はいずれも原本が必要です。
申請した後、本人の住所に届いた照会書に記入押印して窓口に持参します。
そのため、申請してから登録までに時間がかかります。
本人作成の委任状と照会書には、登録する印鑑を使用して押印します。
実印の悪用を防止するため、本人の意思確認が厳格に行われています。
必要書類や手続の流れは自治体によって異なりますので、ホームページで調べるか、役場の窓口でご確認ください。
印鑑登録の注意点は?
登録できる印鑑には制限がありますので、ご注意ください。
三文判や、材質が変形しやすいもの、すでに欠けてしまっているものなど、実印として登録できない印鑑もあります。
また、本人の意思が確認できない場合も印鑑登録をすることはできません。
事情があって窓口に行くことができない方でも、委任状や照会書の自署と身分証明書(原本)の提示という方法によって、印鑑登録の意思を確認できる必要があります。
家庭裁判所の手続が必要になる場合も
以下のような場合には、家庭裁判所の手続が必要になります。
親権者が未成年者を代理できない場合
相続人に未成年者がいる場合、遺産分割協議書には親権者が法定代理人として親権者の実印で押印します。そのため、未成年者の印鑑登録は問題になりません。
しかし、その親権者も相続人である場合や、複数の未成年者の親権者が同一である場合など、親権者が未成年者を代理することができない一定の場合には、家庭裁判所の手続が必要となります。
相続人に未成年者がいる場合については、こちらの記事も参考にしてください。
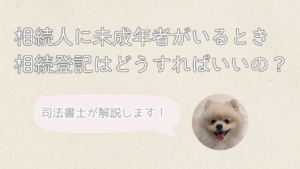
相続人が重度の認知症の場合
また、相続人が重度の認知症である場合、印鑑登録をすることができません。
ですが、印鑑証明書以前に、遺産分割協議自体が無効となりますので、印鑑登録は問題になりません。
このような場合も、家庭裁判所の手続が必要となります。
相続人に重度の認知症の方がいる場合については、こちらの記事も参考にしてください。
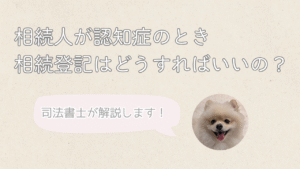
まとめ
印鑑登録は、本人が住所地の役場窓口に行って写真付きの身分証明書を提示することで、簡単に手続することができます。
ただし、事情があって本人が窓口に行けない場合や写真付きの身分証明書がない場合、代理人による手続の場合は少し複雑になります。
まずは住所地の役場に確認するのが安心です。
また、家庭裁判所の手続が必要な場合は、専門家である司法書士や弁護士に相談することをおすすめします。
この記事が参考になれば幸いです。
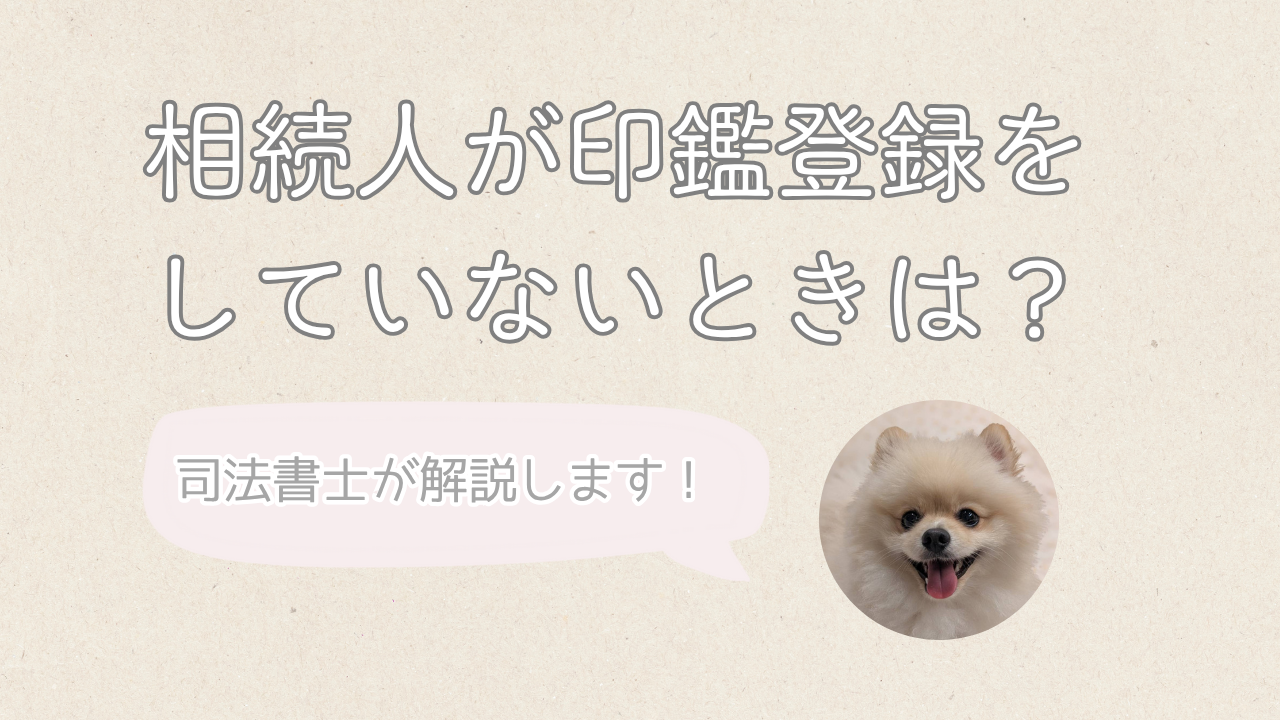
コメント