A. その人の相続人が代わりに権利を引き継ぐことになります。
相続登記をしないでいるうちに、相続人が亡くなってしまう場合も少なくありません。
例えば、父Aの名義になっている自宅の土地建物があり、父Aが亡くなった時点で妻Bと子C・Dは相続人だったが、後に妻Bも亡くなってしまうようなケースです。
この場合、妻Bを子C・Dが相続することになり、相続関係がやや複雑になります。
また、子がC一人の場合は、異なる手続が必要になる場合もあります。
この記事では、上記の事例をもとに、数次相続の基本的な考え方を解説します。
※本記事は、公開時点での法令等に基づいて作成されております。最新情報については、専門家にご相談いただくか、ご自身でご確認ください。
相続人がいつ亡くなったか?
被相続人の死亡時点で相続人が確定します。
いつ亡くなったかで「代襲相続」と「数次相続」に分かれます。
被相続人の死亡以前に亡くなった場合
被相続人の死亡以前に亡くなっている場合、その人は相続人にはなりません。
上記設例でいえば、妻Bが父Aより先に亡くなっている場合、妻Bは父Aの相続人にはなりません。
被相続人より先に亡くなっているのが、子・兄弟姉妹の場合は、孫や甥姪が相続人となります。
上記設例でいえば、子Cが先に亡くなっている場合、その孫が代襲して父Aの相続人となります。
このように、子・兄弟姉妹の代わりに孫や甥姪が相続人となることを代襲相続といいます。
なお、子や兄弟姉妹のことを「被代襲者」といい、孫や甥姪のことを「代襲相続人」といいます。
また、孫も亡くなってしまっている場合は、再代襲といって、曾孫が相続人となります。
被相続人の死亡後に亡くなった場合
上記設例のように、父A亡後、妻Bが他界した場合です。
この場合は、父Aの相続にかかる相続人は、亡妻B、子C・Dです。
すでに亡くなっている妻Bも相続人である点に注意してください。整理すると以下のようになります。
- 父Aの相続→相続人=亡妻B、子C・D
- 妻Bの相続→相続人=子C・D
このように、ある相続において相続人だった方が亡くなったことにより二次的な相続が発生した場合を数次相続といいます。
数次相続の場合は、複数の相続関係を内包するため対応方法もやや複雑になります。
代襲相続と数次相続の対応方法
代襲相続と数次相続の場合、相続関係が複雑になるため、通常の相続登記とは異なる対応が求められます。
ここでは、ごく基本的な考え方について簡単に説明します。
代襲相続
とはいえ、代襲相続の場合はそこまで難しくありません。
- 被代襲者の出生から死亡までの戸籍を集める
- 代襲相続人を特定する
- 代襲相続人の戸籍を取得する
基本的にこれだけです。
上記設例でいえば、子Cが父Aより先に亡くなった場合、子Cの出生から死亡までの戸籍を集め、孫を特定し、孫の戸籍を取得するという流れになります。
数次相続①(子が2人)
どちらかというと、数次相続の方が大変です。
第一の相続の相続人の人数や、第二の相続開始時点での遺産分割協議の有無によっても、相続登記の手続が大きく異なってきます。
まずは、子が2人のケースから説明します。
結論から言うと、父A亡後、妻Bが亡くなった場合、子C・Dは2人で父Aの遺産分割協議を行い、父Aから直接子Cへの相続登記をすることができます。
本来は、妻Bと子C・Dの3人で遺産分割協議をするべきですが、妻Bの相続によって、子C・Dは妻Bの「父Aの相続人」としての地位を承継しています。
よって、妻Bの代わりに子C・Dが遺産分割当事者として協議を行い、子Cへ自宅の権利を取得させることができるのです。
数次相続②(子が1人)
次は、子がC一人のケースについて説明します。
上記と同じように、妻Bが亡くなり、子Cは妻Bの「父Aの相続人」としての地位を承継し、遺産分割協議ができるように思えます。
しかし、相続人一名による遺産分割協議は認められていません。
この場合は、亡妻Bと子Cへの所有権移転登記をして、亡妻B持分全部移転登記をする必要があります。
なお、妻Bの生前に子Cとの間で遺産分割協議がなされた場合、妻B亡後に子Cが単独で作成した遺産分割協議書に基づいて、父Aから子Cへ直接相続登記をすることが認められています。
ただし、あくまでも例外的な取扱である点に注意が必要です。
数次相続③(子が死亡)
今度は、妻Bではなく子Cが亡くなった場合について考えます。
父Aの相続人は、妻Bと子C・Dです。
子Cの相続人が孫E・Fのとき、不動産の取得者を孫Eとしたい場合に、どうすればよいでしょうか。
妻Bと子D、孫E・Fによる遺産分割協議によって、父Aから孫Eへの相続登記が可能です。
亡父Aについての遺産分割協議で子Cを取得者とし、亡子Cの遺産分割協議で孫Eを取得者とします。
そして、父A→子Cと子C→孫Eの相続登記を一件で申請します。
まとめ
代襲相続と比較しながら数次相続の基本的な考え方を説明しました。
数次相続がある場合の手続は、通常の相続登記と比べて一段と大変になります。
相続関係が複雑になり専門知識を要しますので、司法書士や弁護士に相談することをおすすめします。
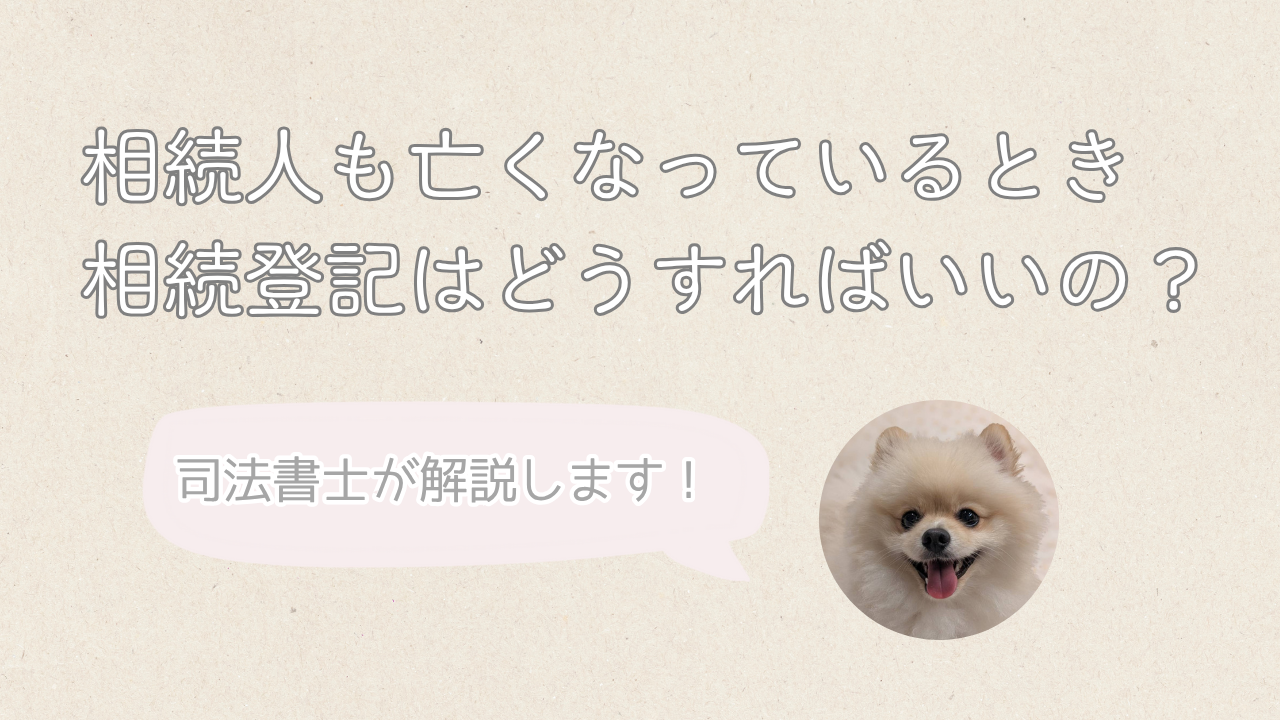
コメント