相続手続において、遺言書の有無で内容が大きく異なります。
基本的には遺言が優先するため、その内容に従って遺産を分配することになります。相続登記に関していえば、「遺贈」か「相続」かによって申請書の内容や必要書類も異なります。
また、手続が完了した後から遺言書が見つかった場合は、遺言の内容に合わせて遺産を分配し直す必要が出てくることもあります。
そのため、被相続人が亡くなったらまずは遺言書の有無を確認することが重要です。
この記事では、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「法務局で保管された自筆証書遺言」の探し方について、解説します。
※本記事は、公開時点での法令等に基づいて作成されております。最新情報については、専門家にご相談いただくか、ご自身でご確認ください。
自筆証書遺言の探し方
自筆証書遺言の保管場所は?
この中で最も探しにくいのが自筆証書遺言です。
誰の関与もなく一人で作成することができるため、保管場所を知らされていなければ遺品の中から探すことになります。
主な保管場所は以下の2つです。
- 自宅
- 銀行(貸金庫)
自宅の金庫・引き出しなどに銀行や不動産関係の書類と一緒に保管されていることもあります。
ただし、遺言書を関係者(友人や士業者、福祉関係者等)に預けていたりと、その保管方法は一様ではありません。
結局、思い当たる場所を一つずつ探してみるしかありません。
自筆証書遺言を発見したら?
遺言書が見つかった場合は家庭裁判所での「検認」手続が必要です。
封がされている場合に勝手に開封すると罰則(過料5万円以下)が適用される場合もあります。早く中身を確認したいところですが、検認期日まで開封しないようにしましょう。
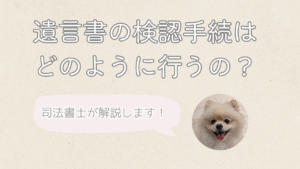
公正証書遺言の探し方
遺言検索システムで簡単に確認可能
公正証書遺言を探すのは簡単です。
- 最寄りの公証役場に行く
- 遺言書を検索したい旨を申し出る
これだけです。
全国どこの公証役場でも、「遺言検索システム」によって公正証書遺言の有無を確認できます。
相続人や利害関係人が本人の死亡後に請求でき、費用はかかりません。
公証役場によっては、事前予約等が必要な場合もありますので、窓口に行く前に電話等で確認しておいた方がよいでしょう。
遺言検索システムの必要書類
- 被相続人の死亡の事実が確認できる戸籍(除籍)謄本
- 相続人であることを証する戸籍書類
- 請求者の本人確認書類(運転免許証など)
写真付きの公的身分証明書がなければ、印鑑証明書(発行日から3カ月以内のもの)でも大丈夫です。
公正証書遺言の内容を確認するには?
遺言書の存在が確認できた場合でも、すぐに内容を確認することができるとは限りません。
遺言書を保管している公証役場に対して謄本の交付請求をする必要があります。
遠方の場合に直接出向く必要はなく、郵送による請求が可能で、その場合の必要書類も交付請求書以外は遺言検索システム利用時と同様です。
また、上記の自筆証書遺言とは異なり検認は不要ですので、すぐに相続登記手続等に進めます。
法務局保管の自筆証書遺言の探し方
遺言書保管事実証明書の交付を請求する
法務局(遺言書保管所)に保管された自筆証書遺言も比較的簡単に探すことができます。
遺言書の保管の有無を確認するには、「遺言書保管事実証明書」の交付請求をします。
相続人・受遺者・遺言執行者等の利害関係人が郵送または窓口にて申請します。
全国どこの遺言書保管所でも可能ですが、窓口で手続をする場合は事前予約が必要です。
下記のリンクから法務局を選択して来庁予約ができます。
遺言書保管事実証明書の必要書類
- 交付申請書
- 被相続人の死亡の事実を確認できる書類
- 相続人であることを証する戸籍書類
- 請求者の住民票の写し
- 請求者の本人確認書類 ※窓口請求の場合のみ
- 返信用封筒 ※郵送受取の場合のみ
手数料は800円で、印紙を貼付する方法により納付します。
交付請求書は、法務局の窓口に設置されていますが、こちらからダウンロードすることも可能です。
遺言書の保管が確認できたら?
保管の事実が確認できたら、「遺言書情報証明書」の交付請求をします。
遺言書情報証明書とは、遺言書の謄本に相当するもので、交付請求には手数料が1400円掛かります。
原則として、被相続人の出生から死亡までの戸籍、相続人全員の戸籍及び住民票の写しが必要となりますが、法定相続情報一覧図の写しがあれば、これに代えることができます。
検認が不要である点は、公正証書遺言と同様です。
亡くなった時に通知がある?
法務局保管の自筆証書遺言だけ通知制度がある
遺言書を書いていることを誰にも伝えていない場合、遺された人がその事実に気付くことは困難です。
そこで、一定の場合に遺言書を保管している旨を通知する制度があります。
上記のうち、遺言者が亡くなったときに通知があるのは、法務局保管の自筆証書遺言のみです。
通知には、①関係遺言書保管通知、②指定者通知の2つがありますが、遺言者が亡くなったときにされるのは、②指定者通知です。
遺言書保管官が遺言者の死亡の事実を確認した場合に、遺言者が指定した人(最大3名)に対して、遺言書が保管されている旨の通知書を送付するものです。
また、書面上には遺言書の閲覧・遺言書情報証明書交付請求に必要な情報として下記の事項が記載されます。
- 遺言者の氏名
- 遺言者の生年月日
- 遺言書が保管されている遺言書保管所の名称
- 保管番号
指定者通知を受領した人が遺言書の閲覧等を行うことにより、①関係遺言書保管通知がなされ、その他全ての相続人等にも、遺言書が保管されていることが通知されます。
ただし、通知されるかは遺言者の任意
この通知は、死亡届の提出等を端緒として市区町村の戸籍担当部局と遺言書保管所が連携し行われます。
遺言書の保管申請書には【指定する者に対する死亡後の通知等欄】があり、通知を希望する場合は、氏名・生年月日・本籍・戸籍の筆頭者の情報を遺言書保管官が戸籍担当部局に提供し、死亡の事実に関する情報を戸籍担当部局から取得する旨に同意することになっています。
そのため、通知が行われるかは遺言者の任意であり、遺言者が希望しない場合は通知が行われません。
通知がない=法務局に保管されていないというわけではありませんのでご注意ください。
まとめ
以上、遺言書の探し方について簡単に見てきました。
遺言書の有無によって相続手続の内容は大きく異なります。
後で遺言書が見つかった場合は、遺産を分配し直す必要が出てきたり、当事者間でトラブルにつながるおそれもあるため、被相続人が遺言書を書いている可能性があるなら、まずは探してみることをおすすめします。
この記事が参考になれば幸いです。
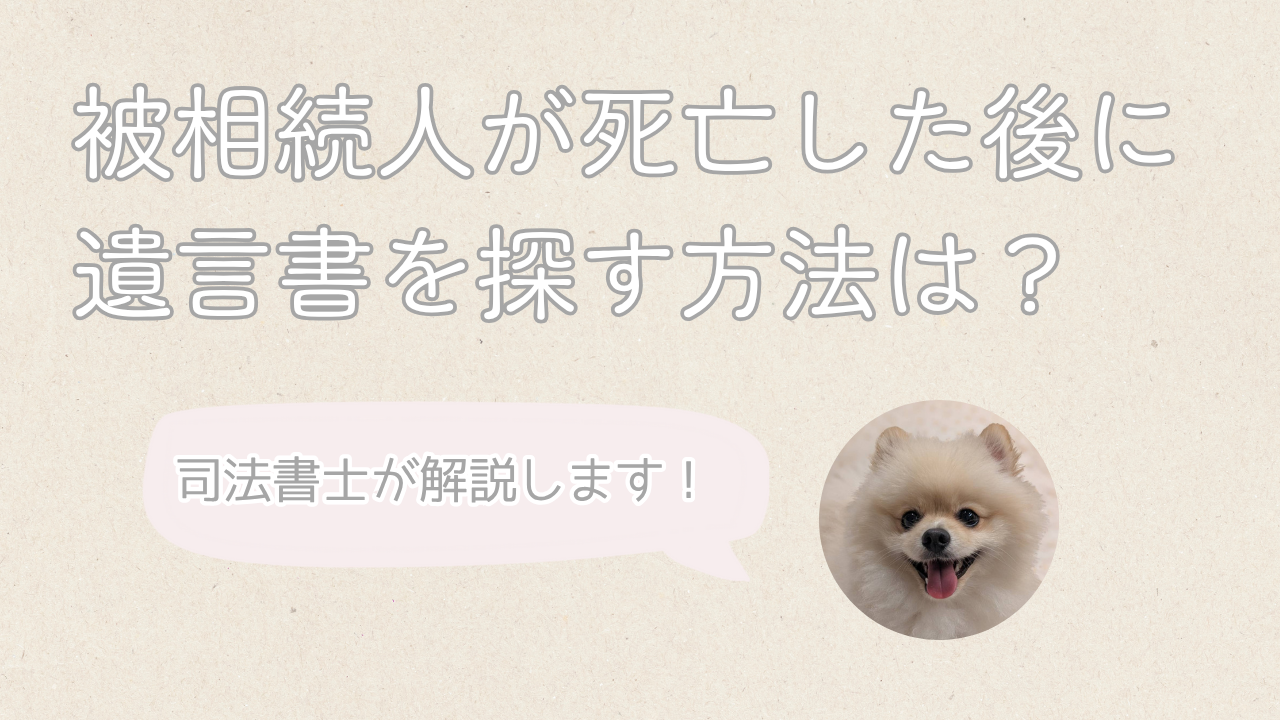
コメント