相続が発生すると、被相続人名義の預貯金口座は「凍結」され、引き出すことができなくなります。
相続人が相続手続をしない限りそのままの状態が続くため、預貯金を分配するには、各金融機関のルールに則って手続を進める必要があります。
預貯金の相続手続はそんなに難しくありません。書類の大部分についても、相続登記で使用したものを流用することが可能です。この記事では、手続の大まかな内容について解説します。
※本記事は、公開時点での法令等に基づいて作成されております。最新情報については、専門家にご相談いただくか、ご自身でご確認ください。
預貯金の相続手続の流れは?
預貯金の相続手続は、基本的に以下のような流れで手続を進めます。
- 金融機関へ連絡する
- 必要書類を揃える
- 金融機関から払戻しを受ける
以下、ポイントについて簡単に説明します。
金融機関へ連絡するタイミングは?
相続が発生した旨を金融機関に伝えると、被相続人名義の口座が凍結され、相続手続の案内が交付されます。
家賃や光熱費の引落口座である等の理由で、相続が開始したことを伝えないままにしているケースもありますが、基本的には、速やかに支払い方法の変更をした上で金融機関に連絡をすべきです。
葬儀費用を引き出してからでもいいですか?と相談を受けることがありますが、常識的な範囲内の金額であり相続人全員の同意ができている場合は、先に葬儀費用分を引き出してからでも問題ないことが多いでしょう。
ただし、口座の名義人が亡くなったら速やかに金融機関に知らせるのが原則です。みだりに預貯金を引き出すことで無用なトラブルを招く原因にもなりかねないためご注意ください。
必要になる書類は?
預貯金の相続手続に必要になる主な書類は以下のとおりです。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書
- 遺産分割協議書(遺言書)
- 通帳
- 相続手続依頼書(金融機関所定のもの)
- 共同相続人同意書(金融機関所定のもの)
※金融機関により異なります。
基本的に、相続登記で使用した書類をそのまま流用することができます。
ただし、戸籍書類や印鑑証明書の有効期限について6カ月程度の期間を設けている場合が多いです。
書類を取得した後は速やかに手続を進めることで再取得の手間を省くことができます。
個別に払戻してくれるの?
金融機関に書類を提出すれば、後は払戻しを受けるだけです。
基本的には、事前に指定した振込先口座に振り込みをしてくれます。
このとき、各相続人の口座に対し取得分ごとに払戻してくれる場合と、代表者の口座に全額を払戻す場合があり、金融機関によって異なります。
預貯金の相続手続に関する質問
預貯金の相続手続に関してよくある質問をいくつか紹介します。
取引支店がわからない場合は?
通帳等の手掛かりがなく、取引支店がわからないときは、自宅周辺の銀行・信用金庫等に照会をかけるしかありません。窓口で必要となる主な書類は以下の通りです。
- 戸籍謄本等の相続を証する書面
- 印鑑証明書
- 本人確認書類
※金融機関により異なります。
近年、通帳を発行しないタイプの口座も増えてきているため、相続人が知らないところに預金されているケースも増えてくるかもしれません。
そのような事態を防ぐために、令和7年4月1日、マイナンバー制度を利用した預貯金口座付番制度が開始されました。
残高証明書は必要?
金融機関に対し、残高証明書の請求が必要となる場合があります。
それは、相続税の申告義務がある場合です。
また、定期預金がある場合は、既経過利息の記載も必要となります。
相続手続は郵送で完結しても、残高証明書の発行は支店窓口で請求しなければならない場合がありますので、ご注意ください。
発行には手数料もかかるので、税の申告が不要な場合には、あえて請求しなくてもよいかもしれません。
遺言書がある場合はどうなる?
遺言書の内容が有効であれば、原則としてその内容に従って手続が進みます。
- 公正証書遺言:検認不要で、すぐに手続可能
- 自筆証書遺言:家庭裁判所での検認が必要
遺言執行者が指定されている場合は、執行者が手続を行います。
遺言書の検認手続については、こちらの記事も参考にしてください。
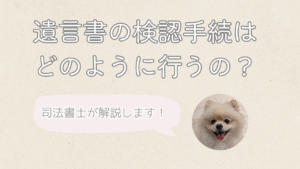
相続人の一部と連絡が取れない場合は?
金融機関は通常、相続人全員の印鑑証明書の提出を求めます。
そのため、連絡が取れない相続人がいると、手続が進まないことがあります。
このような場合には、家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任を申し立てるなどの対応が必要です。
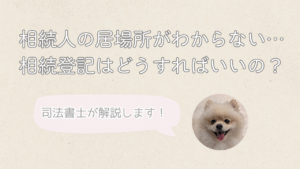
少額であれば簡易な手続ができる?
預貯金の残高によって手続の違いはありませんので、少額だからといって簡易な手続で済ませられるわけではありません。
ただし、一定の条件下では、凍結された口座から相続人が単独で払戻しを受けることが可能です。
- 預貯金の仮払い制度
- 仮分割の仮処分
いずれかの方法によって、相続人が単独で一定の金額を引き出し、当座の生活資金や葬儀費用などの支払いに充てることができます。
仮払い等によって取得した預貯金については、遺産分割で取得されたものとみなされます。
相続登記とは別に考えていいの?
相続登記は法務局に対して行う手続であるのに対し、預貯金の相続は金融機関に対して行う手続です。
それぞれ別の手続で、どちらから先に行っても構いません。司法書士に依頼をすれば、不動産はもちろん預貯金を含む相続財産の調査から遺産分割協議書の作成まで依頼できます。
手続間で書類の流用も可能なため、どちらを先に行う場合であっても、取得した戸籍等の書類は処分せず保管しておくのがおすすめです。
まとめ
この記事では、預貯金の相続手続の大まかな内容について見てきました。
実際は、各金融機関ごとに異なるルールが存在し、個別具体的な対応が求められます。
法務局のように全国一律で同じ手続が運用されている(実務上、管轄ごとの細かい違いはありますが……)わけではなく、各企業ごとの考え方の違いもあって、一概に述べることはできません。
大変に感じるかもしれませんが、一つ一つ対応していけば、預貯金の相続手続は難しくはありません。
煩雑な書類のやり取りが発生するため、どうしても自分たちではできないという場合は、司法書士が代わりに手続を行うこともできますので、お近くの司法書士事務所に相談してみてください。
この記事が参考になれば幸いです。
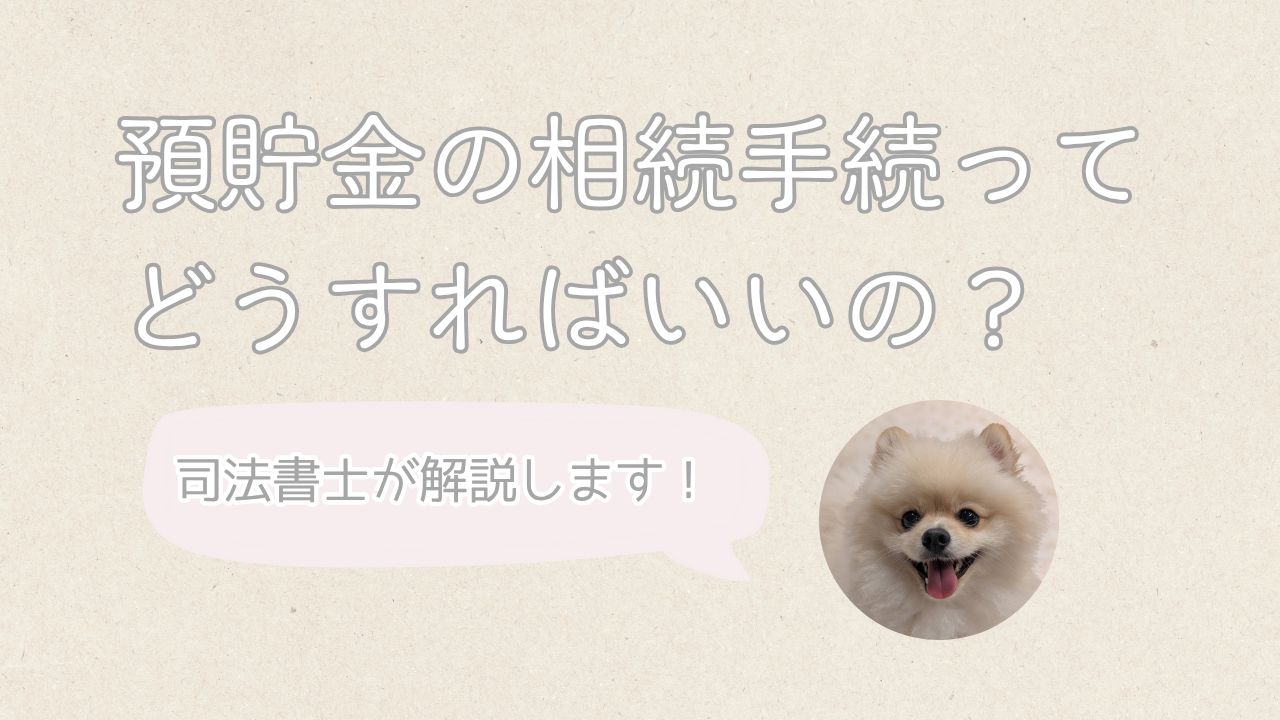
コメント