2020年7月からスタートした「自筆証書遺言書保管制度」は、遺言書を法務局(遺言書保管所)で預かってもらえる制度です。
この制度を利用することで、従来の自筆証書遺言の弱点であった「紛失」「改ざん」「家庭裁判所の検認が必要」といった問題を解消できます。
この記事では、自筆証書遺言書保管制度について解説します。
※本記事は、公開時点での法令等に基づいて作成されております。最新情報については、専門家にご相談いただくか、ご自身でご確認ください。
制度のポイント
自筆証書遺言書保管制度は、全国にある312箇所の法務局(遺言書保管所)で遺言者本人が申請することにより、法務局が自筆証書遺言を保管してくれる制度です。
一度申請した後の変更や撤回も可能で、遺言者の生前には本人が、相続開始後は相続人等の利害関係人が全国にある法務局(遺言書保管所)で閲覧等の手続をすることができます。
まずは制度のポイントを紹介します。
法務局で保管してくれる
従来は遺言書を書いた本人が自分で保管する必要がありました。
そのため、遺言書を紛失したり、遺言書を発見した親族等の利害関係人が勝手に内容を書き換えたりするリスクがありました。
この制度を利用すると、法務局(遺言書保管所)が遺言書を保管することになるため、紛失等の心配がなくなります。
検認が不要になる
通常の自筆証書遺言は、相続開始後に家庭裁判所で「検認」という手続が必要です。
検認は、遺言書が発見された後に改ざん・破棄されたりすることを防ぐために、「この状態の遺言書が確かに存在する」ということを公式に確認する手続です。
ですが、法務局に預けた遺言書については、改ざん等のリスクがないため、検認が不要となります。
通知をしてくれる
遺言者が亡くなった際にあらかじめ指定した者に対して通知をしてくれる仕組みがあります。
遺言者が所定の事項に同意した上で保管申請の際に対象者を指定することで、法務局(遺言書保管所)から遺言書を保管している旨の通知が送付されます。
この仕組みにより、遺言書があることを確実に伝えることができます。
保管申請の方法は?
申請先の遺言書保管所はどこ?
保管の申請ができるのは、以下のいずれかを管轄する遺言書保管所です。
- 遺言者の本籍地
- 遺言者の住所地
- 遺言者が所有する不動産の所在地
手続のためには遺言者本人が遺言書保管所に出向く必要があります(※要事前予約)。
必要な書類は?
保管申請の際に必要な書類は以下の通りです。
- 保管申請書
- 遺言書
- 住民票の写し(本籍の記載があるもの)
- 本人確認書類
遺言書は、日付と氏名を含む全文自書と押印という自筆証書遺言の要件を満たすことに加え、氏名は戸籍上の氏名と同じである必要があります。この点は、民法上の要件(ペンネームでも個人が特定できればOK)と異なりますね。
A4用紙で余白は上側5mm、右側5mm、下側10mm、左側20mm以上確保する必要がある等、一定の様式があります。
申請の前には、法務省のホームページなどをご確認ください。
保管制度を利用するメリット
保管制度を利用するメリットとして、以下の3つをご紹介します。
- 紛失や改ざんを防止できる
- 相続手続がスムーズになる
- 確実に知らせられる
紛失や改ざんを防止できる
法務局で適切に管理されるため、紛失や改ざんを防げます。
遺言書を書いたとしても、その後に認知症の重症化等によって、保管場所や遺言書を書いたことさえ忘れてしまうことも考えられます。遺言者の生前に遺言書の閲覧ができるのは遺言者本人に限られるため、遺言書の内容が気になる親族が勝手に中身を覗き見ることもできません。
そのような心配がなくなるのは、制度を利用する大きなメリットの一つです。
相続手続がスムーズになる
通常は検認手続を経なければ、自筆証書遺言に基づく相続手続をすることはできません。
検認は家庭裁判所の手続で、申立→検認期日→検認済証明書の交付と何日もかかり、申立人は期日に立会が必要となるため、結構大変です。
検認が不要になるため、手続を速やかに進めることができます。
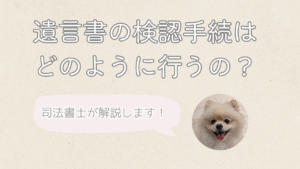
遺言書の存在を確実に知らせられる
2つの通知制度があり、相続人等に確実に知らせられる仕組みになっています。
まず遺言者が亡くなった事実を確認した時点で、あらかじめ指定した対象者に通知書を送付します(指定者通知)。
そして、指定者通知を受けた人や相続人等が閲覧や遺言書情報証明書の交付を受けた場合には他のすべての相続人等に対しても通知が送付されます(関係遺言書保管通知)。
遺言者が亡くなった時に通知する仕組みは、自筆証書遺言書保管制度にしかありません。
書き方について相談できるの?(注意点)
法務局(遺言書保管所)では、遺言の書き方について相談することはできません。
形式的に要件を満たしているかは確認しますが、内容の有効性まではチェックされないため、後に無効となる可能性もあります。
内容が不明確な場合や遺言書本人の意思によるものではない場合等、遺言書の全部または一部が無効となってしまうため、ご注意ください。
この点に関しては、公正証書遺言の場合は公証人が内容について相談に応じてくれる上、証人2名の立会のもと、意思確認を行うため、後に無効となるリスクは低いといえるでしょう。
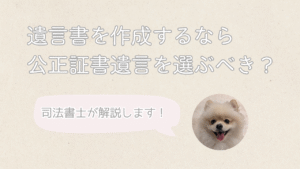
まとめ
この記事では、自筆証書遺言書保管制度の概要について解説しました。
自筆証書遺言書保管制度は、2020年に開始したばかりですが、令和6年時点で約2万3,419件の申請があり、公正証書遺言(12万8,378件)の約18%にも及びます。
遺言書を作成したい需要は高いので、今後ますます利用が増えていくのではないかと思われます。そのうち公正証書遺言の作成件数を超えるかもしれませんね。
この制度を利用することで、従来の自筆証書遺言の弱点であった「紛失」「改ざん」「家庭裁判所の検認が必要」といった問題を解消できます。
将来の相続に備え、この制度を活用して、法務局に遺言書を預けることを検討してみてはいかがでしょうか。
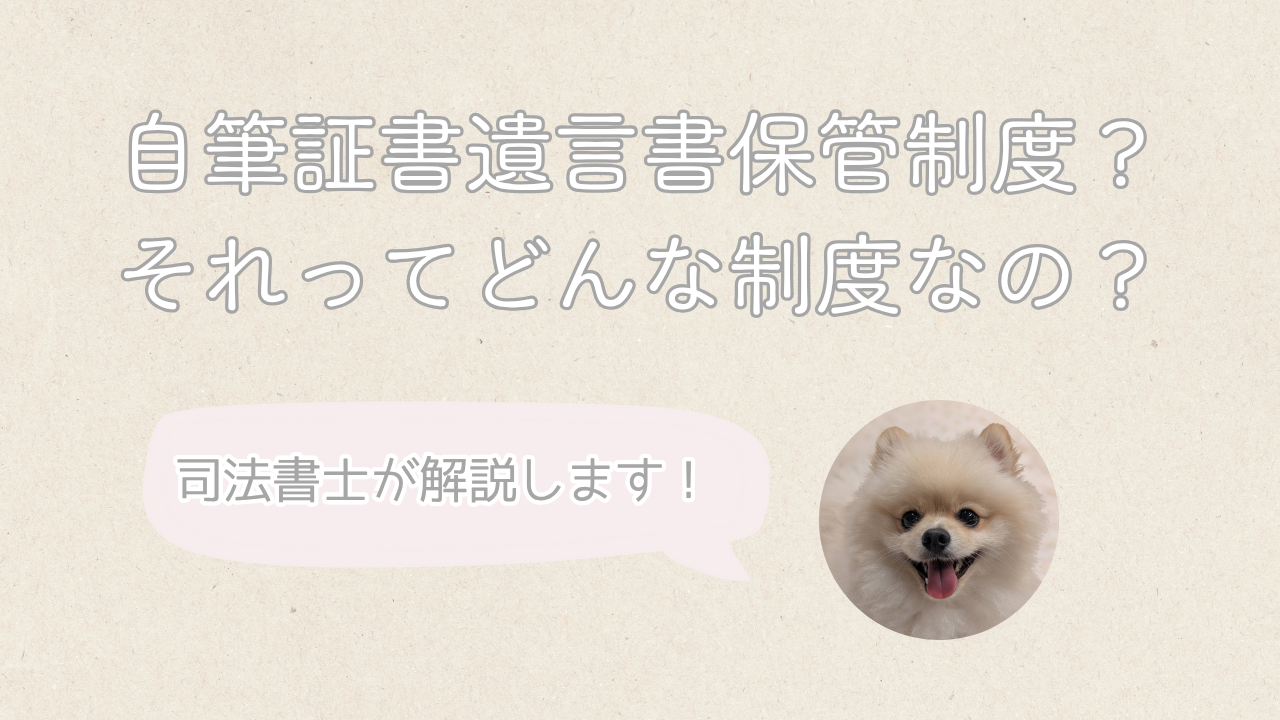
コメント