配偶者が亡くなって、自身も高齢であるために自宅不動産を子に取得させようと考える方は少なくありません。
一方で、所有者である子が勝手に不動産を売却してしまうリスクもあります。
自宅を自分が生きている間は売却したくない、終の棲家にしたいということであれば、「配偶者居住権」を設定して登記をするというのも一つの方法です。
この記事では、配偶者居住権の取得方法や注意点について解説します。
※本記事は、公開時点での法令等に基づいて作成されております。最新情報については、専門家にご相談いただくか、ご自身でご確認ください。
配偶者「短期」居住権とは?
配偶者居住権によく似た権利として、配偶者「短期」居住権というのがあります。
配偶者居住権を理解するうえで比較するとわかりやすいため、まずはこちらから説明します。
配偶者短期居住権は原則成立する
配偶者短期居住権とは、配偶者の短期の住まいを確保するための権利です。
配偶者が相続人の所有していた建物に無償で住んでいた場合、配偶者居住権を取得していなくても、一定期間は自宅に住み続けることができます(民法1037条1項)。
配偶者短期居住権が存続するのは以下のうちいずれか遅い日までです。
- 遺産分割により建物の帰属が確定した日
- 相続開始の時から6カ月を経過する日
- 居住建物の取得者が消滅の申入れをした日から6カ月を経過する日
配偶者を亡くした直後であり、引っ越し先を探すにしてもすぐに見つかるとは限りません。
いずれの場合も最低6カ月間は配偶者短期居住権が存続するため、その間に次の住まいの確保に向けた準備を進めることができます。
配偶者短期居住権が成立しないとき
以下のような場合は、配偶者短期居住権が成立しません。
- 配偶者居住権を取得したとき
- 欠格の規定に該当するとき
- 廃除されたとき
後述しますが、配偶者居住権は配偶者が終身の間存続するので、配偶者短期居住権は不要となります。
欠格者や被廃除者は殺人や虐待をしており、配偶者短期居住権を認めるのは妥当ではありませんね。
欠格・廃除についてはこちらの記事をご覧ください。
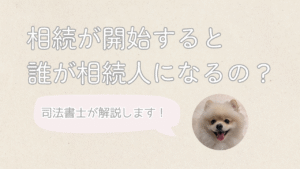
配偶者居住権の取得方法は?
(配偶者居住権)
第千二十八条 被相続人の配偶者(以下この章において単に「配偶者」という。)は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その居住していた建物(以下この節において「居住建物」という。)の全部について無償で使用及び収益をする権利(以下この章において「配偶者居住権」という。)を取得する。ただし、被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合にあっては、この限りでない。
一 遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされたとき。
二 配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき。
(引用元:民法|e-Gov法令検索)
配偶者居住権は、被相続人と同居していた居住建物の全部について無償で使用及び収益をする権利のことです。
配偶者短期居住権と異なり、原則として、配偶者が亡くなるまでの間存続します(民法1030条)。
配偶者居住権には、次の2つの取得方法があります。
遺産分割または遺言による取得
被相続人が亡くなるとき、被相続人名義の居住建物に住んでいた配偶者が次のいずれかに該当すると取得できます。
- 遺産分割で取得するものとされたとき
- 遺贈の目的とされたとき
被相続人の明確な意思または相続人の合意がある場合ですね。
なお、遺言ではなく、死因贈与によって取得させることも可能です。
家庭裁判所の審判による取得
また、家庭裁判所が配偶者居住権の取得を定めることもできます(民法1029条)。
遺産分割の請求を受けた以下の場合です。
- 相続人全員が合意している
- 居住建物の所有者の不利益の程度を考慮してもなお配偶者の生活維持のため特に必要があると認められる
配偶者居住権の取得について相続人が合意していれば問題ありません。
相続人の合意ができなかったとしても、配偶者の申出があり、所有者の不利益と配偶者の利益を天秤にかけて、特に配偶者を保護する必要がある場合に、家庭裁判所は配偶者居住権の取得を定めることができます。
配偶者居住権を取得できないとき
被相続人が亡くなるとき、被相続人名義の居住建物に配偶者が住んでいた場合に取得できます。
ですが、被相続人が居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合は、配偶者居住権は取得できません。
たとえば、被相続人と子が共有していた場合です。
配偶者居住権は無償で住むだけでなく、他人に貸したりすることもできる強力な権利です。共有者に対し強制的に不利益を受けさせることになってしまうため、成立しないことになっています。
配偶者居住権は登記しないとどうなる?
配偶者居住権を第三者に対抗するためには登記が必要です(民法1031条2項)。
配偶者が対象の建物に住んでいるだけでは、第三者に対し配偶者居住権を主張することができません。
例えば、所有者である子が居住建物を売却したとき、買主に対して配偶者居住権があることを主張することができなくなってしまうのです。
平たく言えば、追い出されてしまうことになっても買主には文句が言えないということです。
配偶者を保護するため、居住建物の所有者には、配偶者居住権の設定の登記をする義務があります(民法1031条1項)。
一方、配偶者「短期」居住権はいずれ消滅する権利であるため、登記することはできません。
配偶者居住権Q&A
まとめ
配偶者居住権は、被相続人が亡くなった後の配偶者の住まいを確保するために法律で認められた権利です。
遺産分割や遺贈で自宅不動産を取得しない場合であっても、配偶者は被相続人が亡くなってから自分が亡くなるまでの間(配偶者短期居住権の場合は6カ月以上の間)は、自宅に引き続き住み続けることができます。
また、配偶者居住権をうまく利用することで配偶者の取得する財産の評価額を下げることができたり、相続人間で遺産を公平に分配ができる場合があります。
ただし、税務上の問題が生じたりするおそれがありますので、司法書士に相談される際は、税理士の先生と連携して税務上の問題についても対処してくれるか尋ねてみるとよいでしょう。
この記事が参考になれば幸いです。
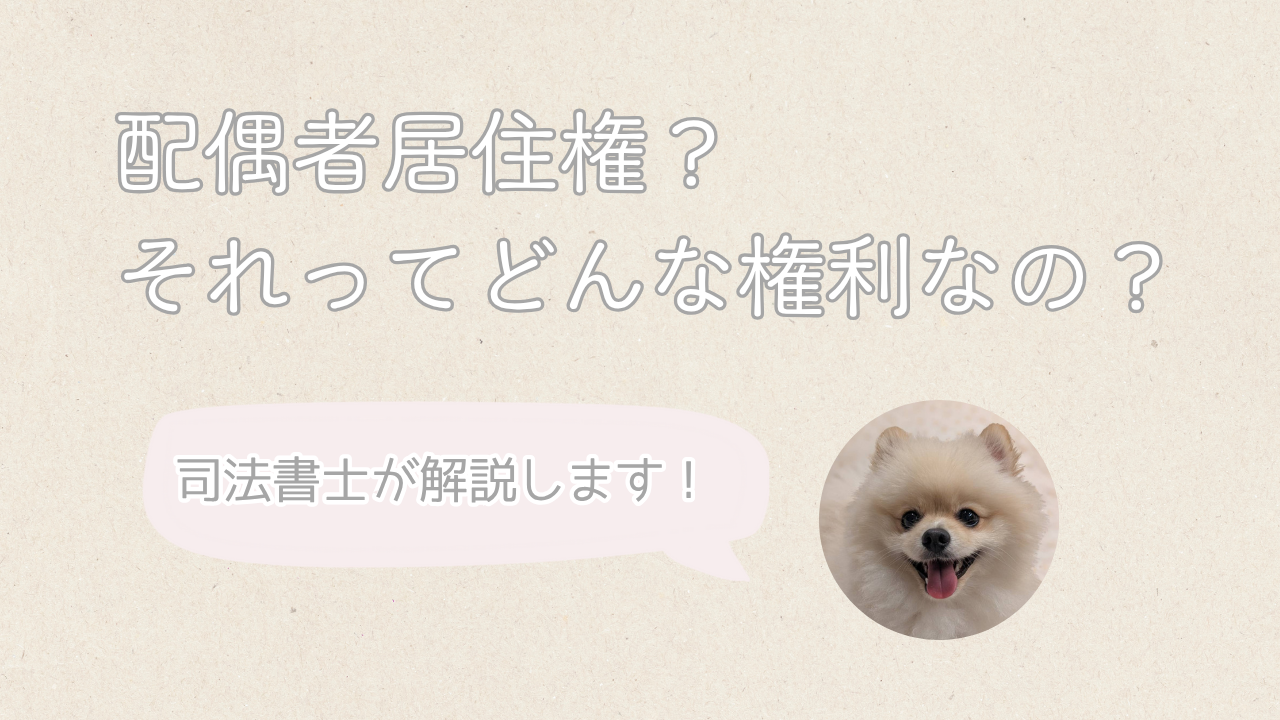
コメント