相続登記の必要書類として、被相続人の住民票の除票があります。
これは、登記記録上の被相続人と戸籍上の被相続人との同一性を証するために必要となる書類です。
しかし、住民票の除票が保存期間経過により廃棄され、取得できない場合があります。そのような場合に、どのように対応すればよいのでしょうか。
この記事では、住民票の除票が取得できない場合の対応方法について解説します。
※本記事は、公開時点での法令等に基づいて作成されております。最新情報については、専門家にご相談いただくか、ご自身でご確認ください。
住民票が取得できない?
住民票の保存期間は5年だった
住民票は、転出等によって消除された日から5年が保存期間として定められていました。
令和元年6月20日以降に消除されたものについては、保存期間が150年に変更されていますが、すでに保存期間が経過してしまっているものについては、取得することができません。
保存期間経過による廃棄の運用は自治体によって異なるようですので、請求する前に市町村役場に問い合わせてみるのが確実です。
戸籍の附票が取得できる場合がある
住民票の除票が取得できない場合は、戸籍の附票を取得できないか検討します。
戸籍の附票には、その戸籍が編製されてから除籍されるまでの間の住所の履歴が記載されます。
戸籍の附票は、住民票と同様に保存期間が5年ですが、その起算日となるのは全部消除されてからなので、配偶者や子など戸籍に残っている人がいる限り、取得することができます。
また、被相続人が登記簿上の住所から2回以上住所を変更している場合は、初めから戸籍の附票を取得した方が早いかもしれません。
住民票には原則として現在の住所と一つ前の住所しか記載されないため、住所のつながりを示すことができず、別途戸籍の附票を取得する必要が出てくる場合があるからです。
住民票(戸籍の附票)が取得できないときは?
権利証があればOK
住民票も戸籍の附票も取得できないときは、被相続人が不動産を取得したときの権利証を提出します。
権利証は、登記の際に名義人に対して一度しか発行されず、再発行もできない代物です。
よって、権利証を持っているということは、登記名義人(=被相続人)に違いないということがいえるため、被相続人の同一性を証することができます。
相続登記では基本的に権利証がなくても手続可能ですが、このような場合に権利証があると役に立ちます。
一部について権利証がないときは?
たとえば、被相続人名義の土地が3筆あり、うち2筆については権利証があるけど、残り1筆について権利証が見つからないような場合です。
このように一部について権利証がない場合、権利証だけでは不十分となってしまうため、後述する上申書を作成する必要があります。
権利証がないときは?
権利証がないときは、上申書を作成します。
上申書には、下記の事項を記載します。
- 書類を取得できず同一性を証することができないこと
- 登記簿上の被相続人と相違ないこと
- 登記の目的及び原因
- 不動産の表示
上申書には、相続人全員の実印による押印と印鑑証明書の添付が必要です。
この印鑑証明書は、第三者の承諾書等に添付する印鑑証明書とは異なり、原本還付が可能です。
よって、遺産分割協議書に添付する印鑑証明書が1通あれば、すべて原本還付用の写しを添付することができるため、別途取得する必要はありません。
なお、上申書は一つの書面に全員が記入・押印しても、各相続人ごとに一枚ずつ作成したものをまとめて提出しても構いません。
まとめ
相続登記には、被相続人の住民票の除票または戸籍の附票の取得が必要となります。
住民票の除票や戸籍の附票の除票には保存期間があり、改正により伸長されましたが、すでに廃棄されてしまったものについては、取得できません。
そのような場合は、権利証や上申書を用意することで登記を申請することができます。
この記事が参考になれば幸いです。
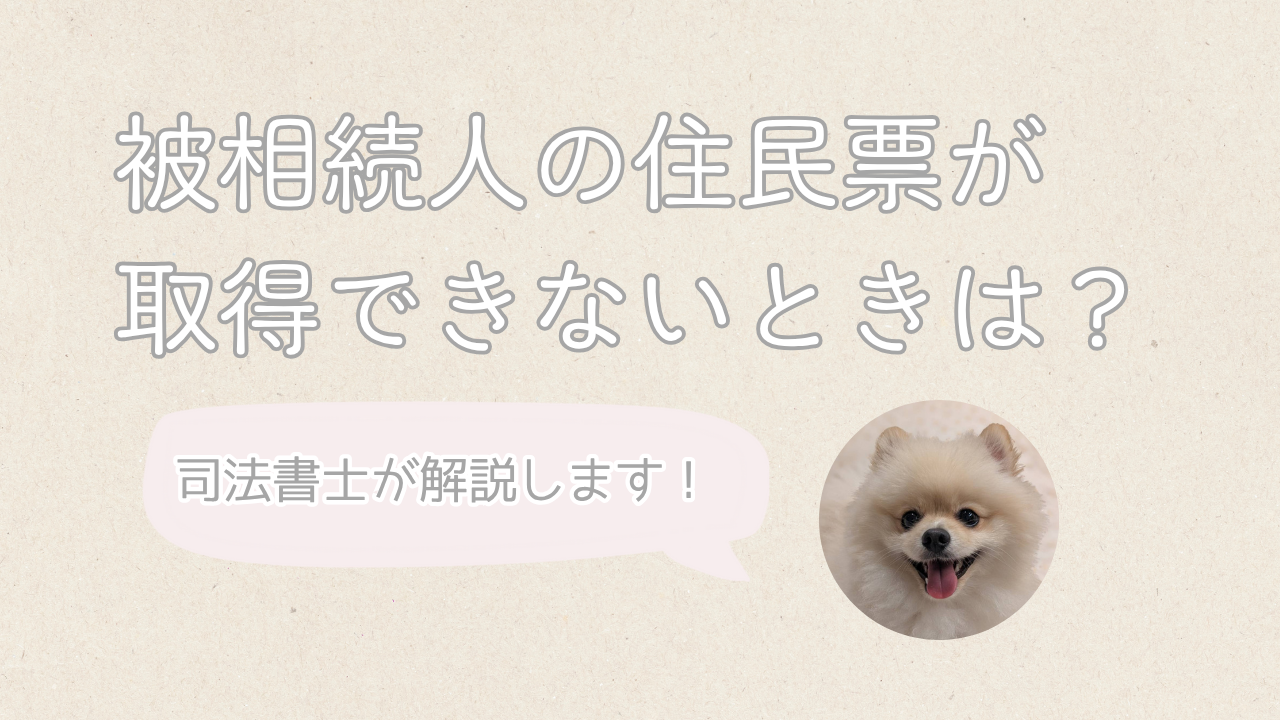
コメント