令和6年4月より不動産登記法が改正され、相続登記が義務化されました。
巷では、「3年以内に相続登記をしないと10万円の罰金」だといわれています。
しかし、3年以内に相続登記をしていないと必ず過料に処されるというわけではありません。
相続の相談をしていると、「義務化」という言葉が一人歩きをして、誤解をしている方が少なくないように感じます。
そこで、この記事では、相続登記義務化に関する、令和5年9月12日法務省民二第927号通達を参考にしながら、現在わかっていることについて解説します。
※本記事は、公開時点での法令等に基づいて作成されております。最新情報については、専門家にご相談いただくか、ご自身でご確認ください。
相続登記の義務とは?
義務の対象となるのは?
(相続等による所有権の移転の登記の申請)
第七十六条の二 所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により所有権を取得した者も、同様とする。
2 前項前段の規定による登記(民法第九百条及び第九百一条の規定により算定した相続分に応じてされたものに限る。次条第四項において同じ。)がされた後に遺産の分割があったときは、当該遺産の分割によって当該相続分を超えて所有権を取得した者は、当該遺産の分割の日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。
3 前二項の規定は、代位者その他の者の申請又は嘱託により、当該各項の規定による登記がされた場合には、適用しない。
(引用元:不動産登記法|e-Gov法令検索)
以下の者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。
- 相続により所有権を取得した者
- 遺贈により所有権を取得した者
「自己のために相続の開始があった」とは、被相続人が死亡したことを知り、かつ、自分が相続人であることを知った時点だとされています。
また、法定相続分による相続登記がされた後であっても、遺産分割により自己の相続分を超えて所有権を取得した場合は、遺産分割の日から3年以内に所有権の移転の登記を申請しなければなりません。
義務を怠るとどうなる?
(過料)
第百六十四条 (省略)第七十六条の二第一項若しくは第二項又は第七十六条の三第四項の規定による申請をすべき義務がある者が正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、十万円以下の過料に処する。
(引用元:不動産登記法|e-Gov法令検索)
義務を怠ると、10万円以下の過料の適用対象となります。
ただし、後述するように、過料に処されるまでには段階があって、いきなり支払い命令のようなものがくるわけではありません。
改正法施行前の相続にも適用される?
相続登記の義務化以前(~令和6年3月31日)に開始した相続によって所有権を取得した場合も義務化の対象となります。
ただし、すでに相続によって所有権を取得している場合であっても、令和9年3月31日までの猶予期間内に相続登記を申請すれば、過料に処される心配はありません。
過料に処されるまでの段階
3年経過した時点でいきなり過料の支払いを命じられるわけではなく、過料に処されるまでは以下のような段階があります。
- 申請の催告
- 正当な理由の確認
- 裁判所への通知
順番にみていきます。
まずは申請の催告がある
(裁判所への通知)
第百八十七条 登記官は、次の各号に掲げる場合には、遅滞なく、管轄地方裁判所にその事件を通知しなければならない。
一 法第百六十四条の規定により過料に処せられるべき者があることを職務上知ったとき(登記官が法第七十六条の二第一項若しくは第二項又は第七十六条の三第四項の規定による申請をすべき義務に違反した者に対し相当の期間を定めてその申請をすべき旨を催告したにもかかわらず、その期間内にその申請がされないときに限る。)。
二 (省略)
(引用元:不動産登記法|e-Gov法令検索)
登記官は、過料事件を裁判所に通知する前に、申請をすべき旨を催告しなければならないとされています。
つまり、いきなり裁判所から手紙がくることはなくて、まずは登記所(法務局)から催告書が届くということです。
そして、催告書に申請できない事情を記載し、その理由が正当であると認められれば過料には処されないということになっています。
正当な理由があると認められる場合
では、正当な理由とは、どのような事情がある場合に認められるのでしょうか。
以下のような場合は、一般的に正当な理由があるとされています。
- 相続人が極めて多数に上り、相続関係の把握等に時間を要する場合
- 相続人間の争いにより、不動産の帰属主体が明らかでない場合
- 申請義務を負う者が重病等である場合
- 申請義務を負う者がDV支援法の対象者等であり避難を余儀なくされている場合
- 申請義務を負う者が登記の申請にかかる費用を負担する能力がない場合
※これらの場合に限定されるわけではありません。
また、正当な理由があることを裏付ける資料の提出も必要です。
期限を経過すると裁判所への通知がされる
催告書には期限が記載されます。
催告書を受けた場合は、期限内に申請をするか、正当な理由がある場合は事情を具体的に記載した催告書を登記所に持参または返送する必要があります。
そして、期限を経過しても申請がない、かつ、正当な理由があると認められる申告が期限内になされないときは、登記官から裁判所への通知がされます。
裁判所の過料決定に対しては、一定の場合には異議申立を行うこともできますが、登記官(法務局)から届く催告書には期限内に対応するようにしましょう。
まとめ
以上、相続登記義務化の内容について簡単に説明してきました。
「3年以内に相続登記をしないと10万円」これだけと聞くと不安ですよね。
どうしても事情があって手続ができない方もいるため、正当な理由があると認められる場合は過料の適用対象とはされていません。
ただし、過料に処されないからといって相続登記申請義務がなくなるわけではありませんし、被相続人の名義のままの状態で放っておくことが、どのようなリスクにつながるのかをよく検討しなければなりません。
この記事が参考になれば幸いです。
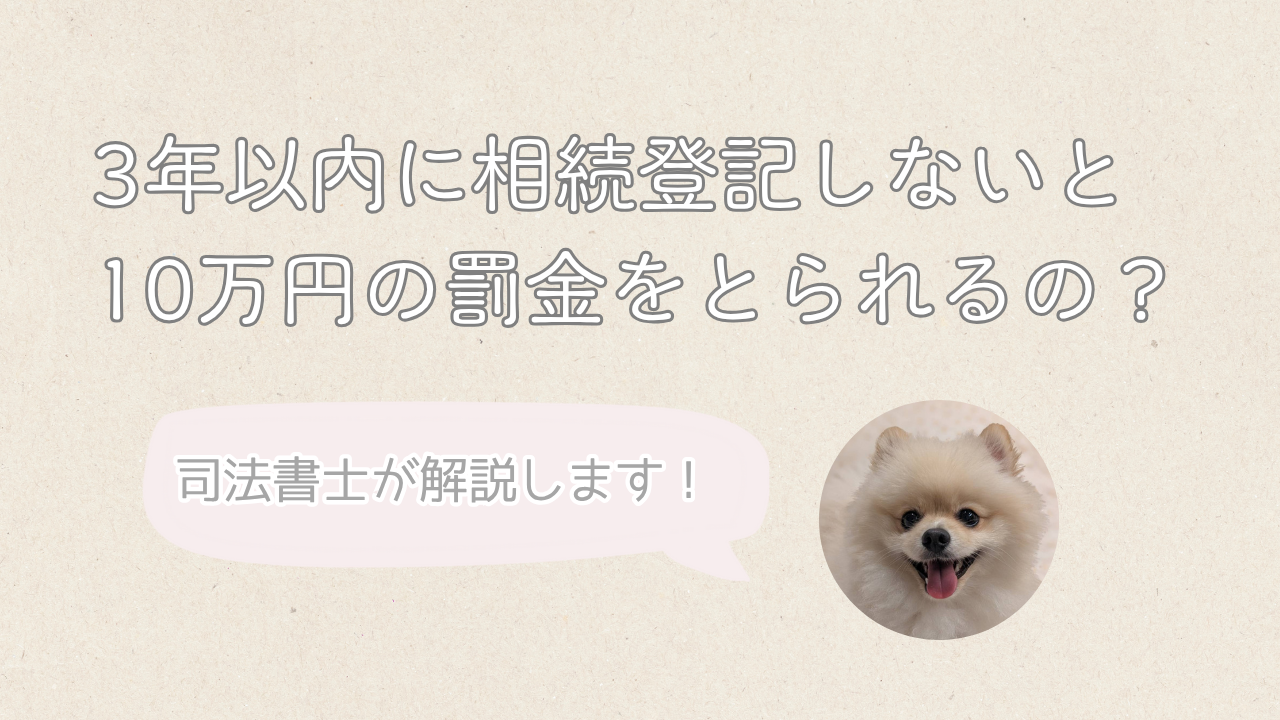
コメント