先日、所属している司法書士会より、会員に対する連絡がきました。
その内容は、相続登記の件数は令和6年度において前年度比で増加したものの、過去(令和2〜5年度)と比べると「増加率」が減少しているので、原因を考えてくださいというものでした。
相続登記の件数自体は増えているものの、相続登記が義務化された令和6年度においては、その伸び率が鈍化しているようです。
そこで、自分なりに原因を考えて整理してみました。
義務化施行前の駆け込み申請
令和6年4月1日からの相続登記の義務化により、令和5年度に申請が集中したため、令和6年度は一時的な反動で伸び率が低下した可能性があります。
罰則が適用されるのは早くても令和9年4月1日以降なので、関心が高い人たちの登記がすでに終わったとすれば、猶予期間の今、新たに動く人が減少したのかもしれません。
そのため、令和9年4月1日に近づくにつれて、罰則適用前の駆け込み申請が増加する可能性もあります。
相続発生件数の増加鈍化
高齢者人口の増加は続いているものの、死亡者数の増加ペースが鈍化しているのではと思い、調べてみました。
| 年 | 死亡者数 | 増減数(前年比) |
| 令和2年 | 1,372,755人 | -8,455人 |
| 令和3年 | 1,439,856人 | +67,101人 |
| 令和4年 | 1,569,050人 | +129,194人 |
| 令和5年 | 1,576,016人 | +6,966人 |
| 令和6年 | 1,605,298人 | +29,282人 |
確かに令和2年~令和5年の平均増加数(48,701人)と比較すると、令和6年の増加数はやや減少していることがわかります。
こうしたことも原因の一つかもしれませんね。
登記コストに対するハードル
義務化で登記しなければならないと理解していても、登録免許税・司法書士報酬・書類準備のコストにより先延ばしされている方は多いのではないでしょうか。
最近になって法務局の窓口が混雑している点や、審査に時間がかかり完了が遅れている点などからも、本人申請が増加しているのは確かだと思われます。
なぜ本人申請をするのかといえば、ほとんどの場合、司法書士費用が大きな負担になっているからです。
特に、経済的価値の低い土地などについては登記しても仕方がないと考え、登記を控える傾向があります。これまでは税金さえきちんと支払っておけば、役所も特に問題なく扱ってきました。
コストを支払ってまで登記をするのは割に合わないと感じるのは、無理からぬ話だと思います。
手続に時間を要している
義務化で登記を意識し始めたが、準備が整わず、件数としては将来に繰り越されているということも考えられます。
書類を集めたり、相続人間で連絡をとるのも大変ですからね。
手を着けてはみたものの、煩雑な手続・膨大な書類に疲れ果て、頓挫して、そのまま寝かせてしまっているというケースも少なくないのではないかと思われます。
困難な案件では1年以上かかることもざらにあるので、早めに着手することと、適切に専門家の力を借りることが重要です。
まとめ
先日、兵庫県尼崎市で空き家の所有者等調査と相続登記を司法書士会に委託する取組がニュースになっていました。
空き家の所有者調査、相続登記まで委託 兵庫県内初、尼崎市と県司法書士会が連携協定
(※会員限定記事です。)
兵庫県では、三木市が「空き家等適正管理事業に関する協定」として、兵庫県司法書士会との間で所有者等調査業務などを委託する提携をしていましたが、相続登記までは含まれていませんでした。
さらに、尼崎市の広報資料によると、「司法書士へ支払うこととなる報酬の一部を市が支援」するとあります。(尼崎市公式ホームページより)
こうした取組が、今後全国でも広がっていくかもしれません。
令和6年4月に相続登記が義務化されて一年以上が経ちました。
制度の背景にある、所有者不明土地・建物問題は深刻で、相続登記の普及促進は喫緊の課題です。
個人的な感覚としては、昨年より相続登記に関する相談は増えていると感じますし、義務化の件でいえば、令和9年4月1日以降は実際に罰則が適用されて過料に処せられる事例が全国でみられるようになってくるものと思われます。
今回のように、市などが費用を補助する仕組みが普及すれば、経済的理由で相続登記を進められずにいる方の助けになるかもしれません。
私も一人の専門家として、できることに取り組んでいく所存です。
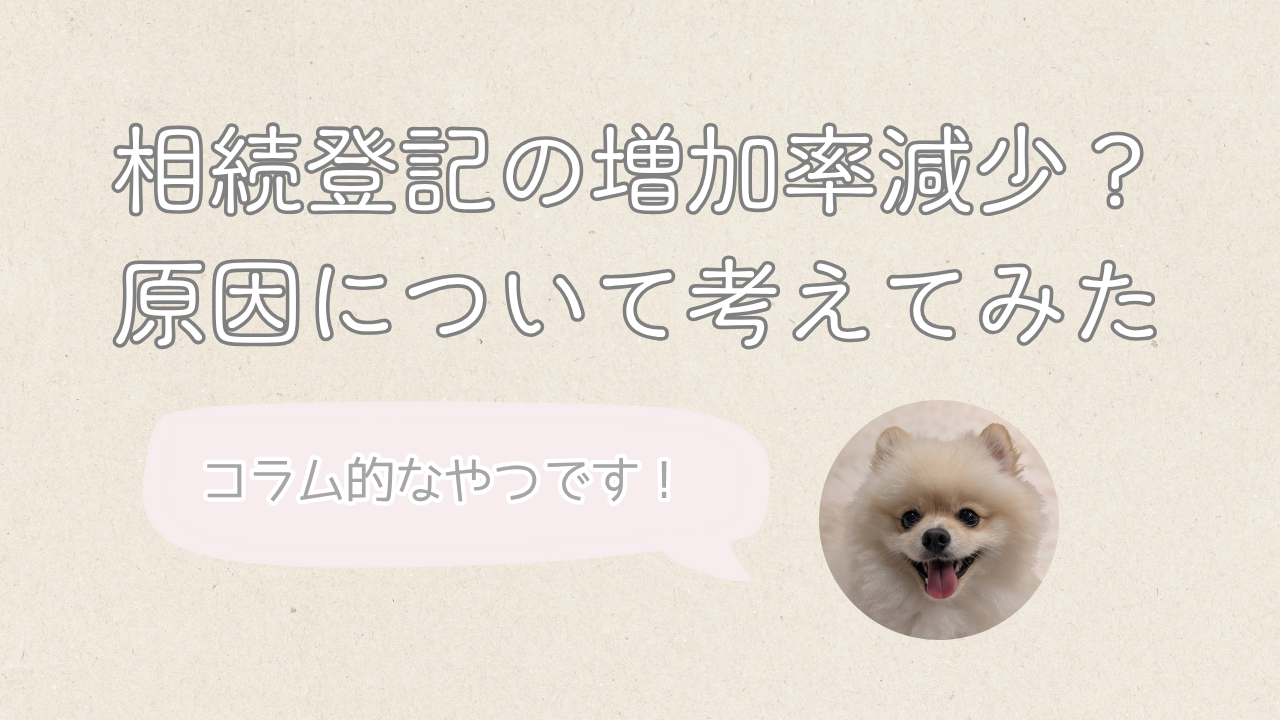
コメント