できたら相続登記を自分で済ませたいと思われている方は多いのではないでしょうか。
確かに、相続登記は自分ですることも可能ですが、注意すべき点もあるので、慎重に判断することをおすすめします。
この記事では、相続登記を自分でする場合の主な流れと注意点について解説します。
※本記事は、公開時点での法令等に基づいて作成されております。最新情報については、専門家にご相談いただくか、ご自身でご確認ください。
自分で手続きすることは「法律上可能」
相続登記は、法律上、本人自ら行うこと(いわゆる「本人申請」)が可能です。
実際、法務局のホームページでは手続きの流れや必要書類についての案内も公開されており、各地の法務局では相続登記に関する相談を受け付けています。
このような行政サービスを利用して、自分で相続登記をする方もいらっしゃいます。
ですが、相続登記を自分でやることについては、基本的にはあまりおすすめしていません。十分な調査や確認を怠った結果、後になって問題が発覚する場合も少なくないからです。
どんなときに「自分でできる」のか?
以下のようなケースでは、比較的スムーズに本人申請できることも多いです。
- 相続人が配偶者と子どもだけなど、相続関係がシンプルかつ明確なケース
- 不動産の数が少ないケース
- 戸籍の収集や遺産分割協議書の作成が済んでいるケース
- 時間に余裕があり、調査・書類作成を自分で進められるケース
自分でやる場合の主な流れ
自分でやる場合の流れは以下のようになります。
- 戸籍や住民票等を収集する
- 遺産分割協議書を作成する(必要に応じて)
- 登記申請書を作成する
- 登録免許税を納付する(5と同時に行う)
- 登記申請書と添付書類を管轄法務局へ提出する
広域交付によって戸籍はずいぶん集めやすくなりましたが、膨大な数が必要になることもありますし、過不足なく揃っているかを確認する作業も欠かせません。
戸籍はただ集めればよいのではなく、そこから相続関係を読み解かなくてはなりません。婚外子や養子などの相続人がいたことが新たに判明する場合もあります。税金の計算にもいくつもの落とし穴があるため注意が必要です。
なんとか申請までこぎ着けたとしても、書類の不備があれば補正を求められ、何度も法務局へ足を運ぶことになります。
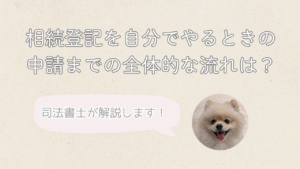
注意が必要なケースとは?
以下のようなケースは、本人申請が一気に難しくなります。
- 相続人の数が多い
- 疎遠な相続人がいる
- 遺言書がある
- 被相続人が複数の不動産を所有していた
- 数次相続や代襲相続が含まれる
こうした場合は、法律関係や登記実務に関する専門的な判断が必要となるため、安易に自分で手続を進めようとせず、司法書士や弁護士へ相談することをおすすめします。
まとめ
相続登記は、自分で手続きすることも可能ですが、
- 時間と手間がかかること
- 専門的な知識が必要となる場合も多いこと
- 後から問題が発覚する場合もあること
これらをふまえ、「どこまで自分でやるのか」「どこから専門家に依頼するか」を見極めることが大切です。
相続登記のミスは後になって大きな問題となり発覚する場合も珍しくありません。
費用などの兼ね合いもあると思いますが、可能であれば司法書士に依頼することをおすすめします。
この記事が参考になれば幸いです。
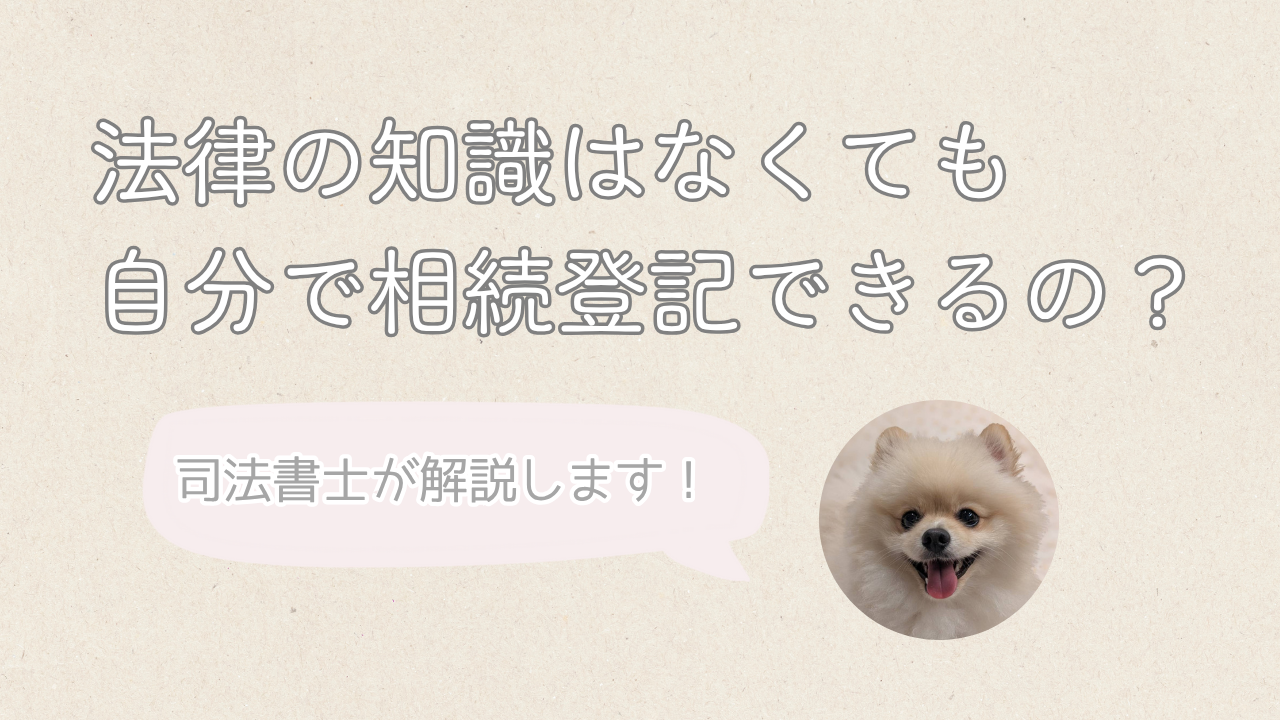
コメント