夫または妻が亡くなり、相続人が残された配偶者と子である場合に、相続登記をするにはどのような書類が必要なのでしょうか。
この記事では、相続登記を申請するうえで必要な書類や手続の流れ、注意点について解説します。
※本記事は、公開時点での法令等に基づいて作成されております。最新情報については、専門家にご相談いただくか、ご自身でご確認ください。
子どもが相続人となるのはどんな場合?
子は第一順位の相続人です。
よって、被相続人に子どもがいれば、当然に相続人となります。
相続人の決まり方に関する民法のルールについては、こちらの記事もご確認ください。
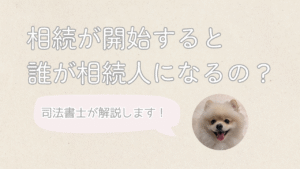
必要書類
相続登記で必要な添付書類は以下のようになります。
なお、共通する書類は1通あれば大丈夫です。
(例えば、夫婦と子が同じ戸籍に載っていれば、それぞれ1通ずつ取得する必要はなく、あわせて1通でOK。)
不動産に関する書類
- 固定資産税納税納税通知書(課税明細書)
-
毎年5~6月に納税義務者の住所に送付されます。
- 固定資産評価証明書
-
不動産所在地の市区町村役場で取得します。
- 不動産登記簿謄本(登記事項証明書)
-
不動産所在地の法務局で取得します。
登録免許税の計算には、不動産の評価額が必要です。
固定資産税納税通知書の後ろには課税明細書がついていて、そこに評価額が記載されています。
課税明細書ですべての不動産の評価額がわかる場合、評価証明書の取得は不要です。
また、登記簿謄本で、権利状況を確認します。
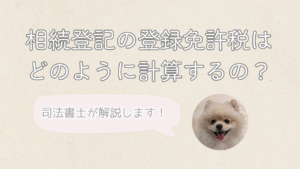
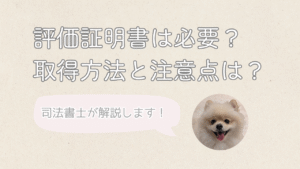
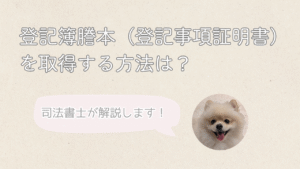
人に関する書類
被相続人の書類
- 出生から死亡までの戸籍謄本等
-
本籍地の市区町村役場で取得します。
- 住民票の除票または戸籍の附票
-
住所地の市区町村役場で取得します。本籍の記載が必要。
住民票の除票または戸籍の附票が保存期間経過により廃棄されている場合は、被相続人の登記済権利証や登記識別情報通知が必要となります。
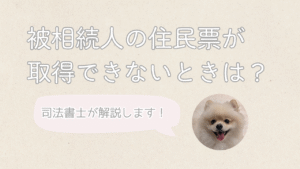
相続人・配偶者の書類
- 戸籍謄本または戸籍抄本
-
本籍地の市区町村役場で取得します。
- 住民票 ※不動産を取得する場合
-
住所地の市区町村役場で取得します。
- 印鑑証明書 ※遺産分割協議をする場合
-
住所地の市区町村役場で取得します。
相続人・子の書類
- 戸籍謄本または戸籍抄本
-
本籍地の市区町村役場で取得します。
- 住民票 ※不動産を取得する場合
-
住所地の市区町村役場で取得します。
- 印鑑証明書 ※遺産分割協議をする場合
-
住所地の市区町村役場で取得します。
コンビニ交付による取得が可能な書類
戸籍謄本、住民票、印鑑証明書は、コンビニ交付による取得が可能です。
※マイナンバーカード(利用者証明用電子証明書が記録されたもの)が必要。
住民票の除票は対象外ですが、戸籍の附票であれば、請求者と被相続人が同じ戸籍に入っている場合は取得できます。
ただし、市区町村により、取得できる証明書の種類が異なるためご注意ください。
広域交付による取得が可能な書類
戸籍書類は、基本的に広域交付による取得が可能です。
※コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍、戸籍の附票は対象外。
本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母など)、直系卑属(子、孫など)に限り、全国の市区町村の窓口で対象となる戸籍謄本等が取得できます。
広域交付を利用することで、本籍地ごとに請求しなくても、最寄りの役場で手続が完結します。
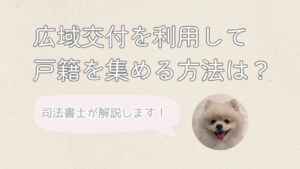
書類の有効期限はある?
相続登記で必要となる書類で、基本的に有効期限は問題となりません。
ただし、集めた書類を預貯金口座の解約手続等に流用する場合は、金融機関ごとに期限のルールを定めている場合も多く、必要に応じて再取得をすることになります。
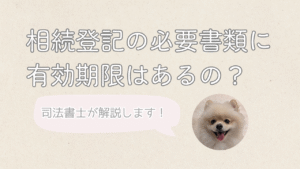
手続の流れ
戸籍書類を収集し、相続人を特定します。
被相続人の名義の権利証、固定資産税納税通知書、名寄帳等から不動産を特定する作業を行います。
戸籍書類の他、登記申請に必要な書類を集めます。
遺産分割協議で不動産の取得者を決定します。
必要に応じて、成年後見人選任の申立等を行います。
不備なく登記申請書を作成します。
不動産の所在地を管轄する登記所(法務局)に申請書・添付書類を提出します。
適宜、補正対応等を行います。
原本還付書類、登記識別情報通知、登記完了証を受け取ります。
登記所に申請書類を提出してから完了までの期間は管轄ごとに異なります。
まとめ
この記事では、夫または妻が亡くなり、相続人が残された配偶者と子である場合の必要書類や手続の流れについて解説しました。
このように相続関係がシンプルだと、最寄りの市区町村役場でほとんどの書類を揃えることが可能です。
多くの事務所では、戸籍等の書類を依頼者自身で集めることで、登記費用を抑えることができます。
司法書士に依頼をする際に、書類を自分で集めることで費用の節約ができないかを提案してみてもよいかもしれませんね。
この記事が参考になれば幸いです。
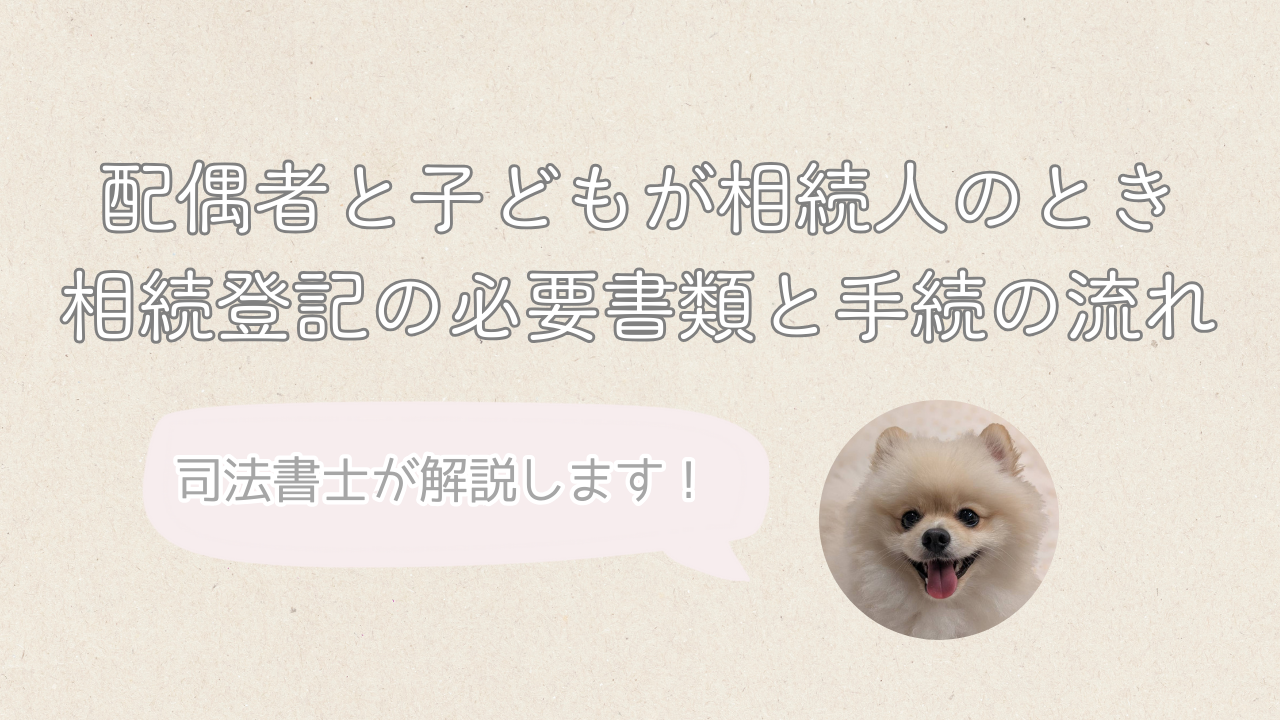
コメント