遺産分割協議の成立には相続人全員の参加が必要であり、相続人が行方不明の場合であっても例外ではありません。
相続人の居場所がわからない場合、遺産分割協議を成立させるには、不在者財産管理人の選任を申し立てるか、失踪宣告の申立を行う方法があります。
不在者財産管理人制度については、こちらの記事で説明しました。
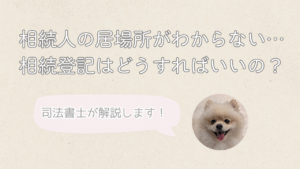
この記事では、不在者が行方不明になって一定期間が経過すると利用できる失踪宣告の制度について解説します。
※本記事は、公開時点での法令等に基づいて作成されております。最新情報については、専門家にご相談いただくか、ご自身でご確認ください。
失踪宣告とは?
失踪宣告は、生死不明の者を法律上死亡したものとみなす制度です。
不在者の生死が7年間明らかでないとき、または、戦争や震災など死亡の原因となる危難に遭遇し、その危難が去ってから生死が1年間明らかでないときに、利害関係人の申立により、家庭裁判所が失踪宣告をします。
失踪宣告は、不在者の従来の住所地または居所地を管轄する家庭裁判所に申立を行います。
申立人
申立を行うことができるのは、利害関係人です。
利害関係人とは、不在者の配偶者、推定相続人、財産管理人などです。
必要書類
- 申立書
- 不在者の戸籍謄本と戸籍の附票
- 失踪の事実を証する資料
- 申立人の利害関係を証する資料
以上の書類が必要となります。推定相続人が申立人となる場合の利害関係を証する資料は、不在者と申立人の相続関係を証する戸籍です。
失踪の事実を証する資料としては、
- 行方不明者届受理証明書
- 住民票(除票)
- 住所宛に送付したが返送された郵便物
- 現地調査報告書
などがあります。
上記の書類がすべて用意できないからといって申立ができないわけではなく、近親者の陳述書など、不在者が行方不明になったことを疎明する資料を複数用意すれば大丈夫です。
また、申立時点で完璧に用意できていなくても、要件を満たしていれば直ちに却下されることはありません。審理の上で必要に応じて、追加提出を求められる場合があります。
費用
- 収入印紙800円分
- 予納郵券(切手のこと)
- 官報公告料4,816円
切手代は裁判所によって異なります。
官報公告料は、後述する生存届出の催告と失踪宣告で必要な官報公告の手数料です。申立時に納める必要はなく、家庭裁判所から連絡を受けて納付します。
詳しくは、申立先の家庭裁判所のホームページなどをご確認ください。
失踪宣告までの手続の流れ
失踪宣告の申立後の手続の流れは以下のとおりです。
- 調査官による調査
- 生存届出の催告
- 一定期間経過
- 失踪宣告
書面上だけではなく、実際に話を聞くかたちで不在者について調査が行われます。
催告期間は、普通失踪の場合は3カ月以上(特別失踪の場合は1カ月以上)の期間を家庭裁判所が定めます。その期間内に不在者または不在者の生存を知っている人が届出をしなければ失踪宣告がされます。
失踪宣告がされると、普通失踪の場合は失踪してから7年の期間が満了した時点で(特別失踪の場合は危難が去った時点で)、法律上死亡したものとみなされます。
失踪宣告後の手続の流れ
失踪宣告がされた後の手続は以下の通りです。
- 確定証明書の申請
- 失踪の届出
- 戸籍取得
まずは、失踪宣告の申立をした家庭裁判所で確定証明書の申請(印紙代150円)をします。
次に、審判書謄本と確定証明書を以下の市区町村役場の窓口に持参し、失踪の届出をします。
- 失踪者の本籍地
- 届出人の住所地
※失踪の届出は審判確定から10日以内にする必要があります。
そして、【死亡とみなされる日】の記載がある戸籍を取得するのですが、失踪の届出がされてから戸籍に反映されるまでは時間がかかります。
戸籍の記載を変更させる作業は本籍地の役場で行われているため、少しでも早く戸籍に反映してほしい場合は、失踪者の本籍地の役場窓口で届出をしたほうがよいでしょう。
注意点
失踪宣告制度の注意点をいくつか紹介します。
- 最低半年くらいかかる
- 不在者の相続人と遺産分割協議を行うことになる
- 生きていた場合に無効となるおそれがある
最低半年くらいかかる
申立書類の準備に1~2カ月、審理に1~2カ月、催告に3カ月、失踪宣告から戸籍の取得までに1カ月となると、早くても半年くらいはかかり、通常それ以上の期間を要します。
相続税の申告などがある場合は、不在者財産管理人を選任し遺産分割協議を行う方がよい可能性もあるため、注意が必要です。
未分割でも申告自体は可能ですが、特例の適用可否など専門的な知識を要しますので、まずは税理士に相談することをおすすめします。
不在者の相続人と遺産分割協議を行うことになる
失踪宣告により、不在者である相続人が死亡したものとみなされるため、不在者について相続が開始します。
不在者の相続人が、代襲相続人または相続人の地位を承継した者として、不在者に代わり遺産分割協議を行うことになります。
直ちに不在者以外の相続人と遺産分割協議を行えるわけではないため、ご注意ください。
不在者に相続人がいなければ、相続財産清算人の選任が必要となる場合もあります。
生きていた場合に無効となるおそれがある
不在者が生きていたことが判明して失踪宣告取消の審判が確定すると、遺産分割協議が無効になる場合があります。
それは、不在者が生きていることを知っている相続人が一人でもいた場合です。
失踪宣告が取り消されると、過去の法律行為の効果がさかのぼって消滅するのが原則です。ただし、取消前に善意でした行為は消滅しないことになっています。
善意とは「知らないで」ということです。
生きていることを知っている相続人がいる以上、善意でした行為とはいえないため原則通り消滅することになります。
まとめ
相続人の行方がわからないときの手続として、失踪宣告制度について説明しました。
失踪宣告制度は、書類を用意したり申立手続を行うこと自体も大変ですが、そもそも制度を利用すべきかどうかを判断するのが一般の方には困難なケースがほとんどでしょう。
不在者を法律上死亡したものとみなすという強力な効果があるため、利用の適否は慎重に判断すべきです。
さまざまな事情を考慮した結果、他の手続を選択する方がいい場合もあるかもしれません。
まずは、専門家である司法書士や弁護士に相談することをおすすめします。
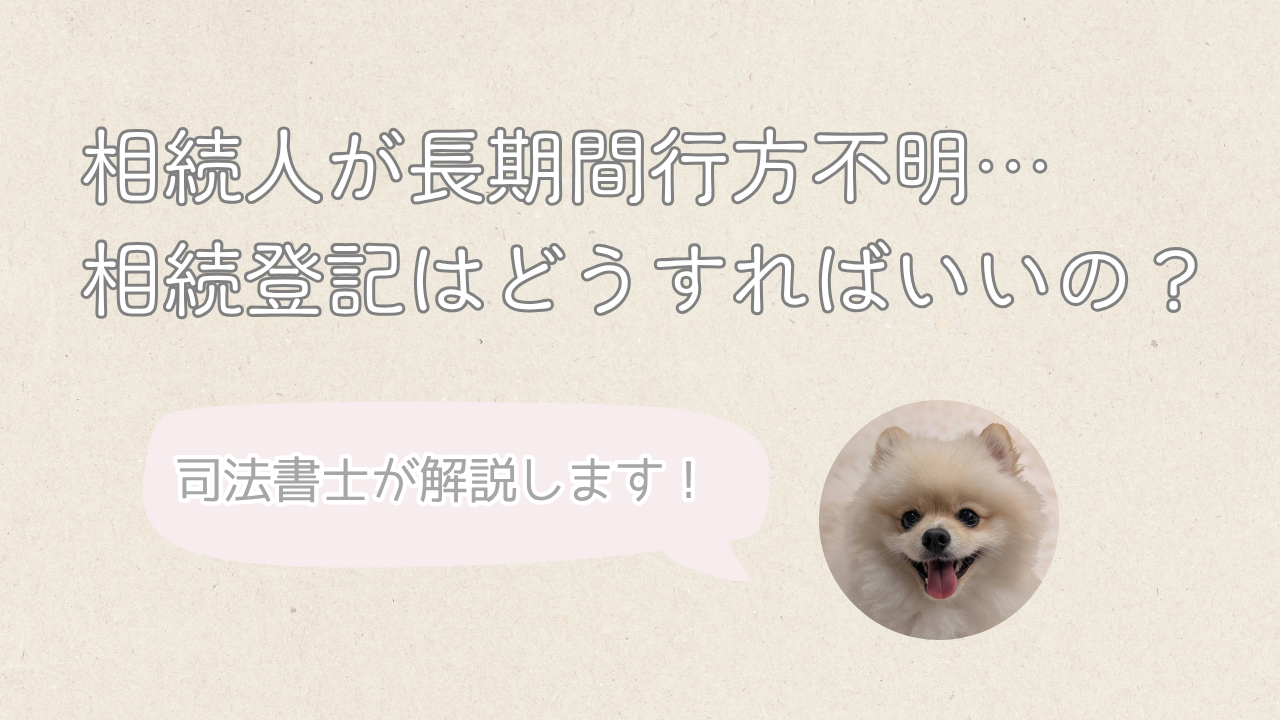
コメント