令和6年4月から相続登記が義務化され、不動産を取得したことを知ってから3年以内に登記を申請しなければ、原則として10万円以下の過料が科されることになりました。
ようやく相続登記が終わって一安心・・・といきたいところですが、相続した土地が農地の場合は「農地法の届出」をする必要があります。
この記事では、農地の相続登記をした後に必要な手続について解説します。
※本記事は、公開時点での法令等に基づいて作成されております。最新情報については、専門家にご相談いただくか、ご自身でご確認ください。
農地法の届出とは
相続により農地を取得した人は、農地法第3条の3の規定に基づき、農地の所在地の農業委員会に対して届出を行う必要があります。
(農地又は採草放牧地についての権利取得の届出)
第三条の三 農地又は採草放牧地について第三条第一項本文に掲げる権利を取得した者は、同項の許可を受けてこれらの権利を取得した場合、同項各号(第十二号及び第十六号を除く。)のいずれかに該当する場合その他農林水産省令で定める場合を除き、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、その農地又は採草放牧地の存する市町村の農業委員会にその旨を届け出なければならない。
(引用元:農地法|e-GOV 法令検索)
届出先
届出先は、農地の所在地の農業委員会です。
市区町村役場のホームページから農業委員会を探します。
下記に全国の農業委員会のURLが記載されているため、該当する市町村を検索するのも一つの方法です。
対象者
農地法3条の届出の対象となるのは、相続、遺産分割、包括遺贈などによる農地の取得者です。
特定遺贈により相続人が農地を取得した場合についても、対象となります。
一方で、相続人以外の人が特定遺贈により農地を取得した場合は、対象外です。
届出ではなく、農地法の許可が必要になるためです。
(農地又は採草放牧地の権利移動の制限)
第三条 農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合及び第五条第一項本文に規定する場合は、この限りでない。
(引用元:農地法|e-GOV 法令検索)
届出期限
届出期限は、相続が発生した日からおおむね10か月以内です。
届出を怠った場合、10万円以下の過料に処せられる可能性があります。
相続登記が完了したら、速やかに手続を行いましょう。
必要書類
- 届出書
- 登記簿謄本(登記事項証明書)
- 公図や住宅地図
- 身分証明書
- 委任状 ※代理人が手続を行う場合
自治体によって異なりますので、参考程度にしてください。(ある農業委員会では届出書のみでOKで、身分証明書さえ要らないと言われました。)
届出書は窓口で取得でき、記載例をもとに簡単に記入できます。書き方について不明な点があれば、職員の方が教えてくれます。
必要書類や当日の持ち物については、事前に電話で確認しておくと安心です。
相続した農地はどうすればいい?
相続した農地をどうするかについては次のような方法が考えられます。
- 売却または賃貸する
- 農地以外として活用する(農地転用)
- 相続土地国庫帰属制度の利用を検討する
それぞれ順番に説明します。
売却する・貸し出す
相続した農地で耕作ができるならそれに越したことはありません。
ですが、多くの場合は遠方に居住していたり、就農できる状況ではない場合がほとんどです。
遠方の農地を管理するのは非常に大変です。放っておけば草が生い茂り、周囲の農家へも影響が出てしまいます。
相続した農地の管理が困難な場合は、農業委員会が管理の相談や借り手を探してくれることがあります。
できることなら売却したいところですが、農地はなかなか買い手が見つからないのが現実です。耕作希望者に賃し出すことによって、代わりに管理をしてもらうことができます。
自分で借り手を見つける他、農地バンクという中間管理機構に貸し付けることができる場合もあります。
詳しくは農業委員会に相談してみてください。
農地以外として活用する(農地転用)
市街地にある農地の場合は、比較的簡単に農地転用の手続ができます。
相続の届出と同様、必要書類を添付して届出書を提出するだけで完了します(※生産緑地を除く)。
一方、市街化調整区域にある農地については、農地転用の許可を得るのは困難です。
農地にも種類があり、例えば、農振農用地は基本的に農地転用できないとされています。
この分野の専門家は行政書士なので、農地転用の手続をしたい場合は、お近くの行政書士までご相談ください。
相続土地国庫帰属制度の利用を検討する
令和5年4月からは、一定の要件のもとで相続した土地を国に引き渡すことができる制度も始まりました。
ただし、要件が厳しく、管理費相当額の負担金も馬鹿になりません。
田・畑の場合、基本的には面積にかかわらず20万円ですが、一部の市街地(都市計画法の市街化区域又は用途地域が指定されている地域)等については面積に応じて算定され、1,000㎡の場合、約110万円になります。
また、審査手数料(土地一筆14,000円)も必要です。
適用の可否、負担金と将来的な管理費等を総合的に考慮して、利用すべきか検討してください。
まとめ
農地を相続した際には、不動産登記法に基づく相続登記と、農地法に基づく届出の両方が必要です。
この記事では、農地法の届出について解説しました。
届出自体はとても簡単なので、私の事務所でも通常は依頼者の方に自分で手続をしていただいています。
罰則もあるので、相続登記が完了したら速やかに手続をすることをおすすめします。
この記事が参考になれば幸いです。
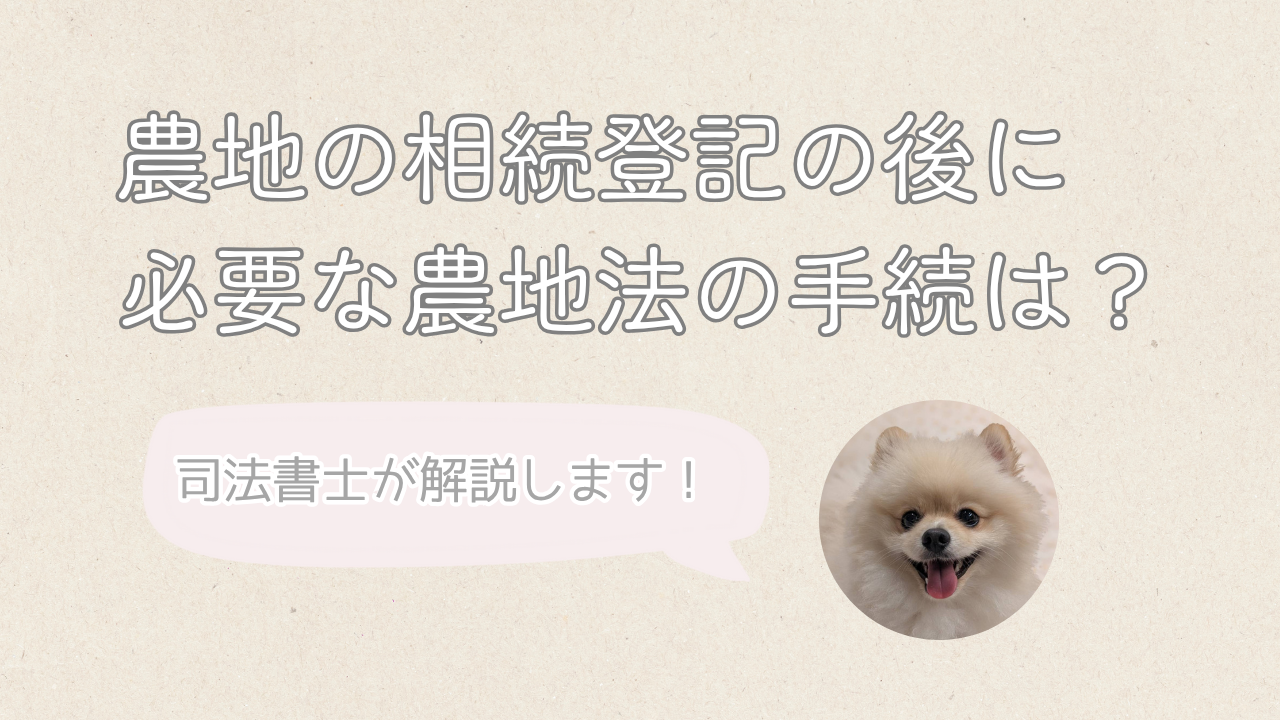
コメント