成年後見人は、判断能力が不十分な方を保護するために、家庭裁判所が選任します。
相続登記においては、重度の認知症で判断能力を欠いている方は、一人で遺産分割協議に参加することができません。そのため、成年後見人が本人の代理人として遺産分割協議に参加し、遺産分割協議書を作成します。
この記事では、相続人が認知症などで判断能力が不十分な場合に行う成年後見人の選任手続について解説します。
※本記事は、公開時点での法令等に基づいて作成されております。最新情報については、専門家にご相談いただくか、ご自身でご確認ください。
成年後見人の選任手続
相続人が高齢である場合に認知症を患っているケースは少なくありませんが、認知症の程度によっては、家庭裁判所で成年後見人の選任手続をしなければなりません。
成年後見人の選任は、本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。
誰が申し立てることができるのか、必要書類・費用に関しては以下のとおりです。
申立人
本人、配偶者、四親等内の親族、検察官、市区町村長などが申立てを行うことができます。
四親等というのは、祖父母や孫はもちろんのこと、高祖父母、玄孫、甥姪の子まで含みます。ほぼ親族全員という認識で大丈夫です。
また、身寄りのない方は、市区町村長の申立により成年後見人が選任される場合があります。
必要書類
成年後見人選任の申立には、非常に多くの書類を収集し、または作成する必要があります。
また、ケアマネージャーの方や主治医の方の協力も必要となります。
裁判所のホームページに詳しく記載されているので、下記のリンクをご確認ください。
費用
- 収入印紙(3400円分)
- 予納郵券(切手のこと。家庭裁判所による)
- 鑑定費用(必要な場合。10万円〜20万円)
切手代は家庭裁判所により異なります。管轄家庭裁判所のホームページなとでご確認ください。
鑑定費用は、鑑定が必要な場合に発生します。鑑定とは、本人の判断能力を検査することで、法律上は原則として行うものとされています。
ですが、実際のところは、診断書その他の書類の内容から判断能力をいていることが明らかなため、鑑定を行わないことが多いです。
申立時点では鑑定費用を納める必要はなく、裁判所の連絡を受けてからで大丈夫です。また、審判で本人負担とされた場合は、本人の財産から支払うことができます。
成年後見人が選任された後はどうなる?
通常1〜2カ月で審理が終了し、家庭裁判所が成年後見人を選任します。
成年後見人には、審判書が送付されます。やがて審判が確定すると、法務局に後見登記がされ、登記事項証明書が取得可能となります。
成年後見人は、成年被後見人の代理人として遺産分割協議に参加し、遺産分割協議書に実印で押印します。
相続登記には、法務局で取得した登記事項証明書と成年後見人の印鑑証明書を提出します。
成年後見人選任手続の注意点
注意すべき点として、以下の5つがあります。
- 後見人を選ぶことができない
- 途中で取下げができない
- 法定相続分の確保が原則
- 特別代理人の選任が必要な場合もある
- 本人が亡くなるまで続く
後見人を選ぶことができない場合がある
できたら親族や本人のことをよく分かっている人に後見人を務めてほしいものです。
申立人は、後見人候補者を申立書に記載します。
ですが、最終的に後見人を選任するのは家庭裁判所です。総合的な判断の結果、弁護士や司法書士などの専門家が選任される場合もあります。
また、後見監督人というかたちで、専門家が御目付役として置かれる場合もあります。そして、これらの決定には不服申立ができません。
途中で取下げができない
一度申立をすると、「やっぱり止めた」ができません。
審判がされる前であっても、申立の取下げをするには家庭裁判所の許可が必要です。
自分の望みどおりの後見人が選ばれそうにない、問題が解決したため後見人を選任する必要がなくなったといった理由では、原則として家庭裁判所の許可は得られません。
法定相続分の確保が原則
成年後見人は、本人を保護するため財産を適正に管理し、その維持保全に努めなければなりません。
遺産分割協議において、成年後見人は、本人の取り分が法定相続分を下回ることがないように努めなければなりません。
特殊な事情により法定相続分通りの協議が困難である場合は、家庭裁判所に事前に相談することが求められます。
特別代理人の選任が必要な場合もある
成年後見人も相続人である場合は、利益相反の問題が生じるため、本人のために特別代理人を選任する必要があります。
特別代人の選任については、こちらの記事も参考にしてください。
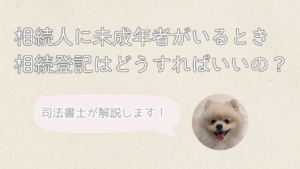
本人が亡くなるまで続く
成年後見人の職務は、本人が判断能力を取り戻して裁判所の取消しの審判を受けない限り、本人が死亡するまで続きます。
その間、本人の財産に関するあらゆる行為能力は制限されます(日用品の購入その他日常生活に関する行為を除く)。
後見人に選任された人は、成年後見制度の趣旨に従い、本人の財産を適正に管理し、事務報告書・財産目録・収支予定表といった書類を作成し家庭裁判所に提出しなければなりません。
また、毎年発生する成年後見人の報酬については、金額を家庭裁判所が決定し、本人の財産から支払われます。
遺産分割協議など申立のきっかけになった問題が解決した後も、成年後見人の職務はずっと続きます。
この点を理解していないと、後になって大きな問題になりかねませんのでご注意ください。
まとめ
遺産分割の方法で相続登記をする際に、相続人が認知症などで判断能力を欠いているときは、成年後見人の選任手続が必要となります。
成年後見人が本人に代わって遺産分割協議に参加し、遺産分割協議書に押印します。そして、相続登記が完了した後も、成年後見人の職務は続きます。
認知症の相続人がいる場合の相続登記手続は複雑であり、専門的な知識が求められます。まずは専門家である司法書士や弁護士に相談することをおすすめします。
この記事が参考になれば幸いです。
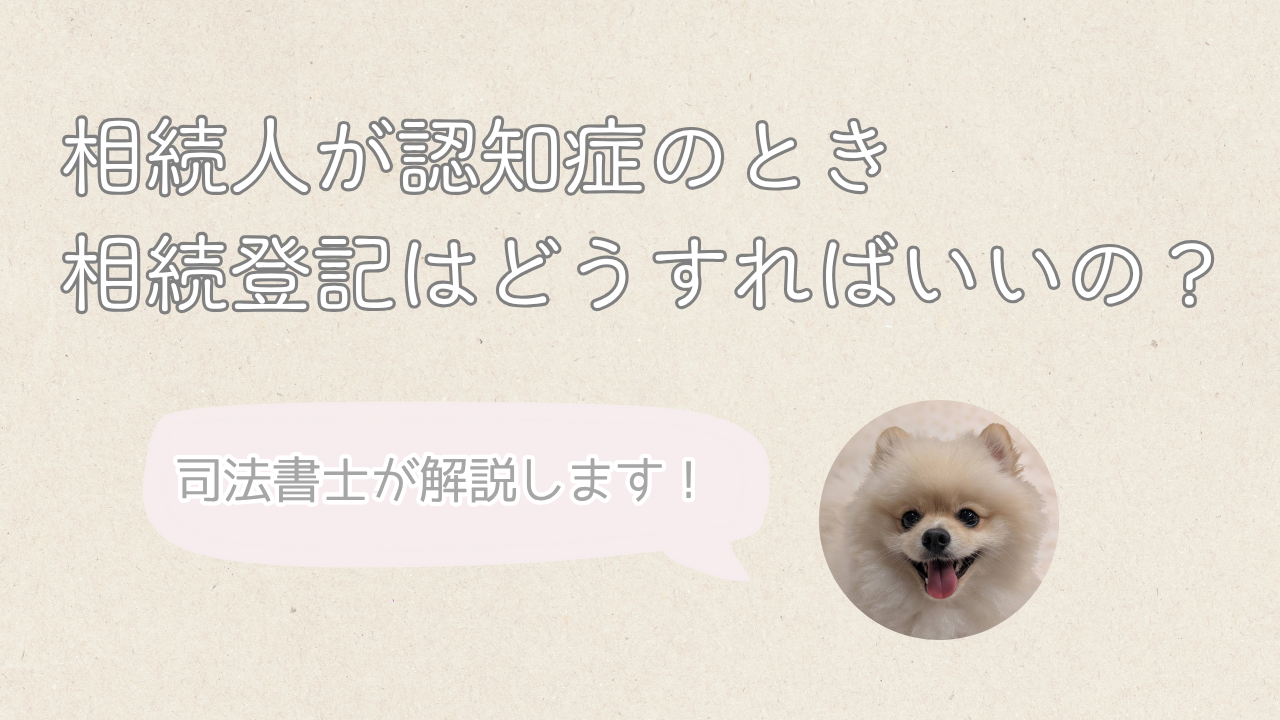
コメント