不動産の相続登記でも、金融機関や証券会社の相続手続でも、必ず用意しなければならないのが「戸籍」です。
法定相続情報一覧図は、戸籍の束の代わりとなり、相続関係を明確に証明してくれます。
複数の管轄法務局に相続登記を申請しなければならない場合や、金融機関や証券会社など、複数の機関に戸籍を提出する場合にあると便利です。
この記事では、法定相続情報一覧図の取得方法について解説します。
※本記事は、公開時点での法令等に基づいて作成されております。最新情報については、専門家にご相談いただくか、ご自身でご確認ください。
法定相続情報一覧図の取得方法は?
法定相続情報一覧図とは、被相続人(亡くなった方)の相続関係をまとめた図で、法務局が認証した公的な書類です。
申出人が作成した法定相続情報一覧図と必要書類を提出して、内容が正しいことを法務局が確認した上で発行されます。
法定相続情報証明制度といい、2017年5月に創設されました。
手続の流れは?
法定相続情報証明制度の流れは、以下のとおりです。
- 必要書類を収集する
- 一覧図を作成する
- 1・2を申出書とともに提出
- 一覧図の写しが申出書に記載した通数分交付される
申出は被相続人の本籍地、最後の住所地、不動産の所在地、申出人の住所地のいずれかを管轄する法務局にて行います。
相続登記と同時に行うことも可能ですが、後で再交付を受けるときに窓口に行きやすいかなども考慮した上で申出先を検討してください。
一覧図の作成には、法務局のフォーマットが利用できます。
また、必要書類についても、わかりやすくまとめられています。
どんなときに使える?
以下のような場面で相続関係を証する書面として活用できます。
- 不動産の相続登記
- 銀行預金の相続手続
- 証券口座の名義変更
- 年金手続
- 相続税の申告手続
利用の拡大についてはこちらのページにまとめられています。
法定相続情報一覧図は、相続手続を複数の機関に対して行う必要がある場合に、あるととても便利です。
申出から5年間は、再交付を受けることもできます。すぐに使わなくても、将来的に利用する可能性がある場合は、手続をしておいて損はないといえます。
一方、戸籍の使い途が自宅の相続登記のみである場合は、取得しなくても大丈夫です。
注意点は?
法定相続情報証明制度の注意点として、次の3つを紹介します。
- 記載事項の変更には対応が必要な場合がある
- 続柄の記載によっては税申告に利用できない
- 外国人がいる場合には利用できない
記載事項の変更には対応が必要な場合がある
法定相続情報には任意で住所を記載することができます。
ですが、記載されている住所や氏名に変更があった場合は、変更を証する書面を補完的に提出しなければならない場合もありますので、注意が必要です。
続柄の記載によっては税申告に利用できない
一覧図に記載する続柄については、戸籍通りの記載ではなく、単に「子」とすることが認められています。
婚姻関係にない男女の間で生まれた子には、戸籍上、「男」や「女」と記載されますが、これらを区別なく「子」と表記することが認められています。
ただし、相続税の申告に利用できないため、戸籍通りに記載する方がよいかもしれません。
外国人がいる場合には利用できない
外国籍の相続人には、戸籍がありません。
住民票があり、印鑑登録をしていても、戸籍がなければ法定相続情証明制度を利用することはできません。
反対に、日本国籍があれば、海外に在住していても制度を利用することができます。
まとめ
法定相続情報証明制度を利用することで、戸籍を何度もコピーして提出する手間が省け、手続がスムーズになります。
特に複数の機関へ相続書類を提出しなければならない場合に有用ですので、必要に応じて是非ご活用ください。
法定相続情報証明制度を利用するには、前提として、戸籍を正確に読み取ることが必要となります。
被相続人が結婚・離婚を繰り返していた場合や、養子縁組や認知によって相続人となる場合など、戸籍の読み取りや一覧図作成に苦労することがあります。
作成が難しい場合は専門家にご相談ください。
この記事が参考になれば幸いです。
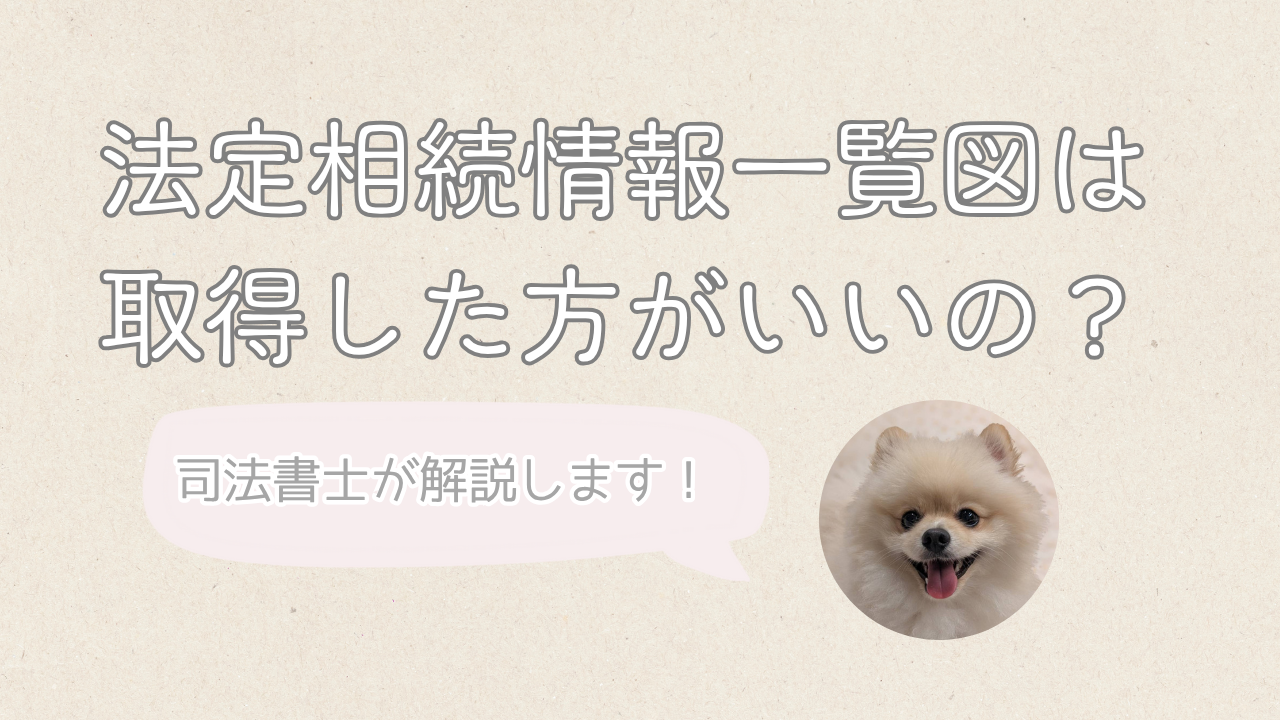
コメント