固定資産評価証明書は必要?取得方法と注意点は?
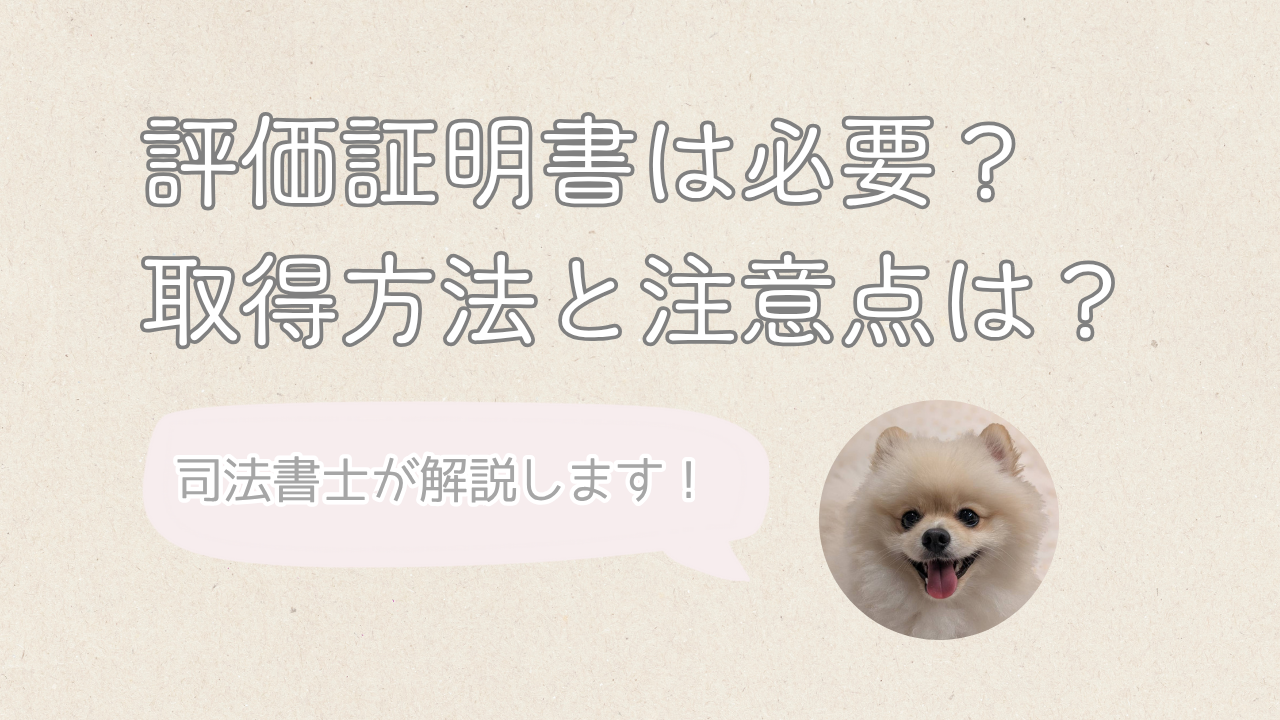
相続登記を申請する際、登録免許税を納付しますが、税額の計算につかうのが「固定資産評価証明書」です。
固定資産(土地・建物)の評価額を証明する公的な書類ですね。課税台帳登録証明書ともいって、固定資産税の課税対象となる不動産の評価額が記載されています。
固定資産評価証明書は、不動産所在地の市区町村役場で取得でき、相続登記でも基本的には必要となります。
この記事では、固定資産評価証明書の取得方法や注意点について解説します。
※本記事は、公開時点での法令等に基づいて作成されております。最新情報については、専門家にご相談いただくか、ご自身でご確認ください。
固定資産評価証明書の取得方法
固定資産評価証明書とは、不動産の固定資産税評価額を証明する書類です。相続登記の登録免許税を計算するために必要で、登記申請時に法務局へ提出します。
どこの市区町村で取得すればいいの?
固定資産評価証明書は、不動産の所在地の市区町村で発行されます。
不動産の所在地は、登記簿謄本(登記事項証明書)や権利証、固定資産税納税通知書で確認することができます。
複数の不動産がある場合は、それぞれの不動産所在地ごとに別々の市区町村役場で取得する必要があります。
どこで手続きすればいいの?
取得方法は次の3通りです。
- 窓口申請
- 郵送申請
- オンライン申請(要マイナンバーカード)
おすすめは窓口申請ですが、遠方の場合は郵送の方法によらざるを得ません。
オンライン申請は一部の自治体で実施されており、順次拡大している模様です。市区町村ホームページ等で確認をしてください。
取得に必要な書類は?
役所によって異なりますが、一般的には以下のものが必要です。
- 本人確認書類(運転免許証など)
- 被相続人の死亡の記載がある戸籍
- 被相続人との関係がわかる戸籍
- 委任状(代理人が申請する場合)
詳細は、各市区町村のホームページ等で事前に確認するのが安心です。
被相続人の氏名・住所・不動産の正確な所在地がわかる書類(固定資産税納税通知書など)があると手続きがスムーズです。
不動産の所在地番がわからない場合、名寄帳を取得する必要があります。名寄帳については下記の記事も参考にしてください。
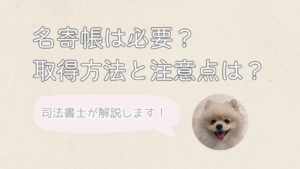
発行手数料は?
市区町村ごとに異なりますが、1通あたり200円~400円が一般的です。
窓口よりも郵送の方が少し金額が高い場合があります。
また、郵送の場合は手数料を小為替で納付するので、あらかじめ金額を調べておく必要があります。
各自治体ごとにホームページ上でわかりやすく記載してありますので、ご確認ください。
注意点
固定資産評価証明書を取得する上で注意すべきなのは以下の点です。
- 登記を申請する年度のものが必要
- 非課税の不動産には評価額が記載されない場合がある
たとえば、令和7年3月28日(令和6年度)に取得した固定資産評価証明書は、令和7年4月1日(令和7年度)に相続登記を申請するために使用することができません。
固定資産の評価には、賦課期日というものがあり、毎年1月1日時点の価格を登録しています。
評価額は3年に一度見直しがされることになっており、前回は令和6年度に評価替えが行われたため、令和9年度までは価格が据え置かれることになります。
ただし、その間に地目の変更や増改築、地価の下落などの理由で価格が修正される場合があります。
法務局は、価格が修正されたかどうかを知る由もないので、登記を申請する年度の評価証明書を使用することになっているのです。
過年度の評価証明書は登記に使用できないため、取得する時期には注意しましょう。
また、私道など評価額のない土地や年度の途中で地目が変更した土地については、近傍宅地価格等計算の基準となる価格を記載してもらう必要があります(自治体により取扱が異なるため、事前に伝えておくと安心です)。
まとめ
相続登記の準備には、評価証明書の取得が基本的に必要となります。
不動産の所在地が判明している場合は、その市区町村役場の窓口に行くのが最も手っ取り早く確実ですが、郵送で請求する場合は、事前に電話等で問い合わせると安心です。
マイナンバーカードを利用してオンライン請求ができる自治体も増えてきています。各自治体ごとにホームページ上で情報を公開しているので、ご確認ください。
この記事が参考になれば幸いです。
コメント