遺産分割協議書の作成にこれといった決まりはなく、もっと言えば、遺産分割協議自体は書面を作成することが成立の要件とされておりません。
そのため、「相続人全員が合意する」だけで有効に成立します。
しかし、後のトラブルを防ぐためにも合意した内容を書面にするのが一般的で、相続登記に使用するには一定のポイントを押さえる必要があります。
この記事では、相続登記に使用する遺産分割協議書の作成方法について解説します。
※本記事は、公開時点での法令等に基づいて作成されております。最新情報については、専門家にご相談いただくか、ご自身でご確認ください。
遺産分割協議書を作成する流れは?
遺産分割協議書を作成する際の流れは以下のとおりです。
- 相続財産を洗い出す
- 相続人を確定する
- 誰が何を相続するか話し合う
- 書面を作成する
遺産分割の前提として、相続財産を調査して相続人を確定する必要があります。
話し合いは全員が一同に会する必要はなく、電話やメール、手紙等どのような方法でも大丈夫です。
結果的に一つの内容に対して全員で合意すればよいので、ABC全員が一度に話し合う必要はなく、AとBが話した後、BとCが話すようなかたち(AとCは話していない)でも大丈夫です。
遺産分割協議書には何を書く?
遺産分割協議書に記載するのは以下の通りです。
- 被相続人の本籍・氏名・死亡日
- 分割内容
- 協議書を作成した日付
- 相続人全員の住所・氏名
書き方のポイント
手書きでもパソコンでも大丈夫です。
相続人の住所・氏名もパソコンでも大丈夫ですが、後のことを考えると、少なくとも署名をするのが無難です。
また、相続財産は、第三者が見てもそれとわかるように特定して記載することが重要です。
不動産に関しては、登記簿謄本(登記事項証明書)の記載通りに書けば大丈夫です。
登記されている内容と異なると、相続登記をする上で支障が出てしまいますので、ご注意ください。
また、遺産分割協議書には相続人全員が実印を押す必要があります。認印では登記に使用できません。
印鑑証明書で印影の確認をすることが必要です。実印だと思っていたけど実は違った、なんてことが本当によくあるので。
遺産分割協議書の注意点
遺産分割協議書の成立には、以下の要件を満たす必要があります。
- 相続人全員が参加すること
- 相続人に十分な判断能力があること
遺産分割協議には、相続人全員が参加する必要があります。よって、相続人が一人でも欠けていると無効になります。
相続人に未成年者や認知症の方、行方不明者がいる場合、家庭裁判所の手続(特別代理人の選任など)が必要になることがあります。
遺産分割協議書に勝手に実印を押したり、偽造した遺産分割協議書を使用して登記の申請をすることは、いずれも犯罪行為に該当する可能性があります。絶対にしないようにしましょう。
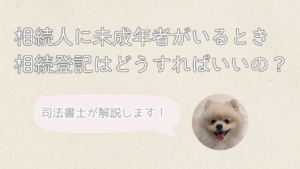
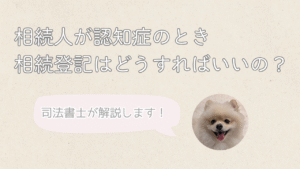
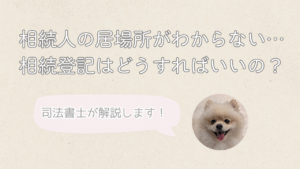
まとめ
遺産分割協議を作成する上で、押さえておくべきポイントについて説明しました。
せっかく遺産分割協議書を作っても要件を満たしていなければ、相続登記手続に使用することはできません。
これまで、(少ないですが)依頼者が自分で作成した遺産分割協議書を使用して相続登記を申請したこともあります。
一方、不動産の記載に誤りがあったり、実印ではなかったり、相続人が全員記載されていなかったりして、作り直しになってしまったこともあります。
時間と労力を考えると、初めから専門家に相談しておけば間違いありません。
この記事が参考になれば幸いです。
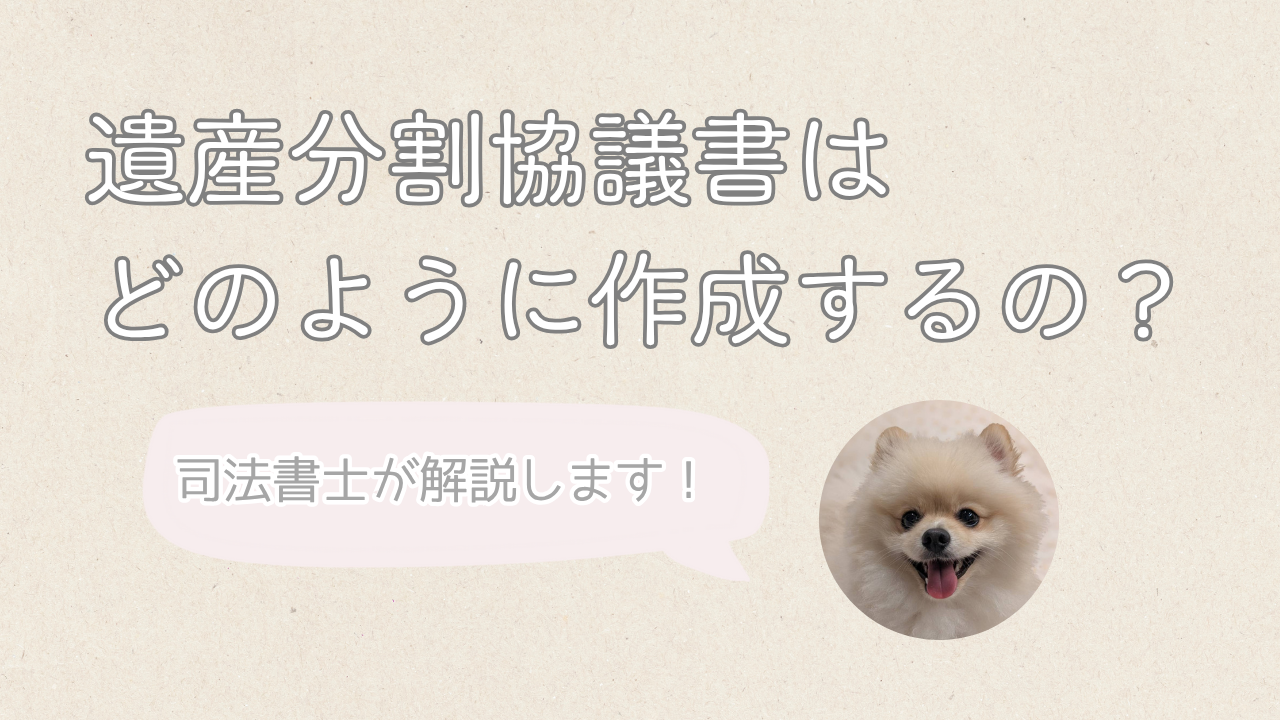
コメント