遺産分割協議の成立には相続人全員の参加が必要であり、相続人が行方不明の場合であっても例外ではありません。
相続人の居場所がわからない場合、遺産分割協議を成立させるには、不在者財産管理人の選任を申し立てるか、失踪宣告を申し立てる方法があります。
いずれも家庭裁判所の手続ですが、失踪宣告についてはこちらの記事で解説しました。
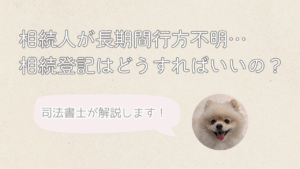
この記事では、不在者財産管理人の選任申立について解説します。
※本記事は、公開時点での法令等に基づいて作成されております。最新情報については、専門家にご相談いただくか、ご自身でご確認ください。
不在者財産管理人とは?
不在者財産管理人は、行方不明の相続人に代わって財産を管理するために家庭裁判所が選任します。
不在者財産管理人の選任は、不在者の従来の住所地または居所地を管轄する家庭裁判所に申立を行います。
申立人
申立を行うことができるのは、利害関係人または検察官です。
利害関係人とは、不在者の配偶者、相続人、債権者などです。
必要書類
- 申立書
- 不在者の戸籍謄本と戸籍の附票
- 不在の事実を証する資料
- 不在者の財産に関する資料
- 申立人の利害関係を証する資料
- 財産管理人候補者の住民票または戸籍の附票
頭を悩ませるのは、不在の事実を証する資料です。
不在者とは、従来の住所または居所を去り容易に戻る見込みがないものと定義されます。
抽象的で曖昧な規定ですが、「容易に戻る見込みがない」ことをどのように証するかが重要です。
不在の事実を証する資料とは?
不在の事実を証する資料として家庭裁判所では、
- 行方不明者届受理証明書
- 住所宛てに送付したが返送された郵便物
- 現地調査報告書
- 近親者の陳述書
などが例示されています。
何を提出すれば足りるということはなく、不在者の所在を調査する上で参考になりそうなものをできるだけ添付することが推奨されています。
現地調査報告書については、郵便物が返送された理由が「留置期間経過」である場合は添付が必要とされています。
直接見に行くだけではなく、管理会社に問い合わせたり、近隣住民に聞き込みをしたりといった具体的な調査を行うことが必要となります。
費用
- 収入印紙800円分
- 予納郵券(切手のこと)
切手代は裁判所によって異なります。
なお、不在者の財産で財産管理費用等を支払うことができない場合、予納金として相当額(30万円~50万円程度)を申立人が納めなければなりません。
詳しくは、申立先の家庭裁判所のホームページなどをご確認ください。
遺産分割協議は許可が必要
不在者財産管理人が遺産分割協議に参加する場合、家庭裁判所の権限外行為許可の手続が必要となります。
財産管理人は、不在者の財産を維持管理する行為について不在者を代理する権限を有します。
不在者の財産をいたずらに減少させたり、価値を毀損するおそれがある行為は行うことができません。
遺産分割協議の内容が不在者にとって不利益にならないかを確認するため、家庭裁判所の許可が必要となります。
注意点
不在者財産管理人制度の注意点をいくつか紹介します。
- 法定相続分の確保が原則
- 相続人は財産管理人になれない場合もある
- 不在者財産管理人の職務は継続する
法定相続分の確保が原則
前述しましたが、財産管理人は、不在者の財産を維持管理するために行動する必要があります。
そのため、遺産分割協議に不在者の法定相続分が確保されていない場合、家庭裁判所の権限外行為許可が下りない可能性があります。
相続人は財産管理人になれない場合もある
遺産分割を目的に不在者財産管理人選任の申立をする場合、利益相反が生じるため、相続人を財産管理人に選任することができません。
不在者財産管理人の職務は継続する
財産管理人の職務は不在者が現れたとき、不在者が死亡したことが確認されたとき,不在者の財産がなくなったとき等まで続きます。
申立のきっかけとなった問題(例えば、遺産分割による相続登記)が解決した後も、財産管理人の職務は継続するため注意が必要です。
まとめ
相続人の行方がわからないときの手続として、不在者財産管理人制度について説明しました。
不在者財産管理人制度は、書類を用意したり申立手続を行うこと自体も大変ですが、そもそも制度を利用すべきかどうかを判断するのが一般の方には困難なケースがほとんどでしょう。
さまざまな事情を考慮した結果、他の手続を選択する方がいい場合もあるかもしれません。
まずは、専門家である司法書士や弁護士に相談することをおすすめします。
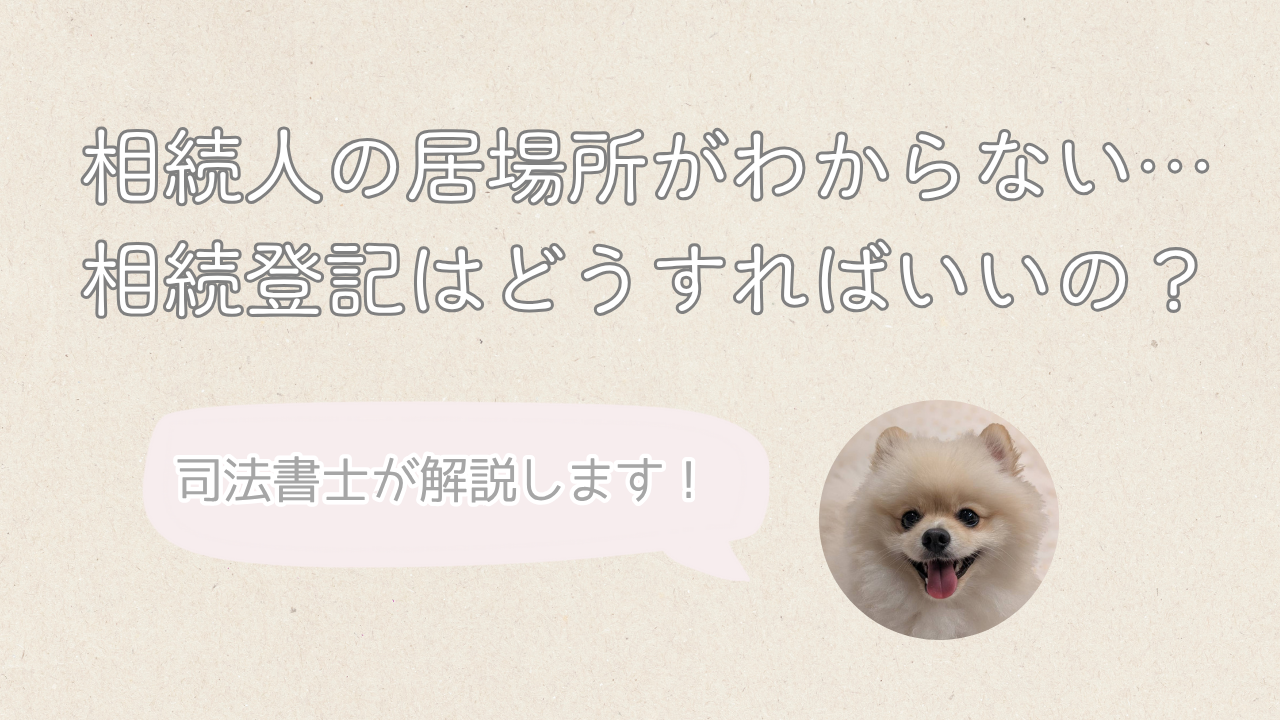
コメント