遺言書を作成する方法にはいくつかありますが、その中でも「公正証書遺言」が選ばれることが多いのには理由があります。
それは、法律上無効となるリスクが極めて低いことや、紛失・改ざんのおそれがないため、自らの希望に沿ったかたちで遺言書を確実に作成することができるからです。
この記事では、そんな公正証書遺言のメリット・デメリットを解説します。
※本記事は、公開時点での法令等に基づいて作成されております。最新情報については、専門家にご相談いただくか、ご自身でご確認ください。
公正証書遺言とは?
遺言にはいくつか種類があり、「自筆証書遺言」は、自分で全文を手書きして作成する遺言書です。費用がかからず、思い立ったとき一人ですぐ作れるのが利点です。
一方で、「公正証書遺言」は、公証役場で公証人に作成してもらう公正証書です。作成には政令所定の手数料がかかり、2名以上の証人による立会いが必要です。
公証役場とは
公証役場とは、公証人が執務する事務所のことで全国に約300箇所あります。詳細な場所については、下記のホームページをご確認ください。
公証人とは
公証人とは、公正証書の作成や私署証書の認証、確定日付の付与といった公証事務に従事する元裁判官・検察官・弁護士等の専門家で、全国に約500人しかいません。
公証人は、高度な専門知識を有し、中立・公正な立場で国の公務である公証事務を担います。
公正証書とは
公正証書は、公証人が職務上の権限で作成する公文書です。そのため、真正に成立した(当事者の意思に基づいて作成された)という強い推定が働きます。
また、作成過程で公証人がその法的有効性について確認するため、効力を争うような事態に発展するリスクを限りなく低く抑えることができます。
公正証書遺言のメリット
公正証書遺言を作成する手間や費用を考えると比較的簡単に作れる自筆証書遺言の方がよい気がしますが、公正証書遺言には以下のようなメリットがあり、多くの人に選ばれています。
- 遺言の内容に法的不備がない
- 紛失・改ざんのおそれがない
- 家庭裁判所の検認が不要
- 見つけてもらえない心配がない
- 自書できない場合でも作成可能
以上について、自筆証書遺言と比較しながら説明していきます。
遺言の内容に法的不備がない
公証人が内容をチェックするため、法律上無効になるリスクがほぼありません。遺言としての要件がきちんと満たされているか、公証人が確認してくれます。
【自筆証書遺言の場合】
内容の確認がなされず、無効となってしまうリスクがあります。
紛失・改ざんのおそれがない
作成された遺言書の原本は、公証役場で保管されます。火事や盗難による紛失や保管場所の失念、第三者による書き換えなどのリスクが極めて少なくなります。
【自筆証書遺言の場合】
遺言者が保管場所を忘れてしまったり、遺言書の保管者や発見者が勝手に中を覗き見て書き換えたり、破棄するおそれがあります。
家庭裁判所の検認が不要
公正証書遺言は家庭裁判所の検認手続を経ることなく、すぐに相続手続に進めます。
【自筆証書遺言の場合】
家庭裁判所に申立が必要となり、手続に時間がかかります。
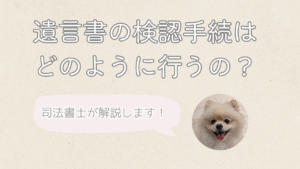
見つけてもらえない心配がない
公正証書で遺言を作成したことを相続人や受遺者となる方等に伝えておけば、亡くなった後に遺言書を見つけてもらえないリスクがなくなります。
遺言者が亡くなった後に、相続人や受遺者等の利害関係人は、公証役場で遺言書を検索し謄本の交付を受けることができるからです。
また、生前に遺言の内容を確認できるのは遺言者に限られるため、中身を覗き見られる心配はありません。
【自筆証書遺言の場合】
具体的な保管場所を知らせていなければ、亡くなった後に遺言書を見つけてもらえないまま処分されてしまうおそれもあります。他人に預けるにしても、破棄や書き換え等のリスクはあります。
自書できない場合も作成可能
公証人は遺言者に代わって署名したり、押印することができます。
そのため、自分で文字を書くことが困難な場合でも、有効な遺言書を問題なく作成することができます。
【自筆証書遺言の場合】
原則として全文を自書する必要があるため、自分で文字を書けないと作成できません。
公正証書遺言のデメリット
メリットばかりに見える公正証書遺言ですが、デメリットもあるため、一応触れておきます。
費用がかかる
公正証書の作成費用がかかります。
手数料の金額は政令(公証人手数料令第9条)で定められていますが、遺言の目的である財産の価格によって増減します。また、遺言者が公証役場に行けないときの出張料等の費用が別途発生する場合もあります。
加えて、司法書士等の専門家に依頼する費用もかかります。
証人が2名必要
遺言作成時に2名以上の証人の立会いが必要です。
未成年者及び推定相続人・受遺者の配偶者や直系血族は証人になることができません。
司法書士等の専門家に依頼することも可能ですが、別途費用が発生します。
亡くなった時に通知するシステムはない
亡くなった時に遺言書が保管されていることを相続人等に通知するような仕組みはありません。
遺言書を書いたこと自体を秘密にしておきたい場合は、相続人等が公証役場に行かない限りは見つけてもらえないリスクがあります。
ただし、遺言執行者を指定することでこの問題は回避できます。遺言執行者が相続人等に対して通知を送ってくれるからです。
公正証書遺言に限らずですが、遺言書の作成と遺言執行者の指定はセットで行うようにしましょう。
なお、2020年7月に開始した自筆証書遺言書保管制度では、遺言者が亡くなった際に遺言書を保管している事実をあらかじめ遺言者が指定した者に対して通知する仕組みがあります。
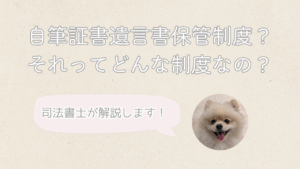
まとめ
公正証書遺言は「確実性と安心」を重視する人におすすめです。
自筆証書遺言の方が簡単に作成できる一方で、無効になるリスクや紛失・改ざんのリスクも少なくありません。
遺言は、人生最期の意思表示といわれます。
無効になってしまったり、相続人同士で争いになってしまったりという事態を防ぐためにも、公正証書で遺言書を作成するのはいかがでしょうか。
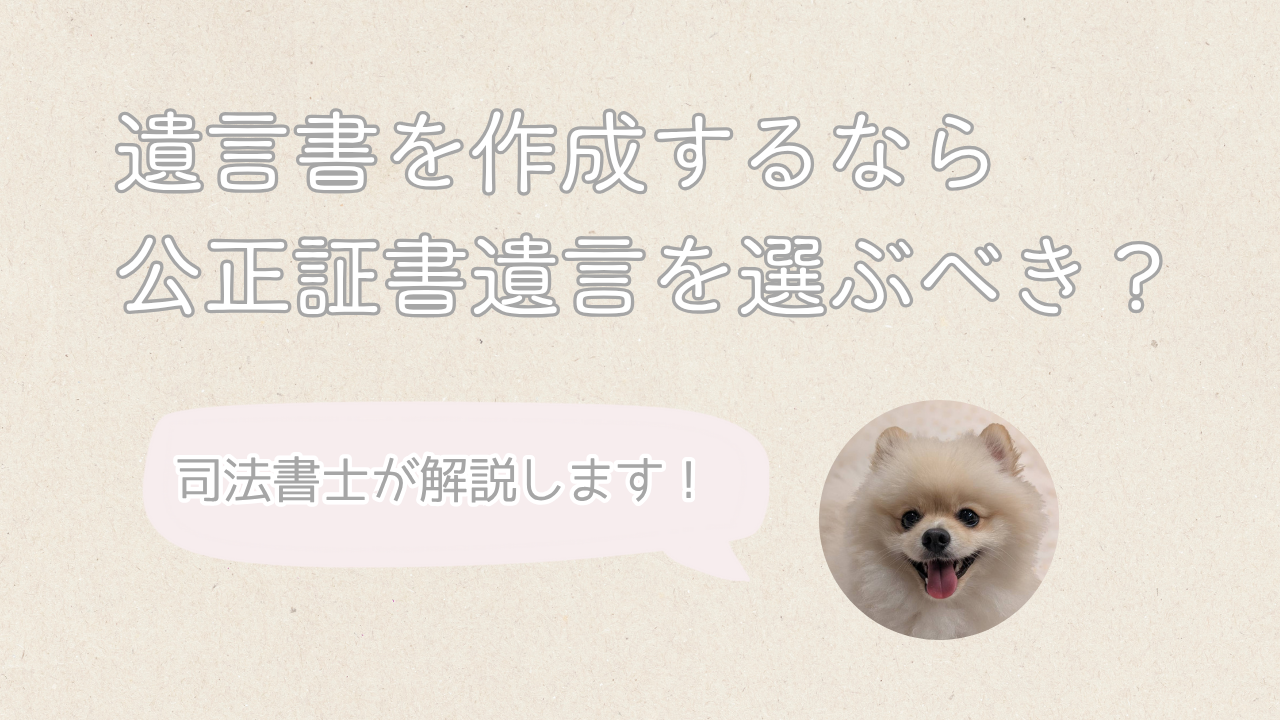
コメント