遺産分割協議には相続人全員の参加が必要です。
相続人の内たった一人でも連絡がとれない場合には、遺産分割協議を有効に成立させることはできません。
遺産分割協議ができないと、必要な書類を整えることができず、相続登記手続が前に進まなくなってしまいます。
連絡がとれない相続人がいる場合、家庭裁判所に遺産分割調停の申立をすることで手続を進めることができます。この記事では、遺産分割調停の申立について解説します。
※本記事は、公開時点での法令等に基づいて作成されております。最新情報については、専門家にご相談いただくか、ご自身でご確認ください。
まずは遺産分割協議を試みる
遺産分割調停を申し立てる前提として、通常、さまざまな方法で連絡を試みます。
メールアドレスがわかればメールをし、電話番号がわかれば電話を掛け、住所がわかれば手紙を送ります。
被相続人が亡くなり、相続人である旨、相続手続に協力が必要なため連絡をとりたい旨を伝えます。
それでも返事がもらえなかったり、途中で音信不通になってしまった場合に、遺産分割調停という家庭裁判所の手続を利用することになります。
遺産分割調停とは?
遺産分割調停は、家庭裁判所の裁判官と調停委員から成る調停委員会のサポートのもと、相続人が遺産分割に関する話し合いを行う手続です。
原則公開となる訴訟と異なり、話し合いは非公開で行われるためプライバシーが保たれます。
調停委員会は各相続人の意見や希望を聞くだけではなく、必要な助言・解決案の提示まで行います。
それでも話し合いがまとまらない場合は、審判手続に移行し、裁判所が遺産分割の内容を決定します。
遺産分割調停の申立方法は?
遺産分割調停は、相手方(申立人以外の相続人等)の住所地を管轄する家庭裁判所または当事者が合意によって定める家庭裁判所に申し立てます。
申立書や申立の事情について記載した書面を作成し、添付書類とあわせて管轄の家庭裁判所に提出します。
必要書類や費用については、下記の裁判所ホームページが参考になります。
詳細については、申立先の家庭裁判所にご確認ください。
遺産分割調停の注意点
遺産分割調停を申し立てるにあたって、注意しておくべき点をいくつか紹介します。
遺産分割調停ではできないこともある
遺産分割調停では、以下のようなことはできません。
- 養子縁組の効力を争う
- 遺言の効力を争う
- 相続人が隠匿している相続財産の存在を争う
それぞれ訴訟で争う必要があります。
調停委員が相続財産を調査することはありません。
調停では、当事者によって明らかにされた相続財産のうち、遺言や遺産分割協議によって取得者が決まっていないものについて、遺産分割の話し合いをします。
また、不動産などの相続財産の価格についても、鑑定という方法による以外は、当事者の合意した価格に基づいて話し合いを進めていくのが基本となります。
自分が希望する通りの価格で合意してもらえるとは限りませんのでご注意ください。
期待通りの分割とならない場合もある
一部の相続人と連絡が取れない場合、親族からの連絡には応じなくても、家庭裁判所からの通知には応じてくるケースもあります。
しかし、調停に相手方が出席しない場合や話し合いがまとまらなかった場合、調停は不成立となり審判手続に移行します。 審判では、裁判所が遺産分割の内容を決定します。
裁判所は、公平な立場で法律的な判断を示すことになるため、希望通りの分割とならない可能性がある点に注意が必要です。
遺産分割調停の申立ができない場合もある
また、以下のような場合は遺産分割調停の申立ができないため、注意が必要です。
- 相続人の行方がわからない場合
- 相続人が認知症で判断能力がない場合
- 相続人が未成年者で利益相反に当たる場合
相続人が行方不明の場合は、まず不在者財産管理人選任の申立や失踪宣告の申立をする必要があります。
相続人に認知症の方や未成年者がいる場合、成年後見人選任や特別代理人選任の手続が必要になる場合があります。
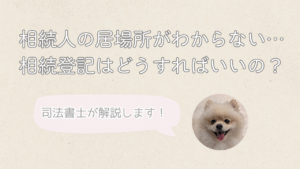
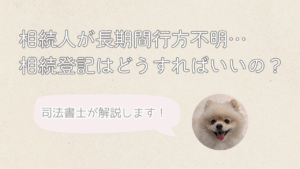
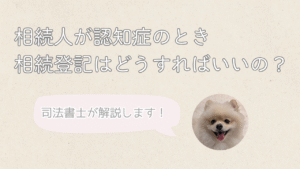
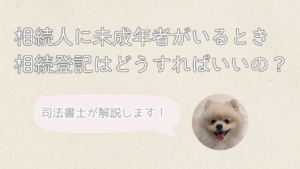
まとめ
連絡のとれない相続人がいる場合、遺産分割協議を有効に成立させることはできません。
このような場合に遺産分割調停の手続を利用して、うまくいけば調停成立、悪くても裁判所による審判というかたちで手続を前に進めることができます。
相続登記では、調停調書や審判書を法務局に提出します。
遺産分割調停には注意すべき点がいくつもあり、専門的な知識を要しますので、司法書士や弁護士に相談することをおすすめします。
なお、司法書士は裁判所に提出する書類の作成はできますが、手続代理人になることはできません。
代わりに調停に参加して話し合いを進めてほしい場合は、弁護士に相談しましょう。
この記事が参考になれば幸いです。
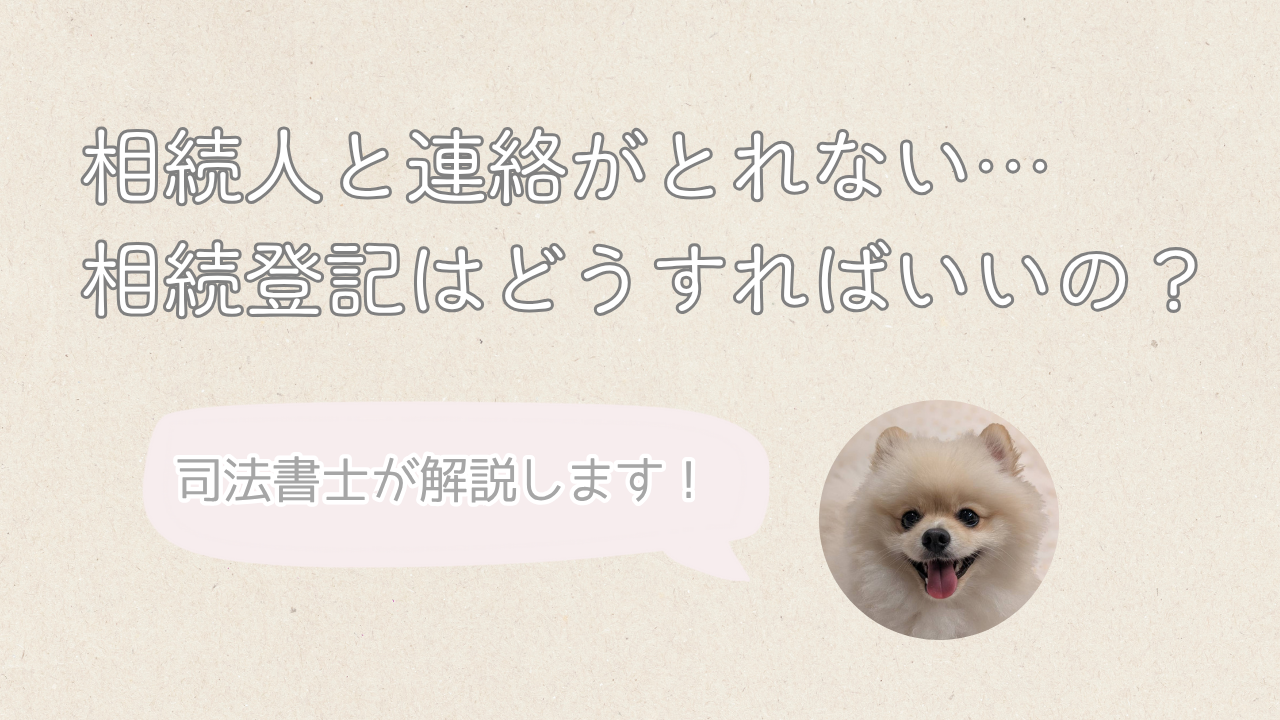
コメント