遺言書を発見した場合、まずは、家庭裁判所で「検認」という手続を行う必要があります。
これは、遺言書の存在と内容を明確にし、偽造や変造を防ぐためのものです。
相続登記では、遺言書とあわせて「検認済証明書」を法務局に提出する必要があり、これがないと登記をすることができません(※公正証書遺言や遺言書情報証明書を除く)。
この記事では、検認申立の流れと必要書類について解説します。
※本記事は、公開時点での法令等に基づいて作成されております。最新情報については、専門家にご相談いただくか、ご自身でご確認ください。
遺言書を確認する
すべての遺言書に検認が必要ではありません。以下の場合、検認は不要となります。
- 公正証書遺言
- 法務局で保管されている自筆証書遺言
これらは偽造や変造のおそれがないため、検認によってその状態を確定する必要がないと考えられているからです。
反対に、上記以外の遺言書はすべて検認が必要となります。
検認をしなかったら遺言が無効になるわけではありませんが、遺言書の保管者または発見者には検認の請求をすることが法律上義務付けられています。
検認の申立の流れ
検認の申立は、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して行います。
最後の住所地とは、亡くなったときの住所のことです。
下記の管轄検索ページから調べることができます。
必要書類
- 検認申立書
- 遺言者の出生から死亡までの戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
※相続関係により異なります。
手数料
- 印紙代(遺言書の通数×800円)
- 予納郵券(切手のこと。裁判所による)
必要書類と手数料は上記のとおりです。
手続の詳細は、各家庭裁判所のホームページなどでご確認ください。
検認申立書の書式・記載例も裁判所のホームページで確認できます。
検認期日に出席する
家庭裁判所から検認期日が相続人全員に通知されます。
申立をした相続人は、検認期日には原則として出席する必要があり、印鑑や裁判所から案内された書類を持参します。
申立人以外の相続人が出席するかは任意で、全員が揃わなくても手続は行われます。
期日では、相続人立会のもと、遺言書の開封、遺言書の状態の確認、内容の確認が行われます。
検認済証明書を取得する
検認手続が完了すると、家庭裁判所から「検認済証明書」が交付されます。
検認済証明書は、相続登記で必要となります。
検認済証明書の申請には印紙代が1通につき150円かかります。
遺言書に基づく相続登記については、こちらの記事も参考にしてください。
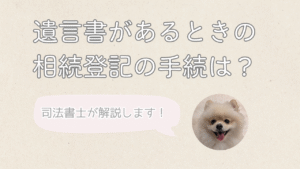
まとめ
遺言書を発見したら、開封せずに家庭裁判所に提出することが原則です。
勝手に開封した場合、罰則の規定があります。ただし、それによって遺言が無効となるわけではありません。
くり返しますが、検認は遺言書の有効性を判断するものではありません。遺言の内容に争いがある場合は、別途、遺言の有効性を争う手続が必要です。
検認申立手続は、相続人が自分で行うことも可能です。
ですが、相続関係が複雑で必要な戸籍を集められない場合など、必要に応じて司法書士や弁護士に依頼するのもおすすめです。
この記事が参考になれば幸いです。
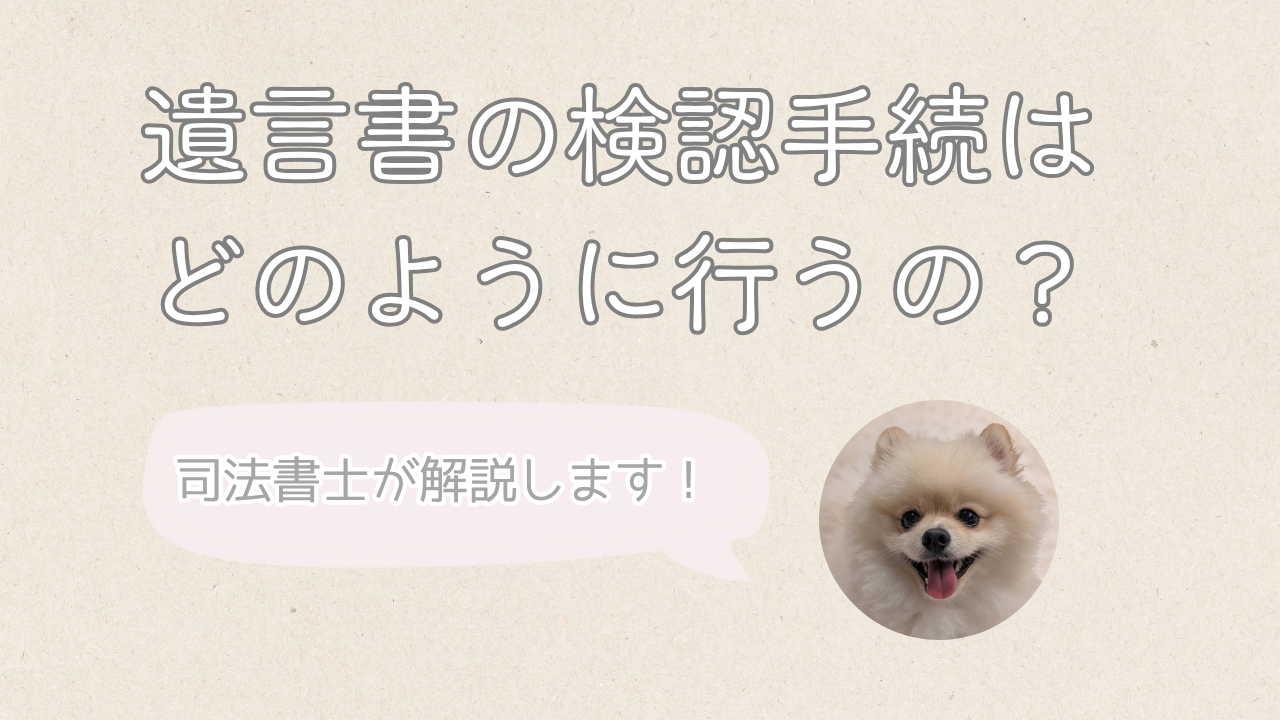
コメント