遺産を放棄したい理由にはいろいろあります。
何十年も会っておらず被相続人と疎遠だったり、多額の借金があるなど、相続したくない積極的な理由があるかもしれません。
遺産を放棄したい場合、とり得る手段はいくつかありますが、それぞれ全く異なる手続ですので違いを理解することが重要です。
この記事では、相続財産がいらない場合の手続として、相続分の譲渡と相続放棄について解説します。
※本記事は、公開時点での法令等に基づいて作成されております。最新情報については、専門家にご相談いただくか、ご自身でご確認ください。
相続分の譲渡とは?
相続人は、自分の相続分を他の相続人または相続人以外の第三者に譲渡することができます。
一部のみ譲渡することも可能で、有償・無償いずれの方法によっても行うことができます。
相続分の譲渡をするには
譲受人(相続人または第三者)との間で合意をすると効力が生じます。
後のトラブルを防ぐためにも契約書を作成するのが一般的です。
相続分の譲渡の注意点
- 債務は免れない
- 税務上の問題が起こり得る
後述する相続放棄とは異なり、被相続人の債権者から請求を受けた場合に、債務の履行を拒むことができません。
被相続人に借金があったとき、相続分を譲り渡したからといって、借金を返済する義務が完全になくなるわけではないということです。
また、相続人以外への相続分の譲渡は、贈与税の問題が生じるおそれがあります。また、有償による相続分の譲渡は、譲渡所得税の問題が生じるおそれがあります。
相続分の譲渡を検討する際は、適宜、税理士や所轄税務署の相談を受けるなど、税務上の問題には注意してください。
相続放棄とは?
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知ってから3カ月以内に、相続放棄の申述をすることができます。
相続放棄をすることで、初めから相続人ではなかったことになり、相続手続から離脱することができます。
相続放棄をするには
管轄の家庭裁判所に相続放棄申述書を提出します。
相続放棄の必要書類については、下記の裁判所ホームページをご確認ください。
相続放棄の注意点
- 期間が経過するとできない
- 法定単純承認をしているとできない
- プラスの財産も承継できない
相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知ってから3カ月以内に申述しなければなりません。
特別な事情がある場合は、3カ月経過した後も認められる場合もありますが、原則として相続放棄はできません。
法定単純承認というのは、相続財産を処分する等によって相続を承認したとみなされることです。
典型例は、預貯金を引き出して金銭を費消する行為が該当します。ただし、使用目的にもよりますので、預貯金に手をつけたら必ず放棄できないというわけではありません。
そして、相続放棄によって、申述人は初めから相続人ではなかったことになります。マイナスの財産はもちろん、プラスの財産についても相続することができません。
相続放棄申述受理の審判には既判力がなく、訴訟で効力を争う事態に発展する可能性がある点にも注意が必要です。
詳しくはこちらの記事をご覧ください。
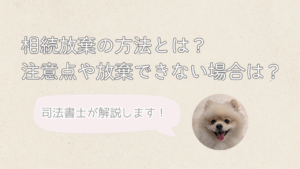
相続登記で必要な書類は?
相続人のうち、相続分の譲渡や相続放棄をした者がいる場合は、相続登記を申請する際に特別な書類を用意する必要があります。
具体的な内容は以下のとおりです。
相続分の譲渡をした場合
- 相続分譲渡証書
- 譲渡人の印鑑証明書
譲渡証明書には譲渡人の実印による押印が必要です。
司法書士に依頼すれば作成してもらえます。
相続放棄をした場合
- 相続放棄申述受理証明書
家庭裁判所で交付してもらうことができます。
申請には1通150円の印紙代がかかります。
必要書類については、相続放棄申述受理通知書と同封されている交付申請書に詳しく書いてあります。
まとめ
相続財産を放棄する方法として、相続分の譲渡と相続放棄を説明しました。
相続放棄は、初めから相続人ではなかったことになり、債権者から債務の履行を請求されても拒むことができるという大きなメリットがある一方で、家庭裁判所の手続が必要なため簡単にはできないという面があります。
相続分の譲渡は、当事者間の合意のみで成立しますが、債務について完全に免れることができない点や税務上の問題が起こり得る点に注意が必要です。
いずれの方法をとるにせよ、専門的な知識を要するため、司法書士や弁護士、税理士に相談するのがおすすめです。
この記事が参考になれば幸いです。
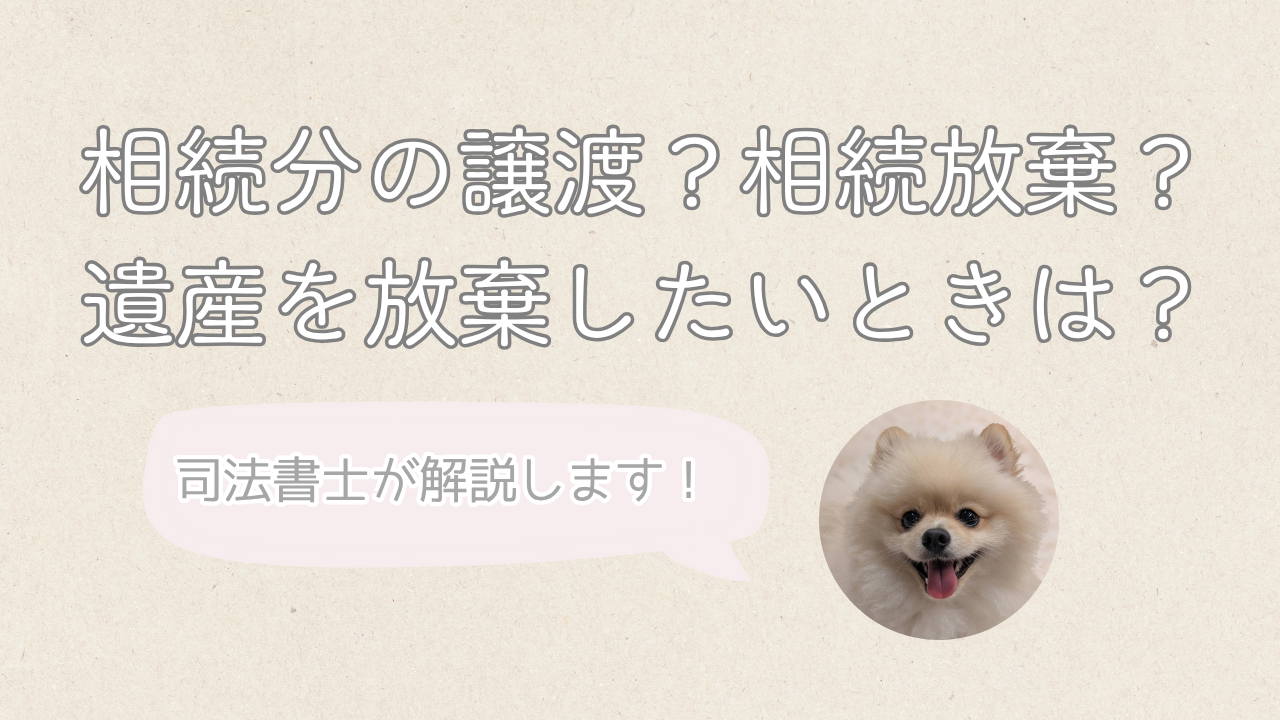
コメント