相続分とは、被相続人(亡くなった人)の相続財産について各相続人が有する割合のことです。
被相続人は、遺言で相続分を指定することができますが、相続分の指定がなかった場合には、民法の規定によって相続分が決まります。
この記事では、相続分がどのように決まるのかについて解説します。
※本記事は、公開時点での法令等に基づいて作成されております。最新情報については、専門家にご相談いただくか、ご自身でご確認ください。
相続分って?
(共同相続の効力)
第八百九十八条 相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。
2 相続財産について共有に関する規定を適用するときは、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分をもって各相続人の共有持分とする。
第八百九十九条 各共同相続人は、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継する。
(引用元:民法|e-Gov法令検索)
相続が開始すると、相続財産は原則として相続人の共有となります。
相続分とは、相続財産に対して各相続人が有するの割合のことです。
相続分には、被相続人の遺言によって指定される「指定相続分」と、民法の規定によって決まる「法定相続分」があります。
遺言がある場合は?
(遺言による相続分の指定)
第九百二条 被相続人は、前二条の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる。
2 被相続人が、共同相続人中の一人若しくは数人の相続分のみを定め、又はこれを第三者に定めさせたときは、他の共同相続人の相続分は、前二条の規定により定める。
(引用元:民法|e-Gov法令検索)
被相続人が遺言で相続分を指定していた場合は、民法の規定に優先して相続分が決まります。
被相続人の意思を優先させるわけですね。
例えば、被相続人の相続人が子ABCの3人であり、子Aの相続分を1/2と指定したとします。
この場合、子Aの相続分は1/2、子BCの相続分はそれぞれ1/4となります。
本来であれば子ABCの相続分は各1/3ずつですが、被相続人の意思によって、上記のように相続分が決まります。
なお、このように相続人の一部のみについて相続分を指定することも可能です。
また、相続分を指定することを第三者に委託することもできます。
法定相続分の決まり方は?
(法定相続分)
第九百条 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
(引用元:民法|e-Gov法令検索)
遺言による相続分の指定がなされていない場合は、民法の規定によって相続分が決まります。
法定相続分の決まり方は以下のとおりです。
配偶者と子が相続人の場合
法定相続分は、配偶者1/2、子1/2です。
子が複数いる場合は、1/2を等しく分けます。
例えば、子が3人の相続分はそれぞれ1/6ずつとなります。
実子と養子で相続分に違いはありません。
また、平成25年の改正により、非嫡出子と嫡出子の相続分も変わらなくなりました。
ただし、平成13年7月以前に開始した相続については、改正前の規定によって相続分が判断されることになります。
ご興味があれば、法務省のページをご覧ください。
配偶者と直系尊属が相続人の場合
法定相続分は、配偶者2/3、直系尊属1/3です。
直系尊属が複数いる場合は、1/3を等しく分けます。
例えば、父と母の相続分はそれぞれ1/6となります。
被相続人が養子である場合は、養親だけでなく、実親も相続人となりますが(特別養子の場合は養親のみが相続人となります)、養親と実親で相続分に違いはありません。
配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合
法定相続分は、配偶者3/4、兄弟姉妹1/4です。
兄弟姉妹が複数いる場合は、原則として、1/4を等しく分けます。
例えば、兄と妹の相続分はそれぞれ1/8となります。
しかし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の半分です。
半血のきょうだいは、全血のきょうだいと比べて血のつながりが薄いため、法定相続分も少なくなっているのです。
代襲相続人がいる場合
代襲相続人の相続分は、被代襲者と同じです。
被相続人の子ABがいて、Aがすでに亡くなっている場合、Aの子(被相続人の孫)CDが代襲相続人となります。
A(被代襲者)の相続分1/2を引き継ぎ、孫CDの相続分は二人合わせて1/2となります。
同順位の相続人の相続分は等しいため、孫CDの相続分はそれぞれ1/4となります。
まとめ
相続分がどのように決まるのかについて、民法の規定を簡単に説明しました。
まずは、遺言による指定が優先し、相続分の指定がない場合は、民法の規定によって相続分が決まります。
法定相続分の計算は、遺留分や具体的相続分を計算する際にも必要となるので、理解しておくと役に立ちます。
この記事が参考になれば幸いです。
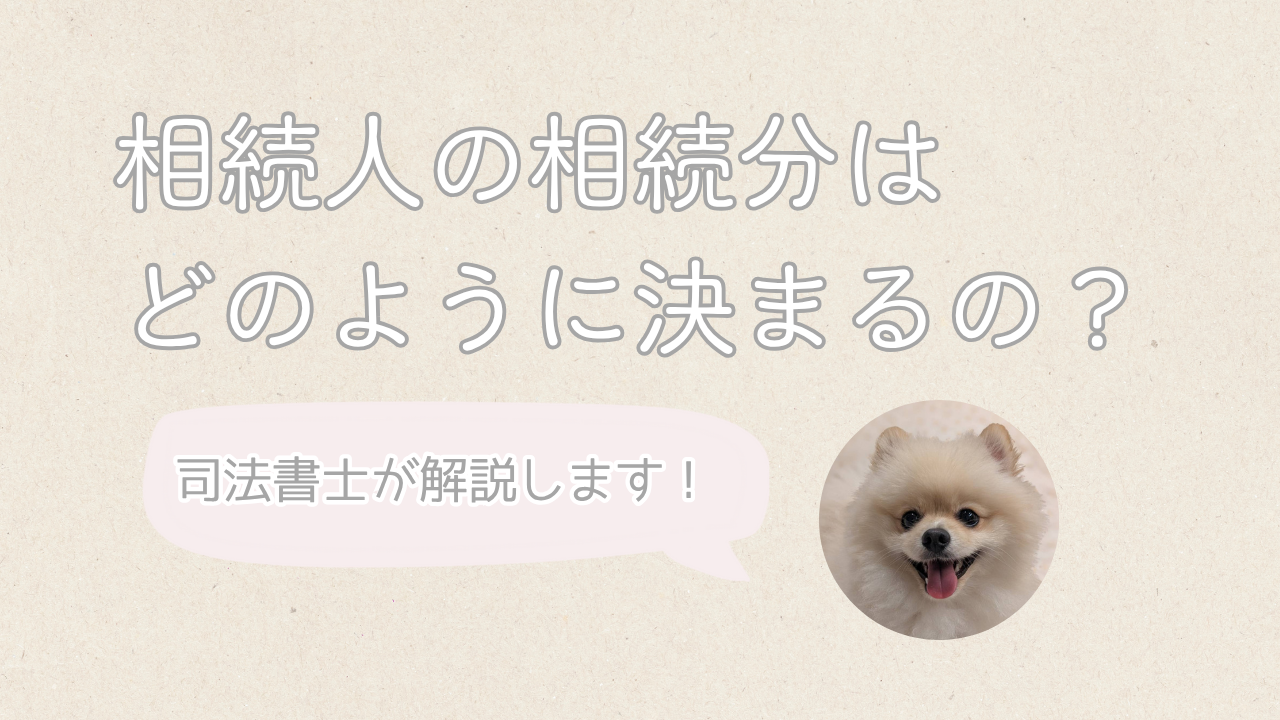
コメント