相続放棄をしたい人の数は、年々増えています。
相続放棄とは、相続財産を一切承継しないと家庭裁判所に申し立てる手続です。
裁判所の手続ですので、わかりにくいことも多いかと思います。この記事では、相続放棄の基本について解説します。
※本記事は、公開時点での法令等に基づいて作成されております。最新情報については、専門家にご相談いただくか、ご自身でご確認ください。
相続放棄でよくある誤解
いきなりですが、まずは相続放棄の相談でよくある誤解について、2つご紹介します。
一定数の方が同じ誤解をされているので、間違えやすいところなのだと思います。
相続放棄したはずなんだけど?
1つ目は、「相続放棄したと思い込んでいる」です。
他の相続人に対して「自分は何も要らない」と意思表示をしたり、他の相続人が一切の相続財産を取得する内容の遺産分割協議書等に押印をすることで、自分は相続放棄をしたと思っている方は多いです。
しかし、「相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない(民法938条)」とあるように、相続放棄をするためには、家庭裁判所に申述する必要があります。
家庭裁判所を通さない手続では相続放棄の効力が認められず、将来的に自分や自分の相続人がトラブルに巻き込まれるおそれがあります。
被相続人が生きている間に放棄できる?
2つ目は、「被相続人が亡くなる前に相続放棄できると思っている」です。
借金などのマイナスの財産の方が多いことがわかっている場合や被相続人との関係性から一切の財産を承継しないことを決めている場合、あらかじめ手続をしておきたいという気持ちはわかります。
しかしながら、相続放棄の申述は、被相続人が亡くなった後でなければ行うことができません。
被相続人が生きている間に放棄することはできませんので、ご注意ください。
さて、次から相続放棄の手続の内容に入っていきます。
いつまでに手続しないといけないの?
(相続の承認又は放棄をすべき期間)
第九百十五条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
2 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。
(引用元:民法|e-Gov法令検索)
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に、相続放棄の申述をしなければなりません。
相続財産を調査したうえで、相続を単純承認するか、限定承認するか、放棄するかをよく考え検討することから「熟慮期間」といいます。
熟慮期間が過ぎると、原則として単純承認したことになりますので(民法921条2項)、相続放棄をすることはできません。
借金が後から発覚した場合などは例外的に認められるケースもありますが、専門家による判断が必要です。
自己のために相続の開始があったことを知った時っていつなの?
非常にわかりにくいですが、次の2つが揃ったときであると解釈されています。
- 被相続人が亡くなったことを知った
- 自分が相続人になったことを知った
熟慮期間の起算点は、相続人ごとに考えます。
また、相続人を保護するため、起算点を遅らせる解釈がなされています。
よって、被相続人が死亡してから3カ月経過しているからといって、絶対に相続放棄ができないというわけではありません。
一度専門家に相談することをおすすめします。
相続放棄ができないケースは?
(法定単純承認)
第九百二十一条 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
二 相続人が第九百十五条第一項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
三 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。
熟慮期間内に相続放棄の申述をしなかった場合はもちろんですが、以下のような場合も法律上単純承認をしたものとみなされるため、相続放棄をすることができません。
- 相続財産を処分したとき
- 相続財産を隠匿し、私に消費したとき
順番に説明します。
相続財産を処分したとき
相続財産を処分したときは、相続放棄をすることができません。
- 預貯金を引き出して使用した場合
- 不動産を売却した場合
- 建物を取り壊した場合
- 賃料を取り立てた場合
例えば、上記のような場合が当たります。
他にもさまざまな例がインターネット上では散見されます。
しかし、実際に単純承認とみなされる処分行為に当たるかどうかは、個別の事案ごとの判断となるため、まずは専門家に相談することをおすすめします。
相続財産を隠匿し、私に消費したとき
こちらは相続放棄をした後の話です。
相続財産を隠したり、被相続人に借金があることを知りながら現金を使い込んだりした場合は、単純承認したことになり、相続放棄の効果が失われます。
具体的にどのような行為が「隠匿」や「私に消費」に該当するかは、やはり、個別の事案ごとの判断となるため、専門家に相談することをおすすめします。
手続の流れ
まずは、必要書類を集めます。
裁判所のホームページでは、被相続人との関係性ごとに必要な書類が案内されているので、こちらをご参照ください。
必要書類を集めたら、申述書を作成します。
申述書のひな形は裁判所のホームページからダウンロード可能です。
記入例(同じページから閲覧可能)を参考に作成します。
申述書ができたら、必要書類と一緒に家庭裁判所に提出します。
この際、印紙の貼付と切手を同封することを忘れないようにしましょう。
(必要な切手の金額及び枚数は管轄ごとに異なるため事前に確認します)
管轄は、「被相続人の最後の住所地」によって定まります。
こちらのページから簡単に調べられます。
提出してからしばらくすると、家庭裁判所から封書が届きます。
同封されている回答書に記入をして、返送します。
まれに照会書が届かず、STEP5の受理通知書が届くことがあります。
一定期間内に返送しなければ相続放棄は却下されますのでご注意ください。
受け取るのが難しそうな場合、問い合わせればいつ頃届く予定かを教えてくれますが、家庭裁判所も忙しいので、むやみやたらと問い合わせるのは避けてください。
回答書を返送してからしばらくすると、家庭裁判所から封書が届きます。
中には、相続放棄申述受理通知書と相続放棄申述受理証明書に関する案内が同封されています。
相続放棄申述受理通知書はペライチの紙であるため(しかも三つ折りにされている)、大事な書類という感じがしないのですが、再発行がきかないため、大切に保管してください。
相続放棄の効果
(相続の放棄の効力)
第九百三十九条 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。
(民法|e-Gov法令検索)
相続放棄が受理されると、申述人は、初めから相続人でなかったことになります。
借金の取り立てや滞納賃料の支払いなど、相続人として負うべき債務から解放されます。
当然、相続財産は、プラスの財産も含めて一切相続することができません。
また、次順位の相続人(子が放棄すれば親や兄弟姉妹など)に相続権が移ります。
注意点
相続放棄の注意点として、以下の3つをご紹介します。
- 後から撤回することができない
- 他の相続人との争いが生じ得る
- 相続放棄の記録は30年しか保存されない
後から撤回することができない
一度相続放棄をすると、撤回することができません(民法919条1項)。
たとえば、借金しかないと思っていたら過払いがあることが判明したり、後からプラスの財産があることが明らかになった場合であっても、相続放棄をとり止めることはできません。
そのため、相続放棄の前に相続財産を十分に調査しておくことが重要です。
他の相続人との争いが生じ得る
相続放棄によって、他の相続人の法定相続分や誰が相続人となるかが変更する場合があります。
相続放棄すると、他の相続人の法定相続分が増えますが、それを好まない相続人がいれば、結果として対立してしまうこともあります。
また、相続放棄によって次順位の相続人に相続権が移る場合は、家庭裁判所から通知がされるといったことは一切ありません。
相続人だということを知ったときには、すでに何らかの問題が発生しているという可能性もあります。
法的に何かを請求されることは考えにくいとしても、感情的な対立が生じる可能性は否定できません。
相続放棄の記録は30年しか保存されない
相続放棄の記録が家庭裁判所で保存されるのは、30年です。
30年を経過し記録が廃棄されると、家庭裁判所で相続放棄をしたことが確認できなくなります。
そのため、相続放棄申述受理通知書の原本は大切に保管しておかなければなりません。
30年経過した後は、相続放棄したことを証明するために、客観的な証拠として相続放棄申述受理通知書が必要となるからです。
また、相続放棄申述受理証明書を推定相続人の人数分取得して、各自に渡しておくという対策も有効かもしれません。
まとめ
この記事では、相続放棄の期限や手続の流れ、注意点について解説しました。
相続放棄の件数は増加傾向にあり、今後も増加することが予想されています。
現行の民法では、相続が開始した後、熟慮期間内に相続の承認・放棄を選択できる制度になっており、誰かの許可を得たりすることなく自由に手続を進めることができます。
裁判所の手続なので少しハードルが高く感じるかもしれませんが、相続放棄を検討されているなら、まずは専門家に相談してみることをおすすめします。
この記事が参考になれば幸いです。
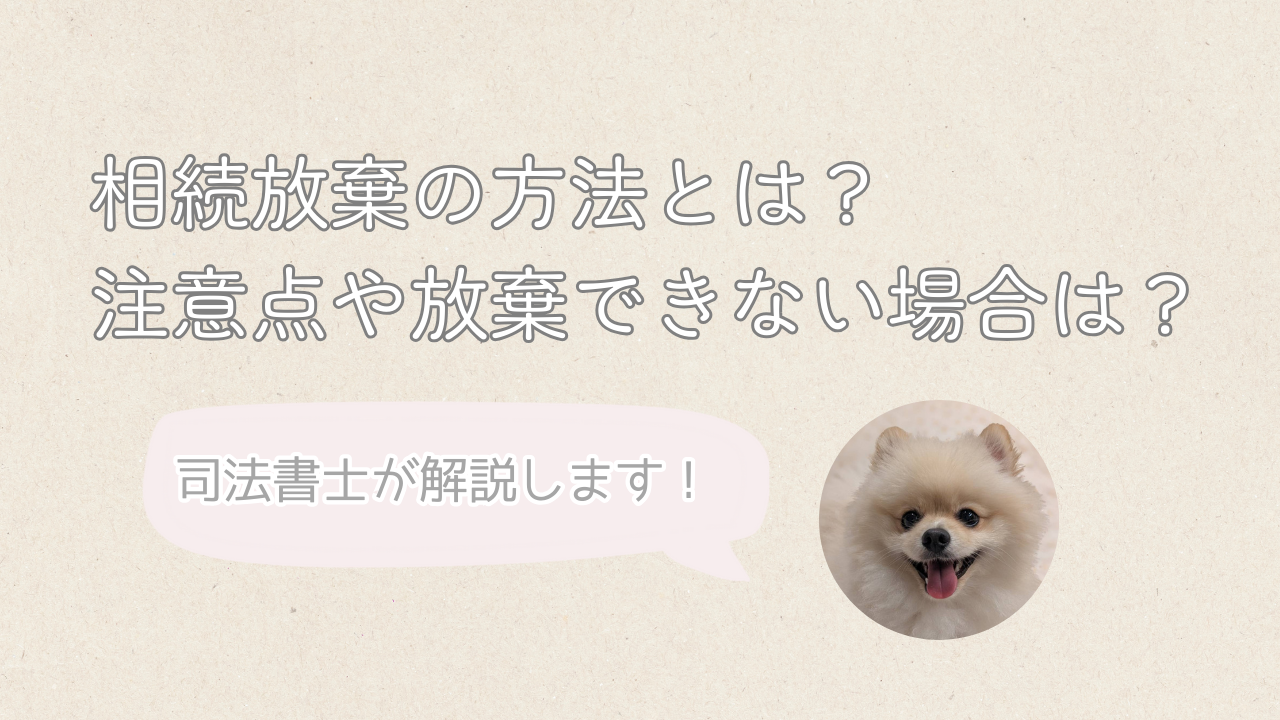
コメント