相続放棄をしようとする場合、自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。
しかし、3カ月以内に手続を行うことができない事情がある場合は、期間の伸長を申し立てることが可能です。
この記事では、相続の承認・放棄の期間伸長申立の手続の流れ、注意点について解説します。
※本記事は、公開時点での法令等に基づいて作成されております。最新情報については、専門家にご相談いただくか、ご自身でご確認ください。
熟慮期間伸長の申立とは?
(相続の承認又は放棄をすべき期間)
第九百十五条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
2 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。
(民法|e-Gov法令検索)
熟慮期間とは?
相続放棄を申述することができる期間は、法律によって定められています。
この期間を「熟慮期間」といい、相続するか放棄するかを考えるために与えられた猶予期間です。
熟慮期間を経過すると、原則として、相続を承認したものとみなされ、相続放棄はできなくなってしまいます(民法921条2号)。
熟慮期間伸長の申立とは?
ところが、3カ月以内に相続の承認・放棄の選択ができない場合もあります。
なんらかの事情で、相続財産の調査を十分に行うことができない場合です。
そのような場合に、家庭裁判所に申し立てることで、熟慮期間を延長してもらうことが可能です(民法915条1項)。
これが認められれば、追加で数カ月間の調査・検討を行うことができます。
期間を伸長することができるのは?
どのような場合に期間伸長の申立ができるの?
期間伸長の申立が可能なのは、被相続人の財産を調査するのに時間的猶予が必要な場合です。
遠方に不動産がある場合や、相続人が海外に住んでいたり、病気やケガで入院している場合など、さまざまな事情により、熟慮期間内に相続財産の調査を完了することができない場合があります。
このような場合に、期間伸長の申立が可能です。
家庭裁判所は、諸般の事情を考慮して総合的に判断します。
自分のケースで期間の伸長が認められるか不安な場合は、専門家にご相談ください。
いつまで延長してもらえるの?
大体、3カ月程度の期間伸長を行うことが多いです。
当初の3カ月に加えて、さらに3カ月あれば、相続財産の調査には十分である場合がほとんどです。
伸長を求める期間は、相続財産の調査に必要な時間として相当な期間であることが重要です。
期間の相当性については、相続財産の状況など個別の判断になるので、専門家にご相談ください。
申立の流れ
まずは、必要書類を集めます。
裁判所のホームページでは、被相続人との関係性ごとに必要な書類が案内されているので、こちらをご参照ください。
必要書類を集めたら、申立書を作成します。
申立書のひな形は裁判所のホームページからダウンロード可能です。
記入例(同じページから閲覧可能)を参考に作成します。
申述書ができたら、必要書類と一緒に家庭裁判所に提出します。
この際、印紙の貼付と切手を同封することを忘れないようにしましょう。
(必要な切手の金額及び枚数は管轄ごとに異なるため事前に確認します)
管轄は、「被相続人の最後の住所地」によって定まります。
こちらのページから簡単に調べられます。
提出してからしばらくすると、家庭裁判所から封書が届きます。
同封されている回答書に記入をして、返送します。
また、照会書が届かずSTEP5の審判書が届くこともあります。
照会書が届く場合、一定期間内に返送しなければ申立は却下されますのでご注意ください。
申立から2週間程度ですが、家庭裁判所により異なります。
受け取るのが難しそうな場合、問い合わせればいつ頃届く予定かを教えてくれますが、家庭裁判所も忙しいので、むやみやたらと問い合わせるのは避けてください。
回答書を返送してからしばらくすると、また家庭裁判所から封書が届きます。
中には、タイトルに「審判」と書かれた紙が同封されています。
申立書に記載した通り期間の伸長がなされているか、ご確認ください。
申立の注意点
相続の承認・放棄の期間伸長申立の注意点として、2つご紹介します。
- 熟慮期間内に申立を行う必要がある
- 税申告は延長されない
熟慮期間内に申立を行う必要がある
熟慮期間が経過する前に申立てを行う必要があります。
期限を過ぎてしまうと延長はできず、原則として相続を承認したものとみなされます。
戸籍等の必要書類が完全に揃わない場合は、ひとまず用意できたものだけを添付して申立をすることができます。
不足書類は追加で提出することで、問題なく手続を進めることが可能です。
税金の申告期限は延長されない
相続に関する税申告には、期限があります。
- 準確定申告(4カ月)
- 相続税申告(10カ月)
税金の申告期限は、相続の承認・放棄の期間伸長申立が認められても、延長されません。
期限を徒過した場合、相続放棄をすれば税申告は不要となりますが、かりに相続の承認(または限定承認)を行った場合は、期限後申告といって無申告加算税や延滞税等を支払うことになります。
税金の申告期限は、熟慮期間とは別の話なのでご注意ください。
まとめ
相続放棄を検討しており、財産や負債の全容がわからない場合、まずは相続の承認・放棄の期間の伸長を申し立てることができます。
手続は比較的シンプルですが、熟慮期間内に申立を行うことが重要です。
また、期限が迫っているからといって調査をおろそかにして相続の承認・放棄を決めてしまうのは、後になって予想外のトラブルを招くことにつながりかねないため、くれぐれも慎重に判断すべきです。
自分で進めることが不安な場合には、司法書士や弁護士に相談することをおすすめします。
この記事が参考になれば幸いです。
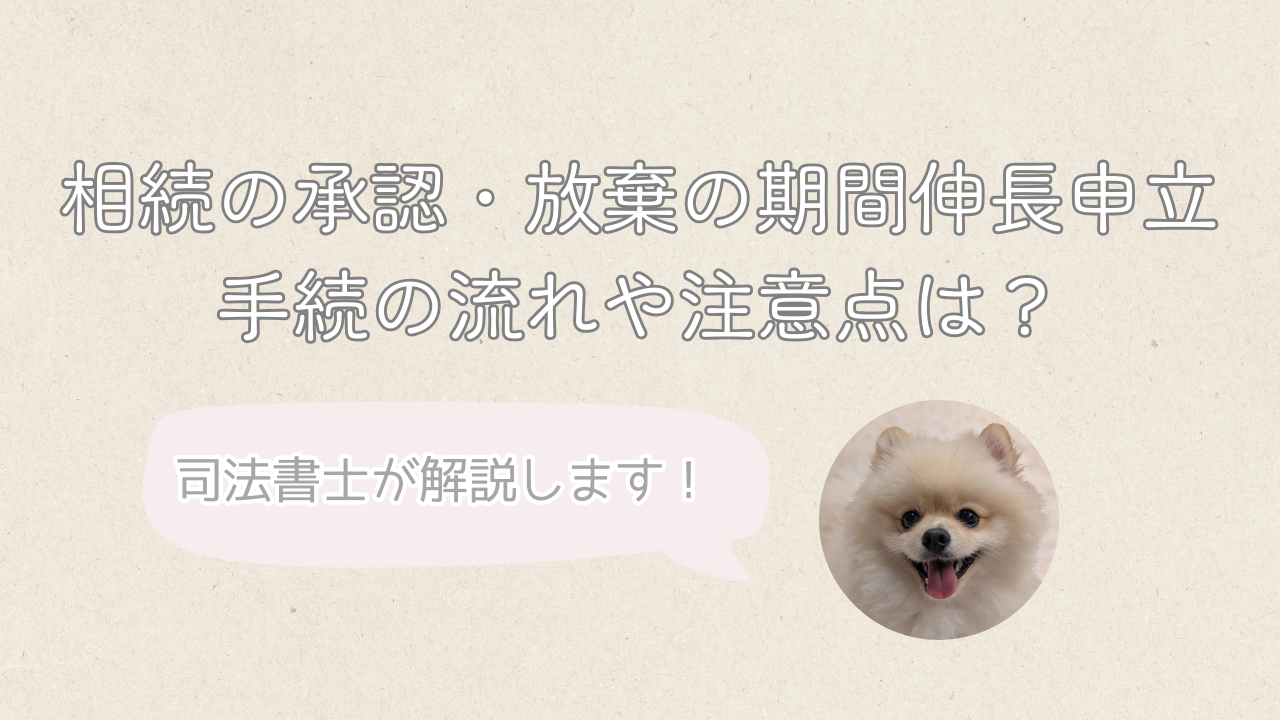
コメント