一般に、相続の開始があった(被相続人が亡くなった)ことを知った時から3カ月以内に手続をしなければ、相続放棄はできないとされています。
しかし、被相続人が亡くなってからとっくに3カ月経過している場合でも、相続放棄が認められることがあります。
この記事では、3カ月以上経過していても相続放棄ができる場合について解説します。
※本記事は、公開時点での法令等に基づいて作成されております。最新情報については、専門家にご相談いただくか、ご自身でご確認ください。
相続放棄の3カ月ルール
相続放棄の3カ月ルール
相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内(熟慮期間)に、家庭裁判所に申述を行わなければなりません(民法915条1項、938条)。
通常、被相続人が亡くなったことを知った時から3カ月以内に申述するのが、相続放棄の基本です。
3カ月経過するとどうなるのか
何もせずに熟慮期間を過ぎると、原則として、単純承認したものとみなされます(民法921条2号)。
単純承認とは、被相続人のすべての権利義務を承継するということです(民法920条)。
3カ月経過すると単純承認とみなされ、被相続人の相続財産をすべて承継します。
典型的な「相続放棄できない」パターン
相続放棄(または限定承認)を行うことなく3カ月経過した場合のほか、被相続人の財産をつかってしまった場合も、相続放棄はできません。
財産を処分すると、単純承認したものとみなされるからです(民法921条1号)。
すでに預貯金を引き出して使用したというのが典型的なパターンですね。
ただし、どの行為が財産の処分に当たるのかは、個別の事案ごとの判断となりますので、専門家にご相談ください。
なぜ3カ月経過後に相続放棄ができるの?
単純承認にならないの?
熟慮期間が経過すると単純承認になるのなら、なぜその後に相続放棄ができるの?と疑問に思われたかもしれません。
それは、相続人を保護するために熟慮期間の起算点を遅らせる解釈がなされているからです。
起算点とは、期間が進行する時点のことです。
つまり、スタート地点を遅らせることによって、
- 熟慮期間が経過した後でも相続放棄ができる
のではなく、
- 熟慮期間である3カ月は経過していない
ということになります。
そのため、単純承認にはなりません。
次で少し詳しく説明しますね。
熟慮期間の起算点を遅らせる解釈とは?
現在、民法915条の条文は次のように解釈されています。
熟慮期間起算点の「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、
- 被相続人が亡くなったこと
- 自分が相続人になったこと
の両方を知った時のことを指します。
そのため、被相続人が亡くなったことを知りながらも自分が相続人であることを知らなかったような場合は、自分が相続人であることを知った時点から熟慮期間が進行します。
数十年前の相続でも放棄できる場合がある?
上記が原則で、例外もあります。
- 相続財産が全く存在しないと信じた
- 相続財産の有無の調査を期待できない事情がある
- 相続財産がないと信じたことに相当な理由がある
これらの要件をすべて満たす場合、相続財産の存在を認識した時か、通常認識できた時から起算します。
これによって、数十年前に開始した相続について相続放棄が認められる場合もあります。
個別の事案ごとの判断となりますので、専門家にご相談ください。
注意点
相当な理由が必要
熟慮期間の起算点を遅れさせるのは、あくまでも例外的な取扱いであり、反対の意見もあります。
かつて、法定単純承認を悪用して、熟慮期間が経過するのを待ってから借金の返済を請求する事例が多発しました。
請求を受けた相続人は借金の存在を知らなかったとしても、熟慮期間経過により単純承認したものとみなされ、請求に応じざるを得ませんでした。
そこで、相続財産がないと信じたことに相当の理由がある場合に限って起算点を遅らせることによって、相続人を保護することにしたんですね。
相当な理由がない場合、原則通り熟慮期間が起算されます。
家庭裁判所の判断による
相続放棄を認めてもよいかは家庭裁判所によって審査されます。
被相続人との関係性や相続放棄に至った経緯など具体的な事情を家庭裁判所に説明しなければなりません。
審査の結果、相続放棄の申述が受理されない可能性もあります。
相続放棄ができるかどうかは、あくまで家庭裁判所による判断次第だという点には注意が必要です。
すぐに相談するべき
相続財産の存在を知らなかった場合でも、その存在を認識した時点で熟慮期間は進行します。
相続人や債権者から相続に関する連絡を受けたとき、自分には関係がないと放置するのは危険です。
こうした連絡を受けた時点で熟慮期間が進行してしまう可能性があるからです。
そのまま3カ月が経過すると単純承認とみなされ、今度こそ相続放棄ができなくなってしまいます。
すぐに専門家へ相談することをおすすめします。
まとめ
相続放棄は原則として、被相続人が死亡したことを知った時から3カ月以内に手続きしなければなりません。
しかし、例外的に、3カ月経過した後も相続放棄できる場合があります。
この記事では、相続の承認・放棄の熟慮期間の起算点に関する解釈について解説しました。
相続放棄が認められるかは個別の事案ごとに検討が必要ですので、司法書士や弁護士にご相談ください。
この記事が参考になれば幸いです。
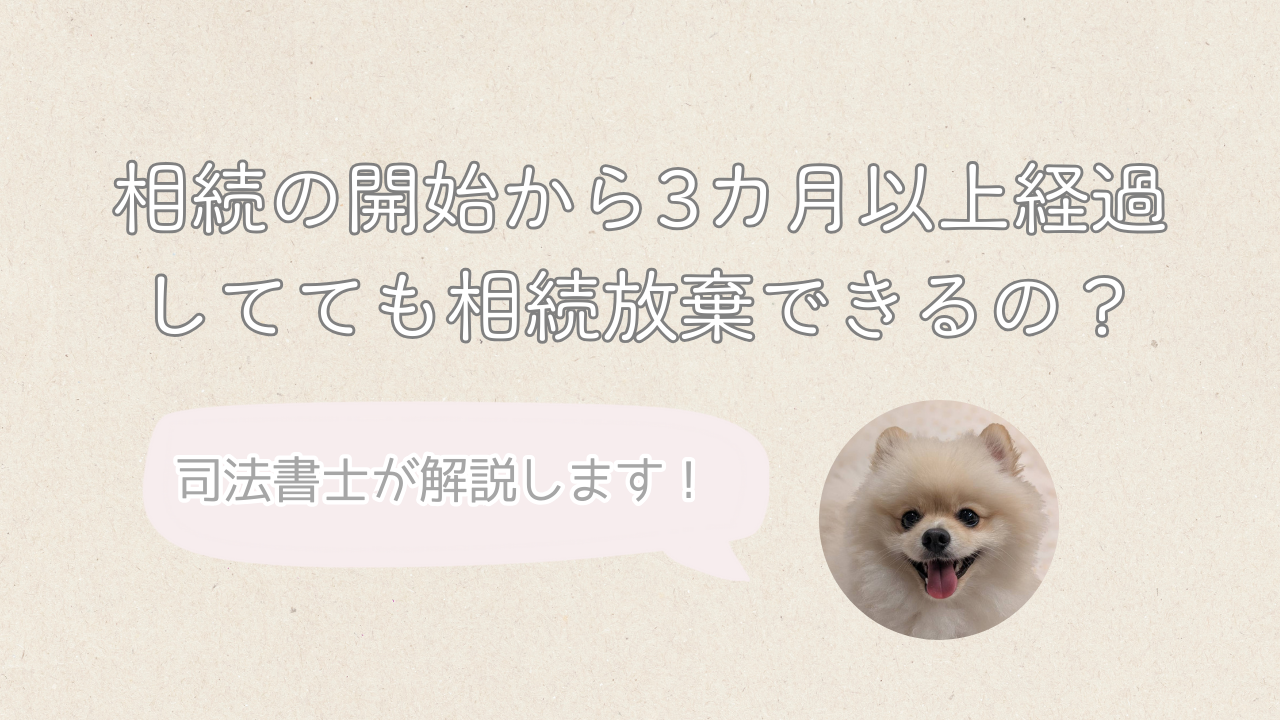
コメント