被相続人(亡くなった方)が遺言書を残していた場合、通常の相続登記とは手続の流れが異なります。
遺言による相続登記手続は、遺言の内容と、遺言執行者の有無によって異なるため、注意が必要です。
この記事では、遺言による相続登記をする場合の全体的な流れと相続登記の方式について解説します。
※本記事は、公開時点での法令等に基づいて作成されております。最新情報については、専門家にご相談いただくか、ご自身でご確認ください。
遺言書の形式を確認する
まずは、遺言書の形式を確認します。
公正証書遺言または自筆証書遺言保管制度による遺言書情報証明書以外は、「検認」という家庭裁判所の手続が必要となります。
遺言書の保管者または発見者には、検認を請求することが法律上義務付けられていて、相続登記では、遺言書とあわせて「検認済証明書」を提出する必要があるからです。
検認手続についてはこちらの記事をご参考ください。
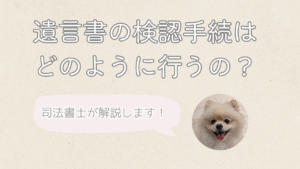
遺言書の内容を確認する
遺言書の内容によって、登記の申請方式、必要書類や登録免許税が異なります。
包括遺贈か特定遺贈か
遺贈には、「包括遺贈」と「特定遺贈」があります。
判別方法は、遺贈の対象となる財産が特定されているかどうかです。
〇〇に1/4の財産を遺贈します
という内容だった場合、遺贈の対象となる財産が特定されていないため、包括遺贈です。
特定の財産のみ取得させる特定遺贈とは異なり、まるっと割合で(または全部の財産が)遺贈の対象に含まれます。
遺贈の対象となる財産が農地である場合など、包括遺贈と特定遺贈の違いは大きなポイントになります。
受遺者が相続人か相続人以外か
〇〇に1/4の財産を相続させます
と書かれていたとしても、受遺者(遺贈を受ける人)が相続人ではない場合、「相続」を原因とする登記を申請することはできません。
この場合は、「遺贈」を原因とする登記を申請することになります。
通常の相続登記とは登記の申請方式と登録免許税が異なり、共同申請・登録免許税の税率2%となります。
登記の申請方式を確認する
相続登記は相続人が一人で申請できるのが基本ですが、遺言による相続登記では共同申請が基本となります。
ただし、受遺者が相続人である場合は単独申請によって行うことが可能です。
受遺者が相続人である場合
受遺者が単独申請により行います。
単独申請とは、登記権利者が一人で登記を申請できることで、共同申請による場合と異なり、相続人全員が手続に参加する必要がなくなります。
2023年4月から、特定財産承継遺言の場合に限らず遺贈の場合でも、受遺者である相続人が単独申請できるようになりました。
受遺者が相続人ではない場合
受遺者が相続人ではない場合の登記申請方式は、いずれも共同申請となります。ただし、遺言執行者がいる場合といない場合で申請人が異なります。
遺言執行者がいる場合
受遺者と遺言執行者による共同申請により行います。
登記書類には、遺言執行者が実印で押印し、遺言執行者の印鑑証明書を提出します。
相続人が手続に直接関与することなく登記手続を進めることが可能です。
遺言執行者がいない場合
受遺者と相続人全員による共同申請により行う必要があります。
相続人の協力が必要となるため、場合によっては裁判手続を経る必要が出てくるかもしれません。
必要書類を揃える
遺言による相続登記の必要書類は以下のとおりです(相続人が受遺者である場合の一例)。
- 遺言書(検認済みのもの)
- 遺言者の死亡の記載がある戸籍
- 遺言者の住民票の除票
- 相続人であることを証する戸籍
- 受遺者の住民票
- 固定資産評価証明書
申請書の書き方については、法務局の登記手続ハンドブックが参考になりますので、ご確認ください。
まとめ
この記事では、遺言書がある場合の相続登記について解説しました。
遺言書に基づく相続登記は、
- 遺言書の内容
- 誰が受遺者なのか(相続人か第三者か)
- 遺言執行者がいるかどうか
により、申請方式や必要書類が異なります。
受遺者が相続人以外の第三者であっても、相続人全員と共同で申請すれば登記は可能です。
ですが、相続人全員の協力が得られない場合は、遺言執行者の選任を申し立てるなど裁判手続を経る必要が出てくる場合もあります。
遺言書がある場合の相続登記は、専門的な知識を要する場合も多く、司法書士や弁護士に相談することをおすすめします。
この記事が参考になれば幸いです。
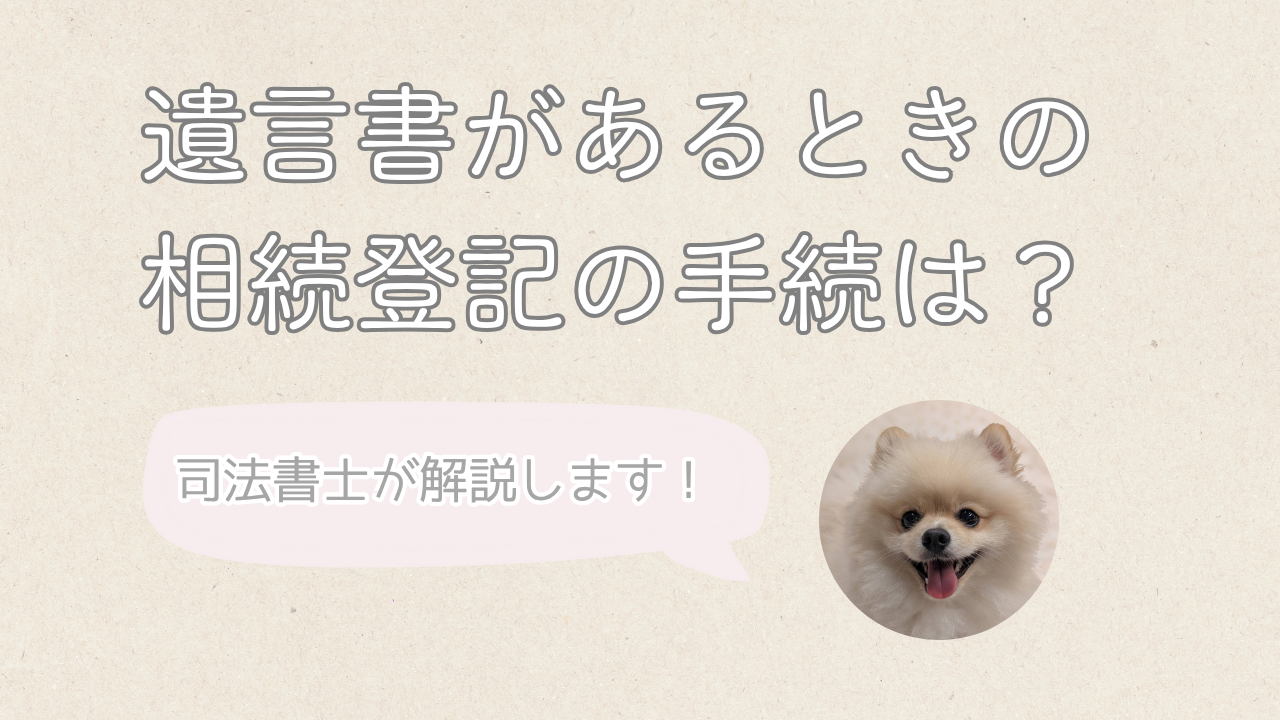
コメント